お墓参りに行く時期や時間帯はいつが正解?必要な持ち物と流れも解説
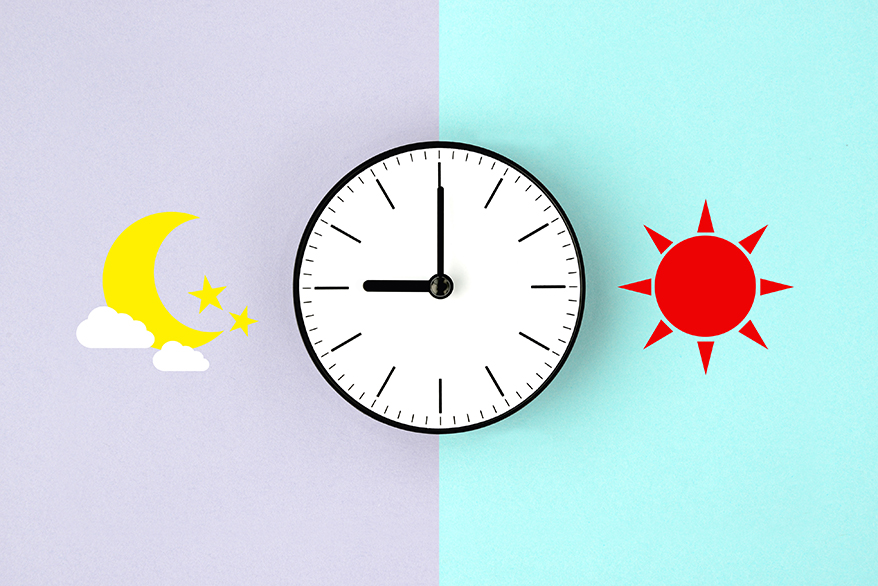
お墓参りの流れやマナーは、お墓参りの習慣がなかった方にとっては馴染みがないでしょう。お墓参りには行っても親の言うことに従っていただけで、実はよくわかっていないという方もいるでしょう。そこでお墓参りにいくタイミングや時間、持ち物、一連の流れなどを解説します。
(目次)
●お墓参りに適切な時間帯
●お墓参りを避けた方がよい時間帯
●お墓参りに行く時期やタイミング
●お墓参りの服装や持ち物
●お墓参りの流れ
●いつでも訪れやすい「證大寺」のお墓参り
●まとめ
お墓参りに適切な時間帯

お墓参りは自分の都合の良い時に行っても問題ありませんが、お墓参りに最適な時間帯は存在するでしょうか?
本来、時間の決まりはない
「お墓参りは午前中に行くべき」という意見を聞いたことはありませんか?これは、故人や先祖の供養に繋がるために、他の用事よりもお墓参りを優先すべきだとする考えからきています。朝の清々しい時間にお墓参りをすることで、気分がよくなるといった理由がありますが、本来、お墓参りの時間に厳格な決まりはありません。
ただし「ついで参り」は避けるべきとされています。ついで参りとは、他の用事のついでにお墓参りに行くことをさします。他に用事があるときは、お墓参りをメインとしてまずお参りし、その後に他の用を済ませるようにしましょう。
基本的には日中の明るい時間帯にお墓参りするのがおすすめ
お墓参りの時間帯は特に決まりはないものの、一般的には日のある明るい時間に行くものとされています。特に照明の設備がない墓地・霊園の場合は、日のある時間帯にお墓参りをすることをおすすめします。
基本的には日中の明るい時間帯にお墓参りするのがおすすめ
お墓参りの時間帯は特に決まりはないものの、一般的には日のある明るい時間に行くものとされています。特に照明の設備がない墓地・霊園の場合は、日のある時間帯にお墓参りをすることをおすすめします。
お盆のお迎えやお見送りのお墓参りは通常夕方に行われる
お墓参りは明るい時間帯がおすすめですが、例外もあります。それがお盆のお迎え・お見送りのお墓参りです。先祖はお墓参りの提灯の明かりをよりどころとして家に帰るため、お迎えのお墓参りは夕方頃に行くことが多いようです。お盆飾りとして鬼灯(ほおずき)が用いられるのも、提灯のような形をしていることからだといわれています。ただし地域によっては、午前中にお墓参りをすませて、夕方に自宅で迎え火を焚くというところもあります。
またお盆のお見送りは、少しでも長く先祖に家にいてほしいという思いから、遅い方がよいとされています。お見送りのお墓参りも夕方から夜に行います。
お墓参りを避けた方がよい時間帯

お墓参りにはいつ行ってもよいというのが基本ですが、そうはいっても避けた方がよい時間帯もあります。
霊園や納骨堂の開園していない時間帯は避ける
霊園や納骨堂は24時間開園しているところもありますが、開園・閉園時間が定められているところもあります。霊園や納骨堂が閉園していると中に入ることはできないので、時間を調べてから出かけるようにしましょう。
住宅地近くの場合、早朝や夜間は避ける
霊園や墓地が住宅地近くにある場合、早朝や夜間は避けるようにしましょう。お墓参りは午前中がよいといっても、あまりに早い時間だと周囲に住んでいる方に迷惑となります。同様に夜間も避けた方が無難です。周囲に住んでいる方への配慮が欠けるようでは、故人や先祖の供養になりません。
照明の少ない霊園は、夜間は避ける
昔ながらの墓地や霊園などでは照明が不足している場合、足元が見えづらく転倒の危険があります。お墓の掃除をする場合も暗いと見えづらく、丁寧に行うことができません。照明が設置されて夜にお墓参りができるようになっている墓地・霊園では、夜にお墓参りしても問題ありませんが、大きな声を出さない等、節度のある行動を心がけるようにしましょう。
夏の場合、昼は暑いので避ける
夏の日中は気温が高く、8月のお盆の時期となると35度を超える猛暑日になることも珍しくありません。霊園や墓地は日差しを遮るものが少なく、炎天下にさらされることになります。熱中症の危険があるので、昼間のお墓参りは避けた方が無難です。まだ涼しい早朝のうち、もしくは夕方少し涼しくなってからお墓参りに出かけるようにしましょう。
お墓参りに行く時期やタイミング

お墓参りは、亡くなった方やご先祖様の冥福を祈り、供養をする行為です。仏事には多くの決まりごとがありますが、お墓参りの時期は基本的に自由です。自分が行きたいと思う時に訪れても構いません。とはいえ、ぜひお墓参りに行っておきたい時期というものもあります。
祥月命日・月命日
祥月命日とは、故人が亡くなった同月同日のことで年に1度あるものです。月命日は故人が亡くなった同日を指すもので毎月訪れます。
祥月命日には一周忌・三回忌・七回忌・十三回忌・十七回忌・二十三回忌・二十七回忌・三十三回忌・五十回忌と法要を行う年があり、この機会にお墓参りに行く方は多いでしょう。しかし法要がない年も忘れずにお墓参りに行くようにしましょう。
また月命日は毎月のため、お墓参りに行かずにすませることもありますが、できればお墓の前で手を合わせたいものです。
お彼岸(春/秋)
春と秋にあるお彼岸は、「春分の日」「秋分の日」をそれぞれ中日とした前後3日、合わせて7日間のことを指します。最初の日は「彼岸の入り」、最後の日を「彼岸明け」と呼びます。
「彼岸」とは「浄土」を指し、西の方角にあるとされています。一方私たちが生きている現世は「此岸(しがん)」と呼ばれ、東の方角にあるとされています。春分の日・秋分の日は太陽が真東から昇って真西に沈むので、「彼岸」と「此岸」が最も通じやすくなるという考えから、この時期にお墓参りを行う習慣が生まれました。
お盆

お盆は故人や先祖が家に帰ってくる日といわれており、お墓参りの時期になっています。
お盆の期間は8月13~16日ですが、地域によっては7月13~16日に行うところもあります。一般的にはお盆のお墓参りは、初日となる13日に故人や先祖を迎えるために行われますが、絶対に13日でなければならないというものではありません。ただし13日の「盆の入り」は先祖が帰ってくる日となるので、その前日までにお墓の掃除はすませておきたいものです。またお盆の最終日にも、お見送りのお墓参りをする習慣もあります。
年末年始
家族や親族が集まる機会となる年末年始も、お墓参りをする時期とされています。
ただし年末の29日は「二重苦」といって縁起が悪いといわれます。また31日もお正月の一夜飾りから縁起の悪い日とされ、お墓参りを避ける方もいるようです。年始のお墓参りも地域によってはハレの日にお墓参りするべきでないとされているところもあります。とはいえ、どちらも仏教的な決まりではないので、お墓参りに行ってもかまいません。気になる方は避けるようにしましょう。
故人に報告したいことがあった時
進学や就職、結婚、妊娠・出産など、おめでたいことがあった時もお墓参りのタイミングです。お墓にお参りして故人に直接報告すれば、先祖や故人もきっと喜んでくれるでしょう。
また反対に、人生の岐路に立って迷った時も、お墓参りに行くことをおすすめします。自分の考えや気持ちが整理できて、よりよい選択ができるでしょう。
お墓参りの服装や持ち物

お墓参りに行く際の服装について、またお墓参りする際に必要なもの、用意すべきものについて説明します。
服装は動きやすい格好で!カジュアルでもOK
祥月命日で法要のある際にお墓参りする場合は、喪服などのブラックフォーマルが一般的です。しかしそれ以外でお墓参りする場合は、カジュアルな服装でかまいません。お墓参りに行くとお墓の掃除がつきものなので、動きやすい格好ならお墓掃除もはかどります。ただし過度に派手な服やアクセサリー、香りが強い香水などは避けた方がいいでしょう。また墓地や霊園は砂利が敷かれていることが多いため、かかとが高いヒールも避けた方が無難です。
【持ち物1】お参りする際に使う物
●線香
●ろうそく
●ライター・マッチ
●数珠(念珠)
線香は亡くなった人の食べ物になるといわれています。心身を清める効果がある、あの世とこの世を繋ぐ架け橋になるなどともいわれています。
またろうそくは火を灯すことで周囲を照らし、お墓参りをしていることを知らせる役割があるとされています。
ライターやマッチは、ろうそくや線香に火をつけるためのもの。野外などでも火が消えにくい風よけ付きの「墓参用ライター」などもあります。
数珠(念珠)はお墓参りの際に手を合わせるために使う道具ですので、持参することをおすすめします。
【持ち物2】お花・お菓子などのお供え物

●お花
●お供え物
お墓にお供えする花は「仏花」とも呼ばれ、花屋やスーパーでセットになったものが購入できます。故人の好きだった花を持って行くのもよいでしょう。
お供え物はお菓子や果物などが一般的です。これも故人の好物を選ぶとよいでしょう。お供え物は墓石の上に直接置くのではなく、半紙に乗せて供えるので半紙の用意もしておきましょう。
【持ち物3】掃除道具
●ほうき、ちり取り
●歯ブラシ、古タオル
●軍手
●ゴミ袋
ほうきとちり取りでお墓の周辺を掃いて清めます。歯ブラシは墓石の細かいゴミを取り除くのに便利。古タオルは墓石を拭くのに用います。磨き上げたい場合は、バイク磨きなどで使われる柔らかめのブラシがおすすめです。雑草を取り除く際に軍手があれば、手が汚れずにすみます。ゴミ袋も持参してゴミは持ち帰るようにしましょう。
掃除で水を使うのに用いる手桶・ひしゃくは、たいていの場合は墓地や霊園で用意してあり、借りることができます。用意がない場合はペットボトルなどで水を持参するようにします。
お墓参りの流れ

知っているようで意外と知らないのが、お墓参りの手順。何度もお墓参りに行っている方も、いま一度確かめてみてはいかがでしょう。
またお寺で本堂がある場合は、お墓参りの前に本堂に参拝するのもお忘れなく。
(1)お墓の掃除をする
掃除の前にまずお墓に合掌します。それから掃除を開始し、敷地内のゴミや雑草を取り除きます。次に墓石を洗います。墓石にはなるべく登らないようにしましょう。ただし手が届かない場合は気をつけて行うようにします。その後、墓石の周りにある小物なども洗います。掃除が終了したら、手桶にきれいな水を汲み、墓石に柄杓で打ち水をして清めます。
(2)お花やお供え物を供える
掃除が済んだらお花を供えます。水鉢があればお水も供えるようにします。その後に菓子や果物など持参したお供え物を半紙に乗せて供えます。
故人がお酒好きだったと墓石にお酒をかける人もいますが、墓石の変色などを引き起こすので避けた方がいいでしょう。お酒を供えたい場合は、器に注いで供えるようにします。
(3)お線香をあげ、合掌してお参りする

ろうそくに火を点し、線香に火を付けます。線香の火は手で振って炎を消し、口で吹き消さないようにしましょう。その後、合掌してお参りします。数人でお墓参りに訪れている場合は、故人と近しい間柄の人から順番にお参りしていきます。
(4)片付けをする
お参りがすんだら、片付けをします。ろうそくは消して持ち帰り、線香は燃やしきるようにします。お供え物のお菓子や果物は、その場で食べてもかまいません。食べない場合は腐敗や害獣・害虫の被害を防ぐため、そのままにしないで持ち帰るようにします。
お花は霊園・墓地などによりますが、供えたままでよいところと持ち帰りを推奨されているところがあります。それぞれのルールに従うようにしましょう。また霊園等で借りた水桶やひしゃくは所定の場所に戻すようにします。
いつでも訪れやすい「證大寺」のお墓参り

證大寺 船橋昭和浄苑の入り口
江戸川区にある證大寺には、お寺の境内に墓地があります。そのほか埼玉には「森林公園 昭和浄苑」、千葉には「船橋 昭和浄苑」があり、24時間開苑しています。いつでもお墓参りに行きやすい配慮があり、お花や線香などお墓参りに必要な物は現地で買うことができ、思いついたときに手ぶらでお参りすることもできます。
お墓は亡くなった方と対話する場所
證大寺が「お墓参りに行きやすい」お墓を目指しているのには理由があります。それは「お墓は亡くなった方と対話する場所」だと考えているからです。お彼岸やお盆、命日だけでなく、ふと「亡くなった人と話がしたい」と思う瞬間はありませんか。そんな時にいつでもお墓参りができるのが證大寺のお墓です。故人とじっくり話をしたいとお弁当を持参し、お墓の前で広げて故人に語り掛けながら昼食を取られる方もいらっしゃいます。證大寺はそんなお墓参りの仕方も歓迎しています。
仕事帰りなど、夜のお墓参りがしやすい

お墓参りに行って故人と話がしたいと思っていても昼間は仕事の都合で行けない方も多いでしょう。證大寺の墓地が24時間いつでも開いているのは、そんな方にもお墓参りに来ていただけるようにと考えたからです。夜のお参りがしやすいから、仕事帰りなどでも行くことができます。
やさしく迎え入れ、包み込むようなライティング
とはいえ「夜のお墓は暗くて怖い」というイメージを持つ方もいるでしょう。しかし證大寺のお墓は夜になると照明が点灯し、足元が明るくなりますので、安心してお参りできます。特に船橋昭和浄苑では、やさしく包み込むような光で迎え入れてくれて、従来の夜のお墓のイメージとは一線を画します。
「私たちは光をデザインしてくださる先生にお願いして、『月燈慈(がっとうじ)』というテーマに基づき、光の縁を描く形でお参りする方々の特別な時間を大切にし、夜の不安を取り除き、安心して過ごせる光を計画しました。」と住職は語ります。最近では夜にしか来られない方だけでなく、あえて誰もいない夜に、一人で故人に会いにお墓参りしたいと考える方も増えているそうです。
またお墓のライティングは、夜のお参り以外にも効用があったといいます。幼い子どもを亡くしたお母様が「暗いお墓に小さな子を入れるのはかわいそう、きっと怖がるに違いない」と納骨をためらっていたものの、船橋昭和浄苑の夜の様子を見て「ここならやさしい雰囲気があって、少しも怖くない」と納骨に踏み切ることができたそうです。
お悩みや相談・対話は夜がおすすめ
住職は「お墓参りだけでなく、お悩みや相談があって僧侶とお話ししたい場合は、ぜひ夜に訪れてください。」といいます。昼間は法要やお寺の行事などで多くの時間がとれないこともあるけれど、夜ならじっくり時間をとって向き合えるからだといいます。
これまではあまり行く機会がなかった夜のお寺やお墓も、足を踏み入れてみると昼間にはなかった心持ちが得られることがあるかもしれません。
まとめ

お墓参りは時期や時間にとらわれず、お参りしたいと思えばいついってもいいものです。お彼岸やお盆、法要の際などばかりになりがちですが、故人と話をしたくなったらお墓参りに行ってみては。大切な人を偲びながら時間を過ごせば、心がリフレッシュでき、日々の生活に新たな視点をもたらすことができるでしょう。










