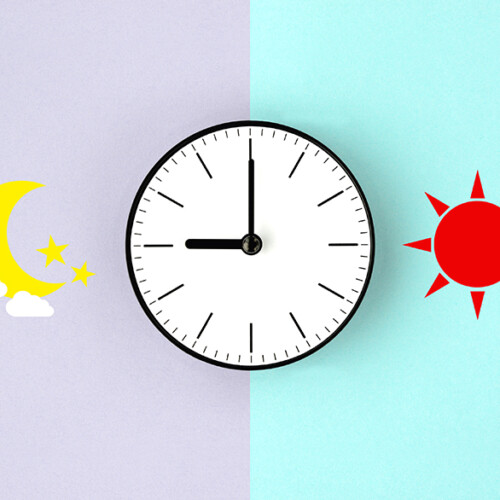浄土真宗のお盆は何をすればいいの?お盆の時期と過ごし方

年に一度のお盆は日本の伝統的な仏事です。お盆では、どの宗派でも家に還ってくる先祖を迎えて供養するものと思っている方も多いでしょう。しかし実は宗派によって異なり、特に浄土真宗は違いが大きいといえるでしょう。そこで浄土真宗ならではのお盆の考え方や過ごし方について説明します。
目次
●浄土真宗のお盆について
●浄土真宗のお盆の時期とは
●浄土真宗のお盆の過ごし方
●【注意点】浄土真宗のお盆のお供え物
●浄土真宗のお寺「證大寺」のお盆について
●まとめ
浄土真宗のお盆について

浄土真宗のお盆は、他の宗派のお盆と異なることが多々あります。自分の家が浄土真宗ならもちろんですが、そうでなくても浄土真宗は日本最大の仏教宗派であるため、他家の仏事としてなどで関わる機会もあるでしょう。その違いを知っておけば、いざというときに役立ちます。
浄土真宗のお盆の考え方
一般的にお盆は、先祖の霊が帰ってくる日とされています。迎え火で故人の霊を迎え、送り火で霊を送るという風習があるのも、この考えがもとになっています。
しかし浄土真宗の教えでは、人は亡くなるとすぐに成仏するとされています。仏様になっているので、お盆の期間に先祖の霊が家に戻ってくることはありません。
■追善供養を行わない
他の宗派ではお盆に追善供養が行われることが多いです。追善供養とは、遺された人が供養して善行を積むことで、故人や先祖の善行に代わるというものです。しかし浄土真宗の教えでは、故人や先祖は仏様になっているので、追善供養を行う必要がないとされています。仏様になっているので、送り火や迎え火を焚いて霊を迎えたり送ったりせず、新盆に迷わず家に帰れるように飾る白提灯も不要とされています。また仏壇にも精霊棚を飾らないなど他宗派とは異なっています。
■浄土真宗のお盆は「歓喜会」
とはいえ浄土真宗にもお盆はあり、全く何もしないというわけではありません。浄土真宗では、お盆の時期を「歓喜会(かんぎえ)」と呼ぶ地方もあります。歓喜会は故人や先祖を供養するものではなく、先祖に感謝する日と位置づけられています。故人や先祖が縁となって念仏の教えに出会えたことに喜ぶというもので、阿弥陀如来の教えに触れる機会として歓喜会の法要も行われます。盆踊りも由来はお盆の経典にあり、餓鬼道にいた母が仏の教えを聞き、歓喜踊躍しながら浄土に生まれるということが由来となっています。
浄土真宗のお盆の時期とは

浄土真宗のお盆の時期は、他の宗派と変わらず旧暦に行います。しかし東京など新暦で行う場合は7月13日〜16日、それ以外の旧暦で行われる場合は8月13日〜16日となります。
浄土真宗のお盆の過ごし方

浄土真宗では追善供養は行わないものの歓喜会の法要を行ったり、他の宗派と同様にお盆にはお墓参りに行ったりします。ただし故人や先祖の霊を迎えに行くためではなく、仏様との縁をつなぐためにお墓参りを行うとされています。
また阿弥陀様の教えを知る機会として、お盆にはお寺の法要に参加し、自宅に僧侶を招くことも多いです。お盆に僧侶を自宅に招く際には、仏壇の飾り付けをするのが習わしとなっています。
お盆用の仏壇の飾り付け
お盆用の仏壇の飾りつけは盆の入りの前日までに行い、また片付けは16日の朝に行うようにします。お盆用の飾り付けは普段とは異なりますので、前日となる12日までに仏壇の埃を払って仏具を磨くなどして準備をしておくようにしましょう。
仏壇の飾り付けの具体的な手順は以下のようになります。
■1.夏用の打敷(うちしき)を敷く
仏壇の卓の本体と上板の間に打敷と呼ばれる布を敷きます。打敷は三角形の布で、刺繍が施されているものが多くあります。お盆には、白・金・青のいずれかの色のもので、夏用のものを選ぶようにしましょう。
■2.供笥(くげ)に餅をのせて供える
供笥と呼ばれる台の上に餅をのせて仏壇にお供えします。この時、供笥の柱に穴があいている面を正面にして置くようにします。また供笥は浄土真宗大谷派では八角形のもの、本願寺派では六角形のものを用いるのが通例となっています。
■3.赤ろうそくを用意し、青木や供花を飾る

先端が太くなっている錨型と呼ばれる赤の和ろうそくを用意し、燭台にさします。花立てには青木や供花を飾るようにしましょう。季節の仏花のほか、槙を中心に蕾のはすや巻き葉などが選ばれる場合が多いです。
■4.仏飯と線香をお供えする
浄土真宗大谷派では、仏飯は盛糟(もっそう)という型抜きのような仏具で円柱形に盛ります。盛糟がない場合は、しゃもじで円柱形に整えて盛ってもかまいません。西本願寺派では仏飯器に丸く蓮のつぼみ型に盛るようにします。いずれの場合も朝にお供えして、昼には下げるようにしましょう。
浄土真宗では線香は立てず、寝かせて焚くようにします。香炉によって寝かせられない場合は、香炉に入る大きさに折って寝かせるようにしましょう。
【注意点】浄土真宗のお盆のお供え物

浄土真宗でもお盆にお供え物をしますが、精霊棚を飾って供えることは行いません。従って精霊馬や精霊牛など野菜で作った動物を供えることはありません。お供え物は供笥にのせる餅が主になります。白い丸餅を用意して供笥にのせてお供えしましょう。丸餅以外では、お菓子や果物なども一緒に供えることもあります。
また盆提灯や供花などについても、気を付けたい点があるので注意するようにしましょう。
浄土土真宗では盆提灯はなくてもよい
他の宗派では盆提灯を飾ることが多く見られます。盆提灯は蓮の花などが描かれたもので、仏壇の側などに飾られます。
浄土真宗では盆提灯は基本的になくてよいとされています。とはいえ禁止されているわけではなく、盆提灯があれば飾ってもかまわないとされています。また地域によっては飾る習慣があるところもあります。
ただし浄土真宗での盆提灯は、他の宗派とは意味合いが異なります。他の宗派では故人や先祖の霊が迷わず家に帰って来られるように飾るとされていますが、浄土真宗では僧侶を自宅に招く際の飾り付けのひとつとして捉えられています。
お供えするときのお花はトゲや毒のある花は避ける

お盆にお供えするお花についても、いくつかの注意点があります。
仏花として必ず供えなければならないと決められた花はありませんが、供えてはいけないとされている花はあります。バラやアザミなどのトゲのある花、彼岸花や夾竹桃など毒のある花は、仏花に相応しくないとされているので避けるようにしましょう。このほか花持ちが悪い花も選ばないようにしましょう。しおれたり枯れたりした花は見苦しく、お供えに適しません。また花びらが落ちやすい花も、仏壇を汚してしまうことになります。後片付けの手間もかかるので、長持ちする花を選ぶようにしましょう。花屋やスーパーなどで仏花として売られているものは、仏壇に供えるのに適切な花が選ばれているのでまず間違いありません。
これらはお盆に限らず、仏壇やお墓に花を供える場合に共通している注意点なので、知っておくようにしましょう。またこの時期が見頃を迎えるほおずきを供花をお供えすることも多いようです。ほおずきは漢字で鬼灯と記すように、死者がご自宅に帰ってくる際の灯火になるという俗説もありますが、浄土真宗ではそのような意味では用いません。
浄土真宗のお寺「證大寺」のお盆について

東京都江戸川区にある證大寺は、浄土真宗のお寺です。お寺には墓地が併設されているため、お盆の時期はお墓参りに来る方で賑わいます。またお盆法要も行われ、これを楽しみに訪れる方も多くいます。
他宗派では、餓鬼道に落ちた故人を救う法要
證大寺の住職は「お盆は正式には盂蘭盆会といい、『仏説盂蘭盆経』という経典がもとになっています」といいます。『仏説盂蘭盆経』には、お釈迦様の弟子である目連が、亡き母が餓鬼道に堕ちて苦しんでいることを知り、母を救うために供養したところ、餓鬼道の苦しみから免れることができたというエピソードがあるそうです。この『仏説盂蘭盆経』が日本に伝わり広まっていく過程で、今日のような形に発展したと考えられます。そもそも仏教には霊という概念がなく、『先祖の霊が帰ってくる』という教えもないそうです。日本でお盆が広まって行く過程で、先祖崇拝の風習と結びついた結果だと考えられるということです。
浄土真宗では、仏様に感謝

「浄土真宗では人は亡くなると極楽浄土に行くという教えです。」と住職はいいます。「とはいえお盆の行事は、宗派を超えて地域色が濃いという特徴があります。たとえば青森のねぶたや沖縄のエイサーなども、お盆に先祖を供養することから始まっているようです。浄土真宗は、これらを否定するわけではありません。地域の風習を尊重しながらも、お盆は『仏様に感謝する日』と捉えています。」また住職は「浄土真宗のお盆について聞きたいことがあれば、お気軽にお尋ねください」とのこと。證大寺では浄土真宗での通夜や葬儀、法要などが行えるほか、仏教講座なども開催しています。お盆にかぎらず相談があれば、話を聞いてみるとよいでしょう。
證大寺について詳しくはこちら
まとめ

浄土真宗のお盆は、精霊棚を飾らず、迎え火や送り火も焚かないなど違いがあります。これはお盆の捉え方自体が他の宗派とは異なるためです。とはいえお盆の期間ならではの仏壇飾りなどもあるので、お盆を迎える前には手順なども確認しておくようにしましょう。