回忌法要はいつ行えばいい?|年忌法要との違いと実施時期について解説

故人がなくなった後に行われる法要に「回忌法要」「年忌法要」と呼ばれるものがあります。この2つは違いがあるのでしょうか。また法要をいつ行えばいいかわかるよう、年回忌の数え方等についても解説します。さらに法要を行う際の準備やマナーについても紹介します。
目次
●回忌法要と年忌法要はどう違う?
●何回忌をいつ行えばいい?年忌法要の実施時期
●年忌法要の準備と進め方
●年忌法要のマナーと注意点
●年忌法要は無理なく行える範囲で!現代に合った供養の形
●證大寺の法事|ご相談ください
●まとめ
回忌法要と年忌法要はどう違う?

故人の法要を行う際、「年忌法要」「回忌法要」といった言葉を聞いたことがある方は多いでしょう。七回忌、十三回忌などの法要をさす言葉で、どちらも同じ意味として使われています。
回忌法要とは
回忌とは「年回忌」の略です。年回忌は、故人が亡くなった後に毎年やってくる祥月命日(故人が亡くなった月日)の日にちをさす言葉です。従って〇回忌とは〇回目の命日という意味となります。回忌に行う法要のため、回忌法要という言葉も使われていますが、年忌法要と呼ぶのが正しい呼び方だとされています。
年忌法要とは
「年忌」という言葉もまた、祥月命日を表すものですが、「祥月命日に営まれる仏事」をさす言葉でもあります。
年忌法要は、故人に対して定められた年に営まれる法要のことで、一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌、五十回忌と続いていきます。
何回忌をいつ行えばいい?年忌法要の実施時期
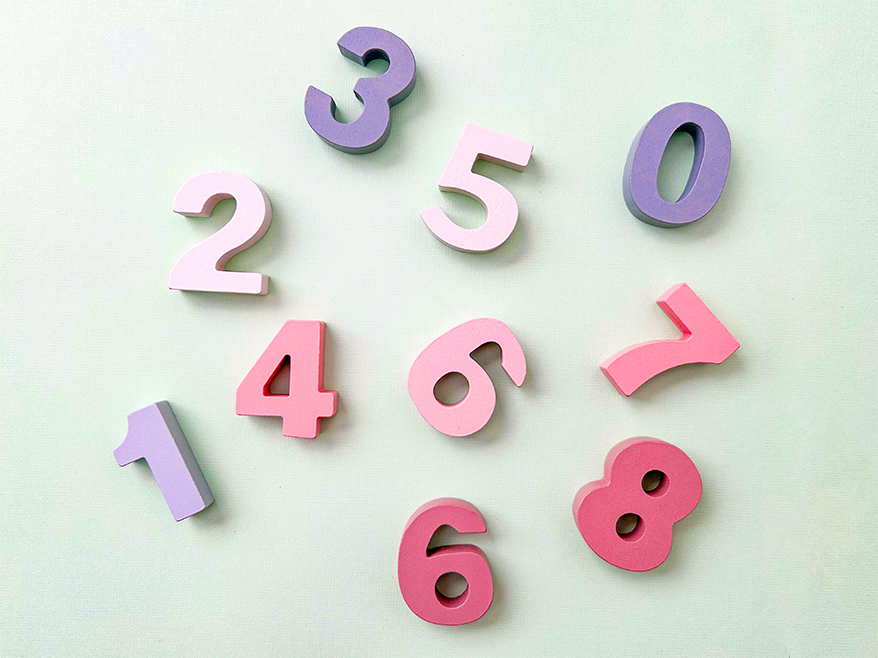
年忌法要は、亡くなった1年後の一周忌の後は、基本的には3と7のつく回忌の祥月命日に行われます。年忌法要は命日当日に行うのが正式な作法となりますが、命日が平日で都合がつかないなどの場合は、日にちをずらして開催されることも多くあります。ただしその際は命日の後ではなく、前倒しするのが慣例となっています。
主な年忌法要の一覧
年回忌法要は数年に1度行うもので、基本的に下記の一覧表のタイミングで行われます。
●一周忌/亡くなってから2年目後
●三回忌/亡くなってから2年後
●七回忌/亡くなってから6年後
●十三回忌/亡くなってから12年後
●十七回忌/亡くなってから16年後
●二十三回忌/亡くなってから22年後
●二十七回忌/亡くなってから26年後
●三十三回忌/亡くなってから32年後
●五十回忌/亡くなってから49年後
宗派や菩提寺によっては、23回忌と27回忌の代わりに25回忌が営まれるといったケースもあります。また三十三回忌法要か五十回忌法要で「弔い上げ」をして、最後の年忌法要とすることが多いです。しかし、どの法要を弔い上げにするかどうかは、明確に決まっているものではありません。
亡くなって3年目は何回忌?数え方と計算のポイント
回忌の数え方はやや複雑なため、混乱することがあるかもしれません。計算方法で迷った場合は、「回忌-1」で考えるとわかりやすいでしょう。例えば三回忌なら「3-1=亡くなってから2年後」、三十三回忌であれば「33-1=亡くなってから32年後」となります。ちなみに一回忌とは「1回目の命日」の意味で、亡くなった当日にあたります。また亡くなった1年後だけは、二回忌ではなく一周忌と呼ばれます。これは故人が亡くなって季節が一周したという意味だといわれています。
年忌法要の準備と進め方

年忌法要の準備は早めに行うようにしましょう。特に祥月命日がお盆やお彼岸の時期と重なっている場合は、法要場所や僧侶の予定も混み合います。事前準備は2ヵ月前位から始め、1ヵ月前には全て終えることを目標とするのが理想といえます。
年忌法要の日程を決める
まず法要をいつ行うのかを早めに決めます。命日が平日の場合は、参列者の都合を考えて法要日以前で最も近い土日に設定するのが一般的です。日にちが決まればお寺に相談して僧侶を依頼し、お寺で開催する場合はその相談も行いましょう。セレモニーホールなど会場で開催する場合は、会場を予約するようにします。
年忌法要の開催場所を決める
年忌法要の開催場所は、お寺、自宅、セレモニーホールなどが候補となります。大きな規模で行う場合はお寺や会場、小規模なら自宅ということが多いです。ただし地域やお寺との関係性などによっては、菩提寺で行うのが慣例という場合もあります。
参列者の人数に応じた会食や返礼品の準備をする
参列者をどこまで呼ぶかなどを決め、案内状を送ります。大方の人数が把握できれば、会食や返礼品の準備も進めましょう。ちなみに法事の食事費用は、1人3,000〜7,000円程度の予算が一般的です。返礼品は最近では法要当日に直接手渡すことが多く、相場は2,000〜5,000円程度が目安となっています。返礼品はお菓子などの食品や日用品などいわゆる「消え物」が好まれます。
年忌法要のマナーと注意点

年忌法要での基本となるマナーや注意したいポイントをまとめましたので、参考にしてください。
案内状の準備と送付のタイミング
年忌法要の案内状は、参列者の人数を把握するためにも予定日の1ヶ月前には届くように送ります。案内状には、誰の何回忌か、日時・場所を記載し、法要後の会食の有無も伝えるようにしましょう。返信用のはがきを同封するのが正式な案内状とされていますが、往復はがきで略式としても問題ありません。また参列者が身内のみの場合などは、電話やメールで出欠を確認してもよいでしょう。
何回忌かによって服装マナーが異なる!参列者・施主それぞれの服装マナー
年忌法要は何回忌かによって服装マナーが変わります。一周忌は施主、参列者とも準喪服で参列するのがマナーとされています。三回忌は施主や遺族は準喪服で、親族以外の参列者は黒スーツなどの略喪服でもかまわないでしょう。七回忌以降は、施主や遺族も略喪服が一般的です。年忌法要は、回を重ねるごとに規模が縮小され簡略化される傾向があります。また施主から「平服で」といわれた場合にはカジュアルではなくダークスーツなどを着用するようにしましょう。
香典は持参するのがマナー
年忌法要に参列する際は、香典を持参するのがマナーです。故人と血縁関係にある親族の場合は1~3万円程度、血縁関係がない場合は5,000~1万円程度が相場となっています。ただし会食がある場合は、5,000~1万円程度を上乗せして包むことが一般的です。回忌を重ねるに連れ規模が小さくなり、それに伴って香典の額も少なる傾向があります。
消えものが一般的?返礼品のマナー
返礼品を選ぶのに特に決まりはありませんが、食品や日用品などの「消えもの」が定番となっています。ただし消費期限・賞味期限が短いものは避けて選ぶのがマナーです。また持ち帰るのに負担となる大きな物、重い物は避けます。故人の地元の名産品など、故人にまつわる思い出のものなら故人を偲ぶきっかけになるでしょう。最近では法事専用のカタログギフトもあるので、それを利用するのもよいかもしれません。
年忌法要は無理なく行える範囲で!現代に合った供養の形

かつては一周忌や三回忌といった年忌法要は、多くの参列者を招待して行うことも珍しくありませんでした。しかし現代では葬儀も家族葬など小規模で行うことも多く、それに伴って一周忌や三回忌も家族など身内だけで、自宅で小さく行うことも増えてきました。年忌法要を省略して行わないのは適切でありません。しかし無理のない範囲で行うというのは、現代に合った供養の形といえるでしょう。
「オンライン法要」を選ぶ人も
まだ少数派ではありますが、現代ではオンライン法要を選ぶ方もいます。オンライン法要とはZOOMやSkypeなどを利用して法事・法要を行うというものです。コロナを機に一部のお寺で始まり、少しずつ広まっています。法要の流れは通常と同じで、遠隔地にいても参加できるメリットがあります。まだまだ馴染みがないものですが、形や方法は変わっても、心を込めた供養こそが大切なのではないでしょうか。
證大寺の法事|ご相談ください

写真:船橋昭和浄苑内「手紙寺」の様子
東京都江戸川区の證大寺は、浄土真宗大谷派のお寺です。證大寺は千葉県船橋市で「船橋昭和浄苑」、埼玉県東松山市では「森林公園昭和浄苑」という霊園を直接運営しています。どちらの昭和浄苑にも本堂があり僧侶が常勤しています。
證大寺や昭和浄苑では、本堂で法事を行うことができます。お墓の側なので、法要の後にお墓参りにもすぐに行けます。また会食場となる「お斎場」もあるから、移動せずに会食を行うことができます。さらに供花、供物、返礼品なども、お寺に依頼すれば手配を行ってもらえます。法事に関する悩みなども、お寺なのですぐ相談できて安心です。
證大寺の法事について、詳しくは下記をご参照ください。
https://shoudaiji.or.jp/advice/houji/houji_flow/
證大寺:https://shoudaiji.or.jp/
證大寺 江戸川:https://edogawa2.eitaikuyou.life/
森林公園 昭和浄苑:https://higashimatsuyama2.eitaikuyou.life/
船橋 昭和浄苑:https://funabashi2.eitaikuyou.life/
まとめ

年忌法要は、祥月命日に行われる大切な法要です。回忌や年忌など似た言葉が多々あり、数え方もやや複雑なため、混乱することもあるかもしれません。この記事を参考に正しく理解し、どの法要をいつ行えばよいのか把握するようにしましょう。また年忌法要にはさまざまな慣習やルールがつきものです。施主となった場合も、参列する場合も、マナーを守るように心がけましょう。










