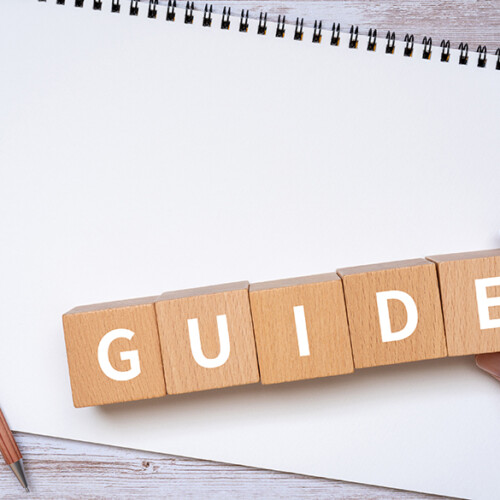永代供養のお墓参りはどうすればいい?|基本的な流れや種類別のお墓参りの方法・必要なものまで解説

近年、永代供養墓を選ぶ人が増えています。その理由は、お墓の承継者がいない、子世代に負担をかけたくないなどさまざまです。では永代供養のお墓参りは、通常のお墓参りと違いがあるのでしょうか。そこで永代供養のお墓参りの種類別の特長、基本的な流れに加えて注意点等も紹介します。
目次
●永代供養墓とは
●永代供養墓のメリット
●永代供養のお墓参りの基本的な流れとおすすめの時期
●永代供養墓の種類別お墓参りの特徴
●お墓参り当日の流れ
●永代供養のお墓参りに必要なもの
●永代供養のお墓参りで注意するポイント
●永代に渡って供養してくれる「證大寺」の永代供養
●まとめ
永代供養墓とは

昔からある先祖代々、家族の間で受け継がれていくお墓は一般墓とも呼ばれます。亡くなった後はそのお墓に家族全員が入るというのが一般的で、お墓の管理や供養も後継者が担うことになります。
これに対して永代供養墓は、家族や子孫に代わって、お寺や霊園が管理と供養をしてくれるお墓を指します。管理も供養も、全て任せられるというのが大きな特徴といえるでしょう。
永代供養墓については、以下の記事でも詳しく説明しています。
https://shoudaiji.or.jp/baton/post57/
永代供養墓のメリット
永代供養墓の大きなメリットは、お墓の後継者が不要な点です。一般墓では、家族が代々管理や供養を引き継いでいく必要があります。一方、永代供養墓ではお寺や霊園が管理も供養も行ってくれるため、継承者問題に悩む心配がなく、将来的に無縁仏になる不安もありません。
また契約時に費用を支払えば、以降の管理費や維持費が不要な場合も多く、経済的な負担を抑えられるというメリットもあります。このような理由から、遠方に住んでいる家族や、子どもに負担をかけたくないと考える方からも選ばれています。
一般墓との違いを解説
一般墓は前述したように、子孫が代々継いでいくことを前提とされています。管理や供養だけでなく、区画やお墓のメンテナンスも遺族で行うことになります。
永代供養墓は、基本的には継承せず一代限りのお墓であるのが一般的です。遺族が亡くなっても供養は続き、お寺や霊園が管理してくれるのでメンテナンスは不要です。またさまざまな種類があるのも、永代供養墓の特徴といえるでしょう。最近注目を集めている樹木葬や納骨堂も、大抵の場合が永代供養付きで、新しいスタイルの永代供養墓とされています。
永代供養墓を選ぶ際の注意点
永代供養墓は後継者不要で安心な選択肢といえますが、選ぶ際にはいくつかの注意すべきポイントがあります。まずは供養の方法や期間が契約によって異なるという点です。永代供養であっても個別で埋葬されるのは一定期間のみで「最終的に合祀される」というタイプも多いことを理解しておくことが大切です。
また費用に含まれるサービス内容(法要の有無、年何回の供養か、管理費の追加有無など)もしっかり確認しましょう。さらにお墓の立地やアクセスも重要な判断材料となります。家族がお参りに行きやすい場所かどうかを事前に見ておくと安心です。契約前に、供養方法、費用、個別埋葬期間、立地条件等を総合的に比較検討し、自分たちに合った永代供養墓を選ぶようにしましょう。
永代供養のお墓参りの基本的な流れとおすすめの時期

永大供養のお墓参りの流れは一般墓へのお墓参りと同じ
永代供養のお墓へのお参りの流れは、一般墓へのお参りとあまり変わりはありません。花や水を供えて、ろうそくを焚いて線香に火を点け、合掌してお参りし、後片付けをするというのが基本となります。ただし火気やお供物に制限がある場合は、それを守るようにしましょう。
おすすめ!永大供養のお墓参りの時期
お墓参りの時期については、祥月命日や春秋のお彼岸、お盆、年忌法要のタイミングでお参りするのがおすすめです。それ以外でも故人に報告がある、故人と対話したいという時にもお墓参りに行くようにしましょう。
永代供養のお墓でも法事はできる
永代供養では、お寺や霊園が定期的に法要を行ってくれます。ただしお彼岸やお盆だけなのか、祥月命日や年忌法要もおこなってくれるのかは契約によって変わってきます。
永代供養墓の種類別お墓参りの特徴

お寺や霊園が管理してくれる永代供養墓でも、お墓参りは欠かせないものです。しかし永代供養墓の場合は、その種類によってお墓参りのルールが異なることがあります。お墓の種類別に、その特徴を見ていきましょう。
納骨堂のお墓参り
納骨堂とは遺骨を安置するための屋内施設で、多くが永代供養付きであることから、現代では永代供養墓の一つと位置づけられています。納骨堂にはロッカー式や仏壇式、自動搬送式などの種類があります。多くの納骨堂では開館時間が決まっているため、夜間のお参りなどはできないのが一般的です。また自動搬送式の場合は参拝室でお参りすることになり、安置場所まで行けないこともあります。さらに施設によって異なるものの、お供えするスペースが限られていて、お供物は持ち帰るルールがあることも珍しくありません。
納骨堂については、以下の記事で詳しく説明していますのでご参照ください。
納骨堂とは?お墓との違いやメリット、デメリットを解説
樹木葬のお墓参り
樹木葬は樹木や草花を墓標とするお墓のことで、主に「里山型」と「庭園型」に大別されます。里山型は山の中にあることがほとんどで、山火事防止のため線香やろうそくが禁止されていることが多いです。また花瓶の設置がなく、供花は地面に直接置くケースもあります。庭園型は霊園の中などにあり、一般墓と同様にお墓参りできるケースが多いようです。ただしこちらも、墓地や霊園によって独自のルールが定められている場合があります。
樹木葬については、以下の記事で詳しく説明していますのでご参照ください。
樹木葬と永代供養の違いとは?基本知識と樹木葬を選ぶ際の注意点を解説
集合式(合祀墓)のお墓参り
墓石がある永代供養墓としては、集合式(合祀墓)のものと個別式の物があります。
集合式(合祀墓)の永代供養墓は、最初から他の遺骨と一緒に埋葬され、ひとつの墓石を共同で墓標とするケースがほとんどです。墓石の側には、大きな香炉や供花台が設置されていて、こちらも共同で使う形になるのが一般的です。お墓参りの際は、香炉に線香をあげ供花台に花を供えることができます。ただしお寺や霊園によっては、線香や花以外のお供物が禁止であるケースもあります。
個別式のお墓参り
個別で安置される個別式の永代供養墓は、故人の名前が刻まれた墓石があるタイプのほか、墓石ではなくプレートが設置されているものなどがあります。それぞれのスペースでお墓参りが行えるので、一般墓と同じ感覚でお参りできる場合が多いといえるでしょう。ただしお寺や霊園によってはお供物を置く場所が設けられていないところもあります。
永代供養墓でも、年忌法要などで遺族が法事を行うこともできます。どのような手順で開催するかは、霊園や墓地などによって異なるので、事前に相談して確認するようにしましょう。また法事を行って僧侶に墓前で読経してもらった場合は、お布施をお渡しするのが通例です。
お墓参り当日の流れ

永代供養では、お寺や霊園によってのお墓参りのルールが設けられていることが多いです。事前にルールを確認して、持ち物なども準備して当日を迎えるようにしましょう。
到着からお参りまでの手順
お寺や霊園に到着したら、まず受付でお墓参りに来たことを伝えます。受付なしで墓前に行けるケースもありますが、納骨堂などでは受付が必要な場合がほとんどです。受付が済んだ後は、供養する墓前に向かいます。その後は通常のお墓参りと同様に、墓前に挨拶をし、供花やお供物を飾り、ろうそくを立てて線香に火を灯します。その後、合掌して故人を偲びながら感謝を伝えてお参りをします。お参りが済んだら、線香やお供物等を片付けてから帰るようにします。
お墓の掃除は?
一般のお墓と永代供養墓のお参りでの違いがある点は、「お墓の掃除」をするか否かでしょう。永代供養墓では管理はお寺や霊園が行ってくれるので、遺族が掃除を行う必要がないのが一般的です。ただし納骨堂や個別式など独自スペースがある場合は、拭き掃除などを行ってもかまいません。また個別式で墓石のあるタイプの永代供養墓では、一般墓と同じようにお墓掃除が必要な場合もあります。
永代供養のお墓参りに必要なもの

永代供養墓でのお墓参りは、持って行くものが一般墓と少し異なることがあります。墓地や霊園ごとに異なるので、ルールを調べて準備しましょう。
お墓参りの持ち物
通常のお墓参りでは、供花、線香とローソク、火を点けるためのライターやマッチ、食べ物などのお供物、墓掃除の道具などが必要となります。しかし永代供養墓では、お墓の掃除が不要なところが多く、その場合は掃除道具を持参する必要はありません。さらに線香やローソクなどが禁止されていたり、お供物や花が飾れなかったりする場合もあるので、事前にルールを確認しましょう。
永代供養墓でのお墓参りでは、基本的には手ぶらでお墓参りにいってもかまわないとされています。しかし墓前に手を合わせるので、数珠は忘れないようにしましょう。
お墓参りの服装マナー
お墓参りの服装は特に決まりはなく、普段着でも問題ありません。ただし墓地や霊園であることをわきまえて、華美な服装や露出の多い服装は避けるようにしましょう。また納骨堂など屋内施設では、素足で上がることなく、靴下やストッキングを履くか上履きを持参するのがマナーです。
ただし法事や法要でお墓参りをする際は、三回忌までは喪服を着用し、七回忌以降や合同法要はダークスーツなどの略喪服で行くのがマナーとなっています。
永代供養のお墓参りで注意するポイント

墓地や霊園は365日24時間いつでもお参りできるとは限りません。特に納骨堂などは、開園時間や定休日などが決まっているところも多くあります。また行事や工事などでお参りできないこともあり得るので、あらかじめお参りができるか確認しておきましょう。そのほかにも注意が必要なポイントがいくつかあります。
線香やお供え物など、ルールに従う
霊園や墓地が独自のルールを設けている場合は、それに従うようにします。特に永代供養のお墓の場合、線香やローソクなどの火の使用が禁止されているケースもよく見られます。またお供物が置けるか、飾った供花は持ち帰るべきかなど、ルールについて事前に確認しておきましょう。
ほかの参拝者に配慮する
永代供養墓では、ほかのお墓と距離が近いものもあるので、ほかの参拝者に迷惑をかけないよう配慮しましょう。特にお彼岸やお盆などお墓参りシーズンは、混雑するので注意が必要です。参拝スペースが共同となっているお墓の場合は、お参りは手短に済ませるなど周囲に気を配りましょう。
お墓参りに行けないときの対応方法とは?
永代供養のお墓では、管理はお寺や霊園が行ってくれるので、お墓参りに行けなくても心配ないといえます。しかし行けないことで、気持ちに負担がかかることもあります。そんな場合は仏壇に手を合わせたり、故人の写真やお墓の方角に向かって手を合わせたりするだけでも、心持ちが変わってきます。大切なのは故人を供養したいと思う気持ちです。事情があってお墓参りに行けないなら、自宅で供養するようにしましょう。
永代に渡って供養してくれる「證大寺」の永代供養

写真:船橋昭和浄苑の浄苑墓(永代供養墓)で読経する住職
東京都江戸川区にある證大寺。正式名称は「続命院 法輪山 證大寺」といい、その発祥は承和2年(西暦835年)に遡ります。1200年の歴史があり『続日本後紀』にも登場する由緒あるお寺です。
證大寺はお寺の墓地のほかに、埼玉県に「森林公園昭和浄苑」、千葉県に「船橋昭和浄苑」という2つの霊園を直接運営しています。墓地や2つの昭和浄苑には、いくつかの種類の永代供養のお墓があります。
證大寺の樹木葬

写真:船橋昭和浄苑の白い花の藤棚
證大寺と昭和浄苑の永代供養墓で、代表的といえるのが樹木葬です。藤や桜などがシンボルツリーとして植えられ、四季の花が咲き誇る中で故人は眠ることができます。證大寺の樹木葬の特長は、将来にわたって合祀されないことです。先々は合祀…という樹木葬が多い中で、合祀を望まない方に支持されています。また維持管理費も不要となっています。
区画は個人用だけでなく、ペアや家族で入れるものもあり、ペットもともに入れるという特長もあります。管理やメンテナンスが充実していて、「いついっても花が咲いている」とお墓参りに来た方たちから喜ばれています。
證大寺の納骨堂
證大寺には、永代供養付きの納骨堂もあります。定休日などはないため、365日お墓参りすることができます。お参りは礼拝施設内や本堂で行い、お参り場所まで僧侶や職員が遺骨を丁寧に運んでくれます。区画は1名用の個別区画のほか家族で利用できる区画もあり、家族区画ではペットも一緒に供養してもらえます。
浄縁墓
證大寺と2つの昭和浄苑には「浄縁墓」と名付けられた永代供養墓もあります。「千年先にも残るお墓にしたい」「自分たち自身も入りたいと思えるお墓に」という住職の想いから、石彫家である和泉正敏氏に依頼して作られました。モニュメントのような大きな石の浄縁墓に触れると、寒い冬には温かく暑い夏にはひんやりと感じ、人の心を癒してくれます。
お墓をしっかり管理しながら、供養も手厚く

写真:證大寺の樹木葬で毎日読経する僧侶
證大寺や昭和浄苑では、通常の霊園に比べて2~3倍以上の職員が配置され、お墓をしっかり管理してくれています。管理が行き届いているだけでなく、供養の手厚さでも定評があります。お寺だけでなく2つの昭和浄苑にも本堂があり、僧侶が在住して毎日読経し、職員も全員参加して供養を行ってくれます。證大寺は浄土真宗大谷派のお寺ですが、過去の宗祖・宗派不問で永代供養墓を利用でき、檀家になる必要もありません。
證大寺や昭和浄苑の永代供養のお墓に興味があれば、無料相談や見学会なども開催されているので、ぜひ参加してください。
證大寺:https://shoudaiji.or.jp/
證大寺 江戸川:https://edogawa2.eitaikuyou.life/
森林公園 昭和浄苑:https://higashimatsuyama2.eitaikuyou.life/
船橋 昭和浄苑:https://funabashi2.eitaikuyou.life/
まとめ

永代供養のお墓は、お寺や霊園が管理していても一般墓と同様にお墓参りしてかまいません。むしろ管理されているからこそ、お墓掃除の手間がなく気軽にお参りができるといえるでしょう。とはいえお寺や霊園ごとにルールが定められていることが多いので、規則を守ってお墓参りするようにしましょう。