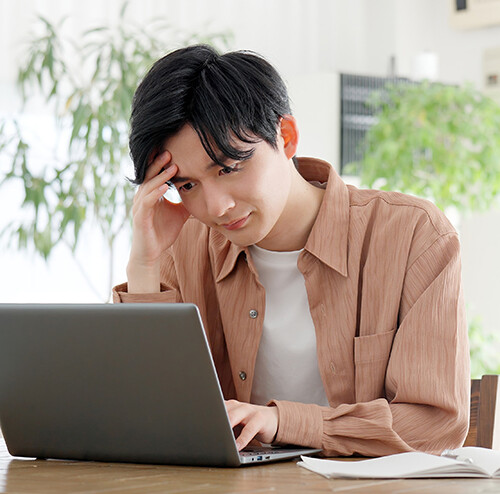納骨はいつ行うのが一般的?時期に決まりはない?四十九日・一周忌など最適な時期と流れ

先祖代々のお墓がありそこに入ると決まっていれば、納骨に悩むことも少ないでしょう。しかしお墓がない、故人の遺志に添った埋葬をしたい、しばらく骨壺を手元に置きたい場合などの理由でスムーズに行えない場合もあります。そこで納骨はいつ行えばいいか、その手順や方法、費用などについて、わかりやすく説明します。
目次
●納骨とは
●納骨はいつ行う?一般的に選ばれやすい納骨の時期
●納骨場所で異なる、納骨の方法
●納骨の手順|納骨式までの流れ
●納骨式当日の流れ
●納骨に必要な費用
●お寺の納骨|多彩な納骨先が選べる「證大寺」の納骨事例
●まとめ
納骨とは

お葬式を終えて火葬を行った後、遺骨は骨壺に納められます。この骨壺をお墓などに安置する儀式を「納骨」といいます。
納骨はいつ行う?一般的に選ばれやすい納骨の時期
納骨する時期について法律などでの指定はありません。
一般的には四十九日法要で行うことが多いため「四十九日に納骨しなければならない」と思い込みがちですが、いつ納骨するかはそれぞれの家庭の事情などで決めてかまいません。
とはいえ節目を選ぶことが多く、一般的には以下のような時期に行われます。
四十九日法要を目安に納骨を行う
自宅で供養した後の忌明けの法要が四十九日法要です。すでにお墓がある場合は、親族が集まる機会でもあるため、この時期に行うことが慣例となっています。
百箇日法要を目安に納骨を行う
百箇日法要は故人が亡くなってから百日目の法要です。故人がその家の先祖として祀られる最初の法要で、遺族にとっては区切りをつけて前進するための儀式ともされています。四十九日では準備が整わなかった場合などに選ばれることが多いです。
一周忌を目安に納骨を行う
一周忌は、亡くなった満1年後に行う法要です。お墓を新しく作る場合、ある程度の時間が必要なので、一周忌を目安に納骨する方も多いです。また年忌法要の中では最も重要とされ、家族や親族などが集う機会となることからも、この時期が選ばれています。
三回忌を目安に納骨を行う
三回忌は故人が亡くなった翌々年(満2年後)に行う法要です。こだわったお墓を作ったり、一周忌ではまだ気持ちの整理がつかなかったりした場合は、三回忌を目安にするのがよいでしょう。
その他 新盆、葬式当日
四十九日の忌明けを過ぎてから、初めて迎えるお盆が新盆です。納骨の時期をなかなか決められないなら、新盆を目安にしてもよいでしょう。
また納骨は四十九日より前に行うことも可能です。諸事情で葬儀後すぐや火葬当日に行うこともあります。
納骨場所で異なる、納骨の方法

現代では、一般的なお墓だけでなく納骨堂や合葬墓、樹木葬などさまざまな納骨場所が選べるようになりました。ただし納骨の方法は場所によって異なるので注意しましょう。
墓地や霊園での納骨の方法
墓地や霊園などにお墓がある場合はそのお墓に、お墓を新たに建てる場合は完成を待って納骨します。お墓の中にはカロートと呼ばれる収納棚があり、そこに骨壷を納めるのが一般的です。ただし関西では、骨壷ではなく納骨袋に入れ替えて埋葬することもあります。
納骨堂での納骨の方法
もともと納骨堂は一時的に遺骨を納める施設でしたが、今ではお墓と同様に供養する場所としての役割を担っています。納骨堂ではお墓と同様に骨壺のまま納骨されます。
納骨堂の種類はロッカー型や墓石型などさまざまなものがあり、個人用のほか夫婦用・家族用などもあります。また継承者がいなくても管理・供養してくれる永代供養の形をとることが一般的です。
ただし多くの納骨堂では一定の期間が過ぎると、他の方と一緒に合祀されます。合祀されると遺骨を取り出して改葬することはできません。
永代供養墓(合祀墓)での納骨の方法
永代供養墓は合祀墓とも呼ばれ、複数の遺骨をまとめて埋葬する他人と共同のお墓です。多くの方と一緒に埋葬するため、遺骨を骨壺から取り出して納骨します。その際に粉骨されることも多いです。
樹木葬での納骨の方法
樹木葬は墓石ではなく木や花を墓標とするお墓です。里山型と庭園型に大別され、里山型では山林などにあるお墓で自然に還るように納骨される場合が多いです。そのため骨壺から遺骨を取り出してそのまま、または骨袋に入れて納骨されます。
一方、庭園型は都市部などにもあり、骨壺や専用の器に入れて納骨される自然に還らない方法のものが多いです。納骨堂と同様に個人用のほか夫婦用・家族用などもあります。一定期間後に合祀される場合とそのまま合祀されない場合があり、寺院や霊園によって異なります。
散骨・分骨など
散骨は遺骨を粉末状にして自然に撒く供養の方法で、納骨は行いません。多くの場合は専門業者に依頼し、散骨が許可されている海上などで行われます(法律がないため海上での許可は不要)。お墓参りができないなどのデメリットがあるため、遺骨の一部を分骨してお墓等に納骨して供養することも多いです。
納骨の手順|納骨式までの流れ

納骨を行うにはそれなりの準備が必要です。どんな手続きが必要でどんなことを決めなければならないかなど、納骨式までの流れを時系列で説明していきます。
1.納骨(埋葬)場所を決める
納骨式までに、どこに納骨するかを決めます。お墓がない場合は、新たにお墓を作るのか、納骨堂や樹木葬などを利用するのか、故人の遺志も尊重しながら決めましょう。
2.必要書類を用意する
納骨を行うには「埋葬許可証」と「墓地の使用許可証」を用意しておく必要があります。
役所に死亡届を提出すると「火葬許可証」が発行されます。これに火葬場が「火葬済」の押印をしたものを「埋葬許可証」といい、お墓や霊園の管理者に納骨時に提出します。
また墓地や霊園の所有者に「墓地の使用許可証」を発行してもらい、こちらも管理者に提出します。
3.納骨式の日程調節をして、お寺に依頼する
納骨式には家族や近しい親族、友人などを呼ぶことが多いですが、誰を呼ぶかには特に決まりはありません。家族のみで行うこともあります。日程を決めてお寺に納骨式の法要をお願いします。
宗教・宗派によっては納骨式を行うのによい日があります。また年末年始やお盆・お彼岸はお寺も忙しい時期なので、日程はお寺とも相談して決めましょう。
今あるお墓に入る場合は、納骨する故人の名前や戒名を墓石に彫刻してもらう必要があります。また実際の納骨は墓石を動かすことになるので、石材店への依頼はお寺や霊園によって石材店が指定されている場合があります。そのため施主側が石材店に直接依頼するのではなく、お寺や霊園側に確認する必要があります。
さらに納骨式当日に必要な供花やお供え物などについて、お寺に確認しておきましょう。参列者に引出物を渡す場合は、その準備も必要です。またお墓に納骨する場合は、納骨式の前に掃除をしてきれいにしておきましょう。
納骨式当日の流れ

納骨式の流れについて説明します。当日は意外とバタバタして忘れ物をしがちで「埋葬許可書を忘れた」「遺骨を家に置いてきた」という事例もあるので気をつけましょう。
1.遺族代表の挨拶
最初に、遺族代表が挨拶をします。一般的には喪主・施主がつとめます。式に参列してくれた方々へのお礼、遺族の近況、納骨式後のおもてなしの有無などを伝えます。
2.納骨
次に僧侶の読経が始まり、いよいよ納骨です。一般的なお墓へ納骨する場合は、霊園の担当者や石材店に納骨作業をお願いすることが多いです。
3.読経・焼香、お供え
納骨が終わると、再び僧侶が読経します。僧侶に合図をもらって、参列者が焼香を行います。読経が終わって焼香が一巡すれば、お墓での納骨式は終了です。その後、お供え物をお供えします。
4.会食
場所を移して会食を行います。最初に喪主・施主が挨拶して献杯して会食が始まります。
会食は参列のお礼のおもてなしという側面もありますが、故人との縁をもう一度考えることができる大切な時間です。ただ食事をするのではなく、故人を偲びながら故人やこの場に集まった人たちの縁を考える時間にしましょう。
会食が終わる前に再度、喪主・施主が挨拶を行い、引出物を用意している場合は終了後に参列者にお渡しします。
納骨に必要な費用

納骨にかかる費用は、埋葬先をどこにするかで大きく変わります。お墓があるかないか、ない場合はどこに納骨するかによっても大きく変わります。
そのためここでは、お墓がある場合の費用、納骨式後の会食やお布施などについて紹介します。
お墓の納骨に関する費用
お墓がある場合、納骨に関する費用は平均5万円といわれています。
■彫刻料
墓石に故人の戒名や命日などを石材店に依頼して刻んでもらいます。相場は3万~5万円程度です。
■納骨作業料
墓石を動かして骨壺を納める作業料で、これも石材店に依頼することが多く作業料は5,000円~が相場となります。
■お供え物の費用
納骨式では通常のお墓参りよりも豪華なお供え物をするのが一般的です。5,000~1万円を目安にし、供花のほか故人の好物などを準備します。
■卒塔婆の費用
宗派によっては納骨式で卒塔婆を立てる必要があるので確かめましょう。卒塔婆は寺院に依頼して用意してもらいます。費用の相場は3,000~5,000円程度です。
納骨式のお布施、会食等の費用
納骨式での僧侶へのお布施は、地域や宗派などによって相場が異なります。また会食や引出物は場合によっては省略されることもあります。
■僧侶へのお布施など
納骨式のみを行う場合、お布施は3万~5万円が相場とされています。年忌法要と一緒に行う場合は、その合計で6万~10万円が相場となります。
お布施のほかにも僧侶にお渡しした方がいいものとして「お車代」と「お膳代」があります。お車代は墓地や霊園がお寺から離れている場合に5,000~1万円程度お渡しします。またお膳代は、納骨式後の会食に僧侶が参加しなかった場合にお渡しします。いずれもお布施とは一緒にせず、無地の白封筒に表書きをして別にお渡しします。
■会食費・引出物
会食1名分の費用は5,000~1万円、引出物の費用は1家族あたり3,000~5,000円が相場とされています。参列者からお香典をいただくことが多いため、それに見合ったおもてなしをしましょう。
お寺の納骨|多彩な納骨先が選べる「證大寺」の納骨事例

證大寺の外営繕によるお墓の清掃
證大寺は江戸川区にある浄土真宗の寺院です。證大寺での納骨は、一般墓の場合は職員が前日までにお墓の清掃を行います。遺族による清掃は不要で、きれいなお墓の状態で納骨ができるようにしてくれます。
真心を込めた永代供養墓への納骨

證大寺の外営繕による納骨の様子
永代供養墓への納骨では、遺族から遺骨をお預かりし、ひとりずつ専用の袋に遺骨を移します。その後、職員が納骨室に1体ずつ丁寧に安置してくれます。納骨堂では、家族ごとに決められた区画に、骨壺のまま納めることができます。
また樹木葬には、家族ごとの専用の納骨箱があり、その中にの専用袋に移して職員が納骨します。
永代供養墓や樹木葬など多彩な納骨先が選べること、隣接する墓所のほかに埼玉県・森林公園昭和浄苑、千葉県・船橋昭和浄苑などお寺自らが運営する霊園があることから、證大寺には多くの方から納骨についての相談が寄せられています。
納骨事例(1)|父が次男のため先祖のお墓がない、宗旨・宗派も不明
お墓がない方、宗旨・宗派がわからない方でも問題ありません。ある方は自身のお父様の納骨で相談に来られたそうです。「父が次男で、先祖代々のお墓がない」しかも「これまで宗教に関心がなかったため、宗旨・宗派もわからない」とのことでした。
證大寺は納骨後の供養は浄土真宗の型式で行うものの、生前の宗教・宗派は不問であること、また一般墓のほかさまざまな形態の納骨先があることを説明。一周忌には無事、納骨することができました。
納骨事例(2)|遠方でお墓参りになかなか行けない

また別の方で、お母様を病気で亡くした方からの相談がありました。先祖代々のお墓はあったものの遠方で、お墓参りに行きにくいという悩みがありました。そこで墓じまいを行い、新たなお墓を建てることに。お父様が車椅子での生活であることを考慮して、バリアフリーの墓地を選択。お墓を建て直し、三回忌を待って納骨ができました。
納骨事例(3)|故人と別れがたく、三回忌を過ぎても手元供養を続けている
小さなお子様を亡くされた方からの相談もありました。大切な子が突然亡くなって悲しみが癒えず、納骨できなかったそうです。四十九日はもちろん、新盆を迎えても三回忌が過ぎても手元供養を続けたといいます。そのような中で七回忌法要が行われ、證大寺の住職と向き合って話をする機会があり、そこで気づきをあたえられたとのこと。
「亡くなった子としっかりと向き合うことで、悲しみだけでなく、大切な子からわたしも願われていた」「親の私はあなたという大切な子がいたことで、私は親にさせてもらうことができた」と感じたそうです。子どもを亡くした悲しみは深かったものの、気づきにより「子どもと出遇い直すことができた」と心が落ちついて、納骨をすることになりました。
お骨ではなく、仏様に手を合わせる
納骨の時期が延びてしまう場合、それまでの間は手元供養をすることになりますが、證大寺の住職は「お骨ではなく仏様に手を合わせて供養を行ってほしい」といいます。「お骨が大切なことはわかります。しかし手をあわせる先はお骨ではなく、仏様となられた大切な方です。仏様となられた大切な方は、いつでもあなたのことを照らしております。」
お墓がなくて納骨先が決まらない場合や、悲しみが深すぎてすぐに納骨する気持ちになれないなどの理由で、納骨の時期が延びてしまうのも仕方ないことです。そんな時は悩みを一人で抱え込まず、お寺に相談してください。最適な納骨先が見つかり、納得できる納骨の機会が得られるなど光明が見えてくるでしょう。
まとめ

納骨についての一般的な時期や、納骨の方法、手順、費用などについてご紹介しました。また「納骨は四十九日」というのも慣例にすぎないことも、おわかりいただけたかと思います。
納骨には法的な期限はないものの、いずれは埋葬しなければなりません。納骨は残された家族にとって、大切な節目になります。故人のためにも残された人々が悲しみを乗り越えるためにも、納骨先や時期についてよく考えて行ってください。