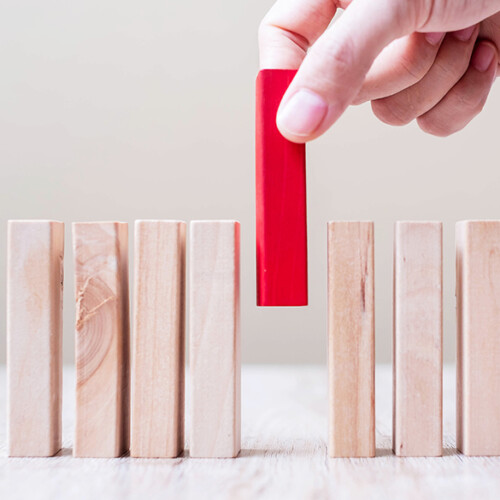墓じまいの費用は誰が払う?兄弟間のトラブルを防ぐ相場と負担の決め方

「墓じまいの費用は、いったい誰が払うべきか」。これは多くの方が悩まれる問題です。
墓じまいの費用はおおよそ50万円〜300万円程度が相場ですが、誰が負担するかには明確な決まりがなく、家族での話し合いが欠かせません。本記事では、代表的な負担パターンや相場、そして円満に合意するための話し合いの進め方を解説します。
目次
●「兄弟の一人だけが負担するのは不公平?」墓じまいの費用、法的に「誰が払う」という決まりはない
●墓じまい費用負担の代表的な4パターン
●墓じまいの費用総額はいくら?費用の内訳と相場を解説
●親族トラブルを回避!費用負担で揉めないための話し合いの進め方
●墓じまいの費用が払えない・高いと感じた時の対処法
●費用を誰も払わない…墓じまいせず放置するとどうなる?
●證大寺のご案内
●まとめ|費用負担の話し合いは、円満な墓じまいの第一歩
「兄弟の一人だけが負担するのは不公平?」墓じまいの費用、法的に「誰が払う」という決まりはない

墓じまいは「誰がやるのか」や「費用は誰が払うのか」があいまいなまま進めると、親族間でトラブルになることも少なくありません。お墓をしまい、ご遺骨を別の場所へ移す「墓じまい」を考えるとき、多くの方がまず直面するのが費用の問題です。「この墓じまいの費用は、いったい誰が払うべきなのだろうか」と、悩まれるかもしれません。
大切なこととして、まず知っておいていただきたいのは、墓じまいの費用を誰が負担すべきかについて、民法第897条では「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」が祭祀財産を承継すると定められていますが、費用負担までは明記されていません。実際のところは、約6〜7割が承継者本人、残りは兄弟姉妹での分担など、ご家庭によって様々です。
だからこそ、最も重要になるのは、ご家族やご親族など、関係される方々の間での事前の話し合いと、皆様が納得のいく合意です。誰か一人が決めて進めるのではなく、皆様で丁寧に相談することが、円満な墓じまいへの第一歩となります。
一般的には「祭祀承継者」が中心となるケースが多い
法律上の定めはありませんが、実際のところ、誰が話し合いの中心となり、費用を工面することが多いのでしょうか。
一般的には、そのお墓や仏壇、系図など、ご先祖様から受け継がれてきた「祭祀財産(さいしざいさん)」を引き継いだ方、すなわち「祭祀承継者」が中心的な役割を担うケースが多く見受けられます。
お墓の管理を主に担ってこられた方として、墓じまいを主導し、費用負担の割合も高くなる傾向にあるようです。
ただし、これもあくまで慣例的なものであり、「承継者だから全額を負担しなければならない」という義務ではありません。費用が高額になることも多いため、承継者お一人ですべてを背負う必要はない、ということも心に留めておいていただければと思います。
墓じまい費用負担の代表的な4パターン

墓じまいの費用を誰が払うかについては、決まりがないからこそ、ご家庭の事情によってさまざまな形があります。ここでは、代表的ないくつかのパターンをご紹介します。ご自身の状況と照らし合わせながら、ご家族とのお話合いの参考にしてみてください。
| パターン | 主な負担者 | 割合目安※ | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ①祭祀承継者が全額 | 長男・名義人など | 約60% | 他の相続財産を考慮して負担するケース |
| ②兄弟姉妹で分担 | 同世代の兄弟 | 約25% | 法要・改葬費用を等分または比率調整 |
| ③親族一同で分担 | 叔父・叔母など含む | 約10% | 感謝金・協力金としての支援 |
| ④故人が生前準備 | 故人の遺産 | 約5% | エンディングノート等で明記される場合 |
※実例に基づいた傾向の目安になります。
パターン1:お墓の承継者(祭祀承継者)が全額負担する
まず、先ほど触れた「祭祀承継者」お一人が、費用を全額負担されるケースです。
特に、ご両親などからお墓以外の財産も相続されている場合に、その中から費用を工面するという考え方で、この形をとられることが多いとされています。
この場合であっても、費用を負担する承継者の方が、他のご兄弟やご親族へ事前に「なぜ墓じまいをするのか」「新しいご遺骨の行き先はどうするのか」を丁寧に説明し、皆様の理解を得ておくことが大切です。事後の報告とならないよう配慮することが、後のわだかまりを避けることにつながります。
パターン2:兄弟姉妹で費用を分担・協力する
現実的に、ご相談として多いのが、ご兄弟や姉妹で費用を分担・協力し合うケースです。
墓じまいの費用は、新しい納骨先によってはまとまった金額になることも少なくありません。祭祀承継者お一人の負担が重い場合、ご兄弟姉妹で助け合うのはとても自然なことといえます。
皆様で均等に分ける方法もあれば、承継者が少し多めに負担し、残りを他の方で分ける方法もあります。あるいは、これまでの法要やお墓の管理にかかってきた手間や費用なども考慮して、負担の割合を相談されることもあるようです。
お金のことだけでなく、これを機にご先祖様の供養について皆様で一緒に考える、大切な機会になるかもしれません。
パターン3:親族一同(叔父・叔母など)で費用を分担する
そのお墓に縁のある、より広いご親族、例えば故人のご兄弟(ご自身から見て叔父・叔母など)にもご相談の上、費用を分担するケースもあります。
ただ、ご兄弟姉妹の場合と比べると、関係性が少し遠くなるため、あくまで「援助」や「協力」という形でお願いすることが多いようです。
例えば、「お墓を更地に戻すまでの撤去費用」は縁のある親族一同で分担し、「新しい納骨先の費用」は承継者やそのご兄弟で負担する、といった費用の項目ごとで切り分けて相談するのも一つの方法とされています。
パターン4:故人が生前に費用を準備している
近年は「終活」という言葉も広まり、生前に「亡くなった後」の準備をする方が増えています。
その一環として、残されるご家族に負担をかけないよう、墓じまいの費用をご自身で準備されているケースもあります。
故人様が遺言書やエンディングノートなどを残されていないか、一度確認してみることも大切です。もし費用が準備されていたならば、それはご家族を想う故人様の最後のお気持ちでもあります。その想いを尊重し、大切に使わせていただくことが、一つの供養の形ともいえます。
墓じまいの費用総額はいくら?費用の内訳と相場を解説

墓じまいを具体的に進めるにあたり、次に気になるのは「いったい、いくらかかるのだろうか」という費用そのものでしょう。
墓じまいにかかる費用の総額は、一般的に50万円から300万円程度が目安とされています。ずいぶんと幅があると感じられるかもしれませんが、これは主に「今あるお墓をどう片付けるか」と「ご遺骨を新しくどこへ納めるか」によって、必要な費用が大きく変わるためです。
特に、ご遺骨の「新しい納骨先(改葬先)」をどのような形にするかが、総額に最も大きな影響を与えるといわれています。ここでは費用の内訳を大きく3つに分けて、それぞれの相場を解説します。
①お墓の撤去関連の費用
まずは、現在のお墓をしまい、更地に戻すためにかかる費用です。
墓石の解体・撤去費用
墓石を解体し、基礎部分なども含めて撤去、整地して墓所を管理者へお返しするための費用です。墓地の広さ(1平方メートルあたり8万円~15万円程度が目安)や、重機が入りやすいかといった立地条件によって変動します。
閉眼供養(へいがんくよう)のお布施
墓じまいの際、お墓の前で僧侶に読経していただく儀式のためのお布施です。一般的に「魂抜き」や「お性根抜き」とも呼ばれ、これまでお世話になったお墓への感謝を伝える大切な儀式とされています。3万円~10万円程度が目安とされています。
(※浄土真宗では、お墓に魂が宿るという考え方はとりませんが、お墓を動かす際の「遷座法要(せんざほうよう)」として、仏様への感謝を伝える法要を大切に営みます。)
墓じまいのお布施について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
>墓じまいのお布施、相場やマナーを徹底解説!後悔しないための完全ガイド
離檀料(りだんりょう)
寺院墓地にお墓がある場合、そのお寺の檀家(だんか)をやめる際に、これまでお世話になった感謝の気持ちとしてお渡しするお布施です。「必ず支払わなければならない」という性質のものではありませんが、長年のお付き合いへの感謝を示すものとして、5万円~20万円程度が目安とされることがあります。お寺様との関係性にもよりますので、事前にご住職へご相談されるのがよいでしょう。
②新しい納骨先(改葬先)の費用
墓じまいの総費用を大きく左右するのが、この新しい納骨先の費用です。ご家族のこれからの供養のあり方にも関わる部分ですので、どのような選択肢があるかを知っておくことが大切です。
一般墓
新しく別の場所(霊園など)に、従来のような墓石を建てる方法です。永代使用料や墓石工事費などで、100万円~300万円程度が目安とされています。
永代供養墓(えいたいくようぼ)
霊園やお寺が、ご家族に代わってご遺骨の管理・供養を永代にわたって行うお墓です。他の方のご遺骨と一緒に納める「合祀(ごうし)」タイプ(5万円~30万円程度)と、一定期間は個別に安置される「個別」タイプ(20万円~80万円程度)があり、費用を抑えやすい選択肢です。
樹木葬(じゅもくそう)
墓石の代わりに、樹木を墓標とするスタイルのお墓です。自然志向の方に選ばれることが多く、10万円~80万円程度が目安とされています。
納骨堂(のうこつどう)
主に屋内の施設にご遺骨を納める方法です。ロッカー式や仏壇式、自動搬送式など様々なタイプがあり、20万円~100万円程度が目安です。
散骨・手元供養
ご遺骨を粉末状にして海や山にまく「散骨」(3万円~30万円程度)や、小さな骨壺などに入れてご自宅で供養する「手元供養」(数千円~数十万円程度)といった方法もあります。
③行政手続きの費用
墓じまい(改葬)には、現在お墓がある自治体で「改葬許可証」を発行してもらうなど、いくつかの行政手続きが必要です。
その際に、埋葬(納骨)証明書や受入証明書といった書類の発行手数料がかかる場合がありますが、合計しても数百円から1,500円程度が一般的です。東京都江戸川区や千葉県船橋市、埼玉県東松山市など多くの自治体では、手数料が無料か、かかっても少額ですので、この部分が大きな金銭的負担になることは少ないです。
親族トラブルを回避!費用負担で揉めないための話し合いの進め方

墓じまいの費用負担を「誰が払うか」という問題は、ご家族やご親族の間でとてもデリケートな話題です。ここで進め方を間違えてしまうと、思わぬトラブルに発展し、お互いの心にしこりを残してしまうことにもなりかねません。
円満に進めるために、どのような点に心を配り、話し合いを進めていけばよいのでしょうか。
なぜ揉めるのか?よくあるトラブルの火種
まず、どのようなことで揉めやすいのかを知っておくことが大切です。
・「何の相談もなく、墓じまいを決めてしまった」(事後報告)
・「いきなり費用の負担を一方的に求められた」
・「新しい納骨先を、承継者が勝手に決めてしまった」
こうしたことは、ご兄弟やご親族からすると、「ご先祖様のことを軽んじられた」「自分たちの気持ちが無視された」と感じさせてしまう原因になります。たとえ祭祀承継者であっても、お墓はご先祖様と縁のある皆様にとって大切な場所です。だからこそ、皆様の「お気持ち」を大切にするプロセスが不可欠です。
話し合いのステップ1:費用の話の前に「想い」を共有する
話し合いを切り出すとき、最も大切なことは、いきなり「お金の話」から入らないことです。
「墓じまいに50万円かかるから、兄弟で分担してほしい」と切り出すのではなく、まずは「なぜ、自分は墓じまいをしたい(しなければならない)と考えているのか」という、ご自身の「想い」や「理由」を丁寧に伝えることから始めてみてください。
・「このままでは、将来お墓を管理する人がいなくなり、ご先祖様のお墓が無縁仏になってしまうのが心苦しい」
・「自分も高齢になり、遠方のお墓参りを続けるのが難しくなってきた」
・「だからこそ、皆がきちんとお参りでき、これからも永く供養を続けていける形にしたい」
こうした想いを共有することができれば、他のご兄弟やご親族も、「それは大切なことだ」「一緒に考えよう」と、前向きに受け止めやすくなるはずです。
話し合いのステップ2:費用の見積もり(内訳)を全員で確認する
皆様の想いや、墓じまいをするという方向性について合意ができたら、次に具体的な費用の話をします。
このとき、ただ「総額で〇〇円かかる」と伝えるだけでは、その金額が妥当なのか分かりにくいものです。
石材店など複数の専門業者から見積もりを取り、その内訳(墓石撤去費用、新しい納骨先の費用など)が分かる資料を皆様で確認することが大切です。客観的な数字(見積書)を土台にすることで、「何にいくらかかるのか」が明確になり、冷静に費用負担の相談を進めやすくなります。
話し合いのステップ3:決まった内容は書面(合意書)に残す
皆様で話し合い、費用負担の割合などが決まったら、その内容を簡単な書面(合意書)として残しておくことをお勧めします。
口約束だけでは、後になって「言った」「言わない」といった行き違いが生じる可能性も否定できません。
堅苦しい契約書のようなものでなくても構いません。「墓じまいの総費用」「誰が、いくらを、いつまでに負担(支払う)するか」といった要点をまとめた覚書をご家族・ご親族間で共有しておくだけで、後々の安心感が大きく違ってきます。これは、お互いの信頼関係を守るためにも大切なことといえます。
墓じまいの費用が払えない・高いと感じた時の対処法

ご家族で話し合ったものの、墓じまいの総費用が思ったよりも高額で、すぐに工面するのが難しい、という場合もあるかもしれません。あるいは、ご自身の負担額が大きく、お一人で払うのが困難な状況も考えられます。
そのような時は、少し立ち止まって、費用負担を軽くするための方法や、他の選択肢がないかを検討してみましょう。慌てずに情報を集め、ご自身やご家族にとって無理のない道を探ることが大切です。
費用を安く抑える工夫(相見積もり・改葬先の見直し)
まず、費用そのものを見直す方法です。
一つは、墓石の解体・撤去を依頼する石材店を、複数の業者から見積もりを取って比較すること(相見積もり)です。業者によって費用が異なる場合がありますので、内訳をよく確認し、納得のいくところに依頼することがコストダウンにつながる可能性があります。
(※ただし、墓地によっては石材店が指定されている場合もありますので、事前に墓地の管理者様にご確認ください。)
もう一つ、そして最も費用に影響するのが「新しい納骨先(改葬先)」の選択です。もし、費用面での負担が大きい場合は、改葬先の種類を見直すことも一つの方法です。
例えば、前述した「永代供養墓(えいたいくようぼ)」の中でも、他の方のご遺骨と一緒になる「合祀(ごうし)」タイプを選ぶと、費用を大きく抑えられることが一般的です。「散骨」や「手元供養」も、比較的費用を抑えやすい選択肢とされています。
費用面だけで決めることではありませんが、ご家族が納得できる供養の形の中で、負担の少ない方法を改めて探ってみてください。
永代供養について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
>永代供養墓とは?お墓の種類・費用相場など基本からわかりやすく解説!
メモリアルローンを利用する
どうしても一時的にまとまった費用を捻出するのが難しい場合には、金融機関が提供している「メモリアルローン」の利用を検討する方法もあります。
これは、お墓や葬儀、仏壇など、供養に関連する費用に用途を限定したローン商品とされています。一般的なフリーローンなどと比べて、金利が低めに設定されている場合があるようです。
もちろん借入れには審査があり、計画的な返済が必要となりますので、最終的な手段の一つとして、慎重に検討することをおすすめします。
費用を誰も払わない…墓じまいせず放置するとどうなる?

ご家族やご親族で話し合ったものの、「誰も費用を払えない」、あるいは「誰も払いたがらない」といった理由で、墓じまいができないまま、お墓の管理がなされなくなってしまうケースも、残念ながらあるようです。
もし、お墓をそのまま放置してしまったら、どうなるのでしょうか。
お墓がある限り、その区画の「年間管理費」の支払い義務は続きます。この管理費を滞納し続けると、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、無縁墳墓改葬の公告→撤去→合祀という法的プロセスが進む場合があります。
まず、墓地の管理者(寺院や霊園、自治体)から督促が届きます。それでも支払いや連絡がない状態が続くと、法的な手続きを経て、最終的にはお墓を使用する権利が失われてしまう可能性があります。
そして、お墓は墓地管理者によって解体・撤去され、中にあったご遺骨は「無縁仏(むえんぼとけ)」として、他の方々のご遺骨と一緒に合祀墓(ごうしぼ)などに移されることになります。これは、お墓を無縁化させないための、墓地管理上の最後の措置といえます。
一度、無縁仏として合祀されてしまうと、他の方のご遺骨と一緒になってしまうため、後から特定のご遺骨だけを取り出すことは、原則としてできなくなります。
ご先祖様のお墓をそのような形にしないためにも、費用負担の問題は、関係される皆様で真摯に向き合い、何らかの合意点を見つけていただくことが切に望まれます。
證大寺のご案内

墓じまいの費用や、ご家族・ご親族との話し合いの進め方について、ここまでご紹介してまいりました。しかし、実際にご自身の状況に当てはめてみると、どのように進めたらよいか、どなたに相談すべきか、迷われることも多いかと存じます。
そのようなお悩みや不安をお持ちのときは、どうぞお一人で抱え込まず、専門的な知識を持つ證大寺までご相談ください。
ご相談について詳しくは、下記までメールでお問合せください。
edogawa_hp@sinran.com
墓じまい相談の実績と専門知識
私たち證大寺(しょうだいじ)は、これまで1,000件を超える墓じまいや改葬(お引越し)に関するご相談をお受けしてまいりました。
人生の大きな節目である墓じまいを、皆様が安心して進められますよう、経験豊富なスタッフが皆様のお気持ちに静かに寄り添い、お手伝いをさせていただきます。費用のお悩みから、お手続きの具体的な流れ、ご親族へのご説明の仕方まで、どのようなことでもお気軽にお尋ねください。
改葬先の選択肢としての霊園拠点
證大寺では、墓じまい後の新しいご供養の場所として、様々な選択肢をご用意しております。
・證大寺 江戸川本坊(東京都江戸川区)
・森林公園 昭和浄苑(埼玉県東松山市)
・船橋 昭和浄苑(千葉県船橋市)
いずれも、お墓参りのしやすい環境を大切にした霊園です。永代供養墓や樹木葬など、現代の多様なニーズにお応えできるご供養の形をご提案しております。
安心のサポート体制(無料相談会・宗派不問)
皆様のお悩みに、より丁寧にお応えするため、證大寺では「無料相談会」を随時開催しております。まずは皆様のお話をじっくりとお伺いすることから始めさせていただきますので、どうぞお気軽にご参加ください。
また、證大寺の永代供養墓は、宗旨・宗派を問わず、どなたでもお受け入れしております。これまでのお寺様が異なる宗派であった場合でも、何ら心配はいりません。ご先祖様を大切に想うお気持ちを、そのままお持ちいただければと思います。
墓じまいは、皆様のご事情や想いによって、その形もさまざまです。證大寺は、皆様が納得のいく新たな一歩を踏み出すための、信頼できるパートナーでありたいと願っております。
まとめ|費用負担の話し合いは、円満な墓じまいの第一歩
墓じまいの費用を「誰が払うか」ということについて、法的な決まりはありません。だからこそ、ご家族やご親族が、お互いを思いやりながら話し合う時間が何よりも大切になります。
その話し合いの根底に、「ご先祖様への感謝の気持ち」や「これからも供養を続けていきたい」という想いを共有することができたなら、それはきっと円満な合意へとつながっていくはずです。
費用という、ともすると切り出しにくいお話かもしれませんが、その点を皆様で明確にし、納得し合うことこそが、これからのご家族の新たなご供養の形を、穏やかにスタートさせるための大切な第一歩となるのではないでしょうか。