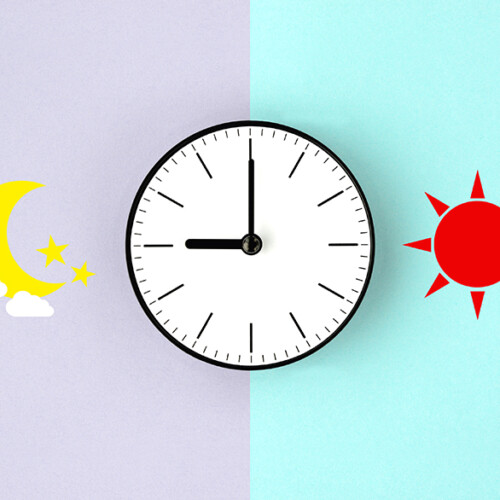【お盆とお彼岸の違い】時期・やるべきこと・マナーを専門家が徹底比較

お盆はご先祖様を家に迎える期間、お彼岸は私達が会いに行く期間です。この根本的な違いから、時期、お供え、新盆の迎え方、お布施のマナーまで徹底解説。これ一本で、お盆とお彼岸の全ての疑問が解決します。
目次
●はじめに:似ているようで全く違う、お盆とお彼岸
●お盆とお彼岸|根本的な意味と目的の違い
●由来と語源|文化と宗教から見る違い
●お盆とお彼岸の時期と期間|毎年いつ?具体的な日程の違い
●お盆とお彼岸でやるべきこと|共通の供養と独自の風習の違い
●お盆とお彼岸でのお供え物|象徴的な食べ物と花の選び方の違い
●初めて迎える場合:新盆(初盆)と初彼岸の格式の違い
●知っておきたい作法:お布施やお供え物のマナー
●お盆とお彼岸に関するよくある質問
●證大寺のお盆とお彼岸について
●まとめ:違いを理解し、ご先祖様を敬う心を大切に
はじめに:似ているようで全く違う、お盆とお彼岸

ご先祖様を供養する大切な行事として、私たちの暮らしに深く根付いている、お盆とお彼岸。どちらも家族が集い、故人様を偲ぶ穏やかな時間であることに変わりはありません。
しかし、「具体的に何が違うのでしょうか」と尋ねられると、はっきりと答えるのは少し難しいかもしれませんね。
この記事では、そんなお盆とお彼岸の違いについて、一つひとつ丁寧に紐解いていきます。それぞれの行事が持つ根本的な意味から、過ごし方、マナーに至るまで、分かりやすく解説してまいりますので、どうぞ最後までお付き合いください。
お盆とお彼岸|根本的な意味と目的の違い

二つの行事を理解する上で、まず心に留めておきたいのが、その根本的な意味と目的の違いです。ご先祖様と私たちが、どのように関わる時間にしたいのか。その視点に、大きな違いがあるといわれています。
お盆:ご先祖様を自宅に「お迎え」してもてなす期間
お盆は、あの世(浄土)にいらっしゃるご先祖様の霊が、年に一度、私たちの住む家へと帰ってこられる期間であるとされています。
主な目的は、久しぶりに帰ってこられたご先祖様を、家族みんなで心を込めて「お迎え」し、日頃の感謝を伝え、ゆっくりと過ごしていただくための「おもてなし(供養)」をすることにあります。
普段は離れて暮らすご先祖様が、すぐそばにいてくださる。そんな温かい繋がりを感じられるのが、お盆という時間なのです。
お彼岸:ご先祖様がいる彼岸に「思いを馳せる」期間
一方でお彼岸は、私たちがいるこの世「此岸(しがん)」と、ご先祖様がいるあの世「彼岸(ひがん)」との距離が、一年で最も近くなるとされる期間です。
そのため、ご先祖様がこちらへ帰ってくるお盆とは逆に、私たちがご先祖様のもとへ思いを馳せ、会いに行くという考え方が基本となります。お墓参りが大切にされるのも、こうした理由からです。
同時に、お彼岸は仏様の教えを実践する修行の期間でもあります。「彼岸」とは本来、迷いのない悟りの世界を指す言葉です。その理想の世界に到達するための修行「六波羅蜜(ろくはらみつ)」に励むべき大切な一週間ともいわれています。お盆との大きな違いの一つと言えるでしょう。
由来と語源|文化と宗教から見る違い

お盆とお彼岸が持つ意味の違いは、それぞれの成り立ち、そのルーツを辿ることで、より深く理解することができます。なぜこれほど異なる意味を持つようになったのか、その背景を静かに紐解いてみましょう。
お盆の由来:「盂蘭盆会(うらぼんえ)」という仏教説話から
お盆の正式名称は「盂蘭盆会(うらぼんえ)」といいます。これは、古代インドの言葉であるサンスクリット語の「ウランバーナ」を漢字で表したもので、「逆さ吊りの苦しみ」という意味を持つとされています。
この言葉の背景には、お釈迦様の弟子の一人、目連尊者(もくれんそんじゃ)とそのお母様の、次のような物語があります。
神通力で亡き母の姿を探した目連は、母が餓鬼道に堕ち、逆さ吊りにされて苦しんでいることを知ります。母を救いたい一心でお釈迦様に助けを求めると、「夏の修行を終えた僧侶たちに、たくさんのご馳走をもてなしなさい」という教えを受けました。
目連がその教えの通りに実践したところ、その功徳によって母は苦しみから救われた、と伝えられています。この物語が、ご先祖様の霊をお迎えし、手厚くおもてなしをする現在のお盆の風習へと繋がっていきました。
お彼岸の由来:日本独自の農耕儀礼と仏教思想の融合
一方で、お彼岸はインドや中国にはない、日本で育まれた独自の仏教行事です。その語源は、サンスクリット語の「パーラミター」にあり、「彼岸へ至る」、つまり悟りの境地へ至るという意味が込められています。
日本では古くから、昼と夜の長さがほぼ同じになる春分と秋分の日を特別な日としてきました。豊かな実りをもたらす太陽や、自然の恵みに感謝を捧げ、ご先祖様を敬う農耕儀礼が、暮らしの中に根付いていたのです。
この日本古来の自然信仰やご先祖様を大切にする心に、仏教の「彼岸に至るための修行」という考え方が合わさり、長い年月をかけて、現在のお彼岸の形が作られていきました。お盆とお彼岸の違いには、このような文化的な背景の違いもあるのです。
お盆とお彼岸の時期と期間|毎年いつ?具体的な日程の違い

それぞれの行事が持つ意味を理解すると、次はその時期がいつなのかが気になりますね。お盆とお彼岸の期間には、それぞれ明確な定め方があります。
お盆の期間:7月盆と8月盆があり、地域で異なる
現在、全国的に最も広く行われているお盆は、8月13日のお迎え火から16日の送り火までの4日間です。これは一般的に「月遅れ盆」と呼ばれています。
一方で、東京都江戸川区をはじめとする都心部や一部の地域では、新暦の7月13日から16日をお盆の期間とする「新暦盆」が行われます。
このように地域によってお盆の時期が違うのは、明治時代に行われた暦の改正がきっかけとされています。暮らしの暦が新しくなった際に、お盆の時期をどうするかという解釈が地域によって分かれ、今に至っているのです。
お彼岸の期間:春と秋の年2回、祝日を中日とした7日間
お彼岸は、春と秋の年に二度訪れます。
国民の祝日である「春分の日」と「秋分の日」。この祝日を期間の真ん中の日、すなわち「中日(ちゅうにち)」として、その前後3日間をあわせた、合計7日間がお彼岸の期間と定められています。
期間の初日を「彼岸の入り」、そして最終日を「彼岸の明け」と呼びます。この一週間を通して、私たちはご先祖様や仏様の教えに、静かに心を向けていくのです。
春分の日と秋分の日は、その年ごとの天文学的な計算によって定められるため、お彼岸の期間も毎年少しずつ変動します。ちなみに、来年2026年(令和8年)の春のお彼岸は、3月20日(金・祝)が中日となります。
お盆とお彼岸でやるべきこと|共通の供養と独自の風習の違い

それぞれの行事が持つ意味や時期がわかると、次に「具体的に何をすればよいのだろう」という疑問が浮かびますね。期間中の過ごし方にも、お盆とお彼岸の特徴的な違いが見えてまいります。
共通して行うこと:お墓参りと仏壇の掃除
まず、どちらの行事にも共通する、最も大切なことがあります。それは、お墓やご自宅の仏壇をきれいに掃除し、心を込めてお参りをすることです。
ご先祖様が安らかに過ごせるよう、また、いつでも気持ちよくお参りができるよう、感謝の気持ちを込めてお墓の周りを掃き清め、墓石を丁寧に磨きます。ご自宅の仏壇も同様に、普段はなかなか手の届かない場所まで、きれいに整えたいものですね。
物理的な場所を清めることは、私たち自身の心を洗い、整える時間にも繋がります。ご先祖様への感謝を示す、供養の基本となる行いです。
お盆のお墓参りについて、流れや持ち物などこちらの記事でご紹介していますのでご興味のある方はご覧ください。
>お盆のお墓参りはいつ行く?お墓参りの流れと必要な持ち物を解説
お盆ならではの風習:お迎えとお見送りの準備
ご先祖様を自宅に「お迎え」し、「おもてなし」をするお盆には、そのための特別な準備や風習があります。いずれも、ご先祖様が気持ちよく過ごせるようにという、優しい願いが込められたものです。
◯盆棚(ぼんだな)・精霊棚(しょうりょうだな)
ご先祖様の霊が滞在される場所として、仏壇の前などに設ける特別な祭壇です。ござを敷き、位牌を安置して、さまざまなお供え物を飾ります。
◯精霊馬(しょうりょううま)・精霊牛(しょうりょううし)
きゅうりやナスに、割り箸などで足をつけたお供え物です。きゅうりは足の速い馬に見立て、「少しでも早く家に帰ってきてほしい」という願いを。ナスは歩みの遅い牛に見立て、「帰りはゆっくり、景色を楽しみながらお帰りください」という願いが込められているといわれます。
◯盆提灯(ぼんぢょうちん)
ご先祖様の霊が、夜道に迷うことなく自宅にたどり着けるよう、目印として灯す提灯です。
◯迎え火・送り火
お盆の初日(13日)の夕方に、ご先祖様をお迎えするために焚くのが「迎え火」。そして最終日(16日)に、ご先祖様をあの世へお見送りするために焚くのが「送り火」です。
お彼岸ならではの過ごし方:六波羅蜜(ろくはらみつ)の実践
お彼岸は、お墓参りをしてご先祖様を供養すると同時に、悟りの世界(彼岸)へ至るための仏道修行に励む期間でもあります。この修行は「六波羅蜜(ろくはらみつ)」と呼ばれ、六つの徳目が示されています。
六波羅蜜は、仏様が私たちに教えてくれた“よりよく生きるための6つの心得”です。日々の生活の中でも、ほんの少し意識することで実践できる内容ばかりです。
布施(ふせ):見返りを求めず、他者に親切にすること。
→たとえば、道を聞かれたら笑顔で教える、困っている人に席を譲るなど、思いやりの行動が「布施」です。
持戒(じかい):決められたルールを守り、自分の行いを律すること。
→信号を守る、時間を守る、ごみを分別するといった小さな約束を守ることも立派な持戒です。
忍辱(にんにく):困難に耐え、心を穏やかに保つこと。
→怒りそうになった時に深呼吸して落ち着く、人の言葉にカッとならないなど、自分の感情を整える練習です。
精進(しょうじん):目標に向かって、努力を続けること。
→毎朝の挨拶を欠かさない、家の掃除を少しずつでも続けるなど、コツコツ積み重ねることが精進です。
禅定(ぜんじょう):心を静め、自分自身と向き合うこと。
→スマホを置いて静かな時間を5分作る、一人で散歩して心を整える。そんな時間も禅定になります。
智慧(ちえ):物事の本質を見極め、正しく判断する力を持つこと。
→目の前の出来事を一歩引いて考える。他人の立場になって考えることも、智慧の実践です。
お彼岸の期間は、ご先祖様を思うとともに、自分自身の行いを静かに振り返る良い機会となるかもしれません。
お盆とお彼岸でのお供え物|象徴的な食べ物と花の選び方の違い

ご先祖様への感謝の気持ちを表すお供え物にも、それぞれの行事を象徴する違いがあります。心を込めて選ぶお供え物は、きっとご先祖様に喜んでいただけることでしょう。
お盆のお供え物:精霊馬やそうめん、夏の野菜・果物
お盆のお供え物は、帰ってこられたご先祖様をもてなすための品々が中心となります。きゅうりやナスの精霊馬も、大切なお供え物の一つです。
その他にも、そうめんをお供えする風習が広く見られます。これには、ご先祖様があの世から荷物を運ぶための「荷綱」に見立てたという説や、細く長く幸せが続くようにという願いが込められているなど、諸説あります。
また、提灯のように見えることから、ほおずきを飾ることもあります。お花は、夏の暑さの中でも長持ちしやすい菊やリンドウなどがよく選ばれるようです。
お彼岸のお供え物:春は「ぼた餅」、秋は「おはぎ」
お彼岸のお供え物として馴染み深いのが、「ぼた餅」と「おはぎ」です。実はこの二つは基本的に同じもので、季節によって呼び名が変わります。
春のお彼岸には、その季節に咲く牡丹(ぼたん)の花にちなんで「ぼた餅」。秋のお彼岸には、同じく秋の七草の一つである萩(はぎ)の花にちなんで「おはぎ」と呼ばれるようになりました。
また、おはぎに使われる小豆の赤い色には、古くから邪気を払う力があると信じられており、ご先祖様の供養にふさわしい食べ物とされてきました。
お彼岸にお供えするお花には、特に厳しい決まりはありません。故人様がお好きだったお花や、その季節に美しく咲くお花を飾ることで、より心のこもった供養となるでしょう。
初めて迎える場合:新盆(初盆)と初彼岸の格式の違い

大切な方が亡くなられて四十九日を過ぎ、初めて迎えるお盆やお彼岸は、ご遺族にとって特別な意味を持つことでしょう。この二つの行事の迎え方には、少し違いがあるようです。
新盆(初盆):故人が初めて帰ってくる特別な年
故人が亡くなられてから初めてのお盆は、「新盆(にいぼん)」または「初盆(はつぼん)」と呼ばれ、特に大切に営む習わしがあります。
これは、故人の霊が初めてご自宅へ帰ってこられる、一度きりの機会と考えられているためです。そのため、通常のお盆よりも手厚く、丁寧にお迎えの準備をします。ご親族や、故人と特に親しかった方々をお招きして、僧侶に読経をお願いする法要を営むことも多いようです。
新盆の際には、目印として「白紋天(しろもんてん)」と呼ばれる、白い無地の提灯を玄関や軒先に飾る風習があります。清浄無垢な白で、故人の霊を丁寧にお迎えするという、美しい意味が込められています。
初彼岸:静かに迎えることが一般的
一方、四十九日後に初めて迎えるお彼岸は「初彼岸(はつひがん)」と呼ばれますが、新盆ほど盛大に何かを行うことは少ないようです。
特別な飾り付けや大規模な法要というよりは、通常のお彼岸と同じように、ご家族でお墓参りをし、仏壇に手を合わせるなどして、静かに故人を偲ぶ時間を大切にするのが一般的とされています。
お彼岸のお墓参りについて、服装やマナーなどこちらの記事でご紹介していますのでご興味のある方はご覧ください。
>【2025年秋】お彼岸はいつ?お墓参りの日程・服装・マナー解説
知っておきたい作法:お布施やお供え物のマナー

お盆やお彼岸の時期には、法要に参列したり、お供え物を持参したりする機会も増えるかもしれません。いざという時に戸惑うことのないよう、基本的なマナーについて触れておきましょう。
法要のお布施の相場と渡し方
法要の際にお渡しするお布施は、読経などへの対価ではなく、ご本尊様へお供えする感謝の気持ちを表すものです。そのため決まった金額はありませんが、一つの目安として参考にされるとよいでしょう。
例えば、お彼岸のお寺での合同法要では3千円から1万円、お盆にご自宅へ僧侶をお招きする棚経では5千円から2万円、新盆の法要では3万円から5万円ほどを包まれる方が多いようです。
お布施は、白無地の封筒か、奉書紙(ほうしょし)と呼ばれる和紙に包みます。表書きは「御布施」とし、袱紗(ふくさ)という布に包んで持参するのが丁寧な作法です。
お供え物を贈る際の「のし(掛け紙)」の書き方
ご自宅以外へお供え物を持参する際は、掛け紙(のし紙)をかけます。その際の表書きには、いくつかの使い分けがあります。
お盆・お彼岸ともに、一般的には「御供」や「御仏前」と書きます。
ただし、故人が亡くなられて四十九日を迎える前にお供えする場合は、「御霊前」とするのが通例です。これは、四十九日をもって故人の霊が仏様になると考えられているためです。
また、新盆を迎えるお宅へお供えを持参する場合は、「新盆御見舞」と書くと、より丁寧な気持ちが伝わるでしょう。
お盆とお彼岸に関するよくある質問

ここまでお盆とお彼岸の違いについて解説してまいりましたが、他にも気になる点があるかもしれません。読者の皆様からよくいただくご質問に、Q&A形式でお答えします。
Q1.お盆やお彼岸の時期に、やってはいけないことはありますか?
A.「これをすると罰が当たる」というような、厳密なタブーは特にないとされています。
ただし、どちらもご先祖様を供養し、静かにご自身を振り返る期間です。そのため、結婚式や新築祝いといった華やかなお祝い事は、この時期を避けるのが望ましいと考える方もいらっしゃいます。大切なのは、ご先祖様を敬う気持ちと、周囲の方々への配慮といえるでしょう。
Q2.お彼岸の時期に結婚式などのお祝い事をしても大丈夫ですか?
A.法的・宗教的に禁止されているわけではありませんが、お彼岸やお盆はご先祖様を供養し、静かに過ごす期間とされています。年配の親族などが気にされる場合もあるため、周囲への配慮が必要です。挙式や披露宴を避け、日程調整や伝え方を工夫することが望ましいでしょう。
Q3.お盆とお彼岸、どちらがより重要な行事ですか?
A.どちらの行事がより重要で、どちらが軽いということはありません。どちらも、ご先祖様や故人を偲ぶための、かけがえのない大切な期間です。
ご先祖様を「お迎え」することに重きを置くお盆。私たちがご先祖様に「会いに行く」ことを大切にするお彼岸。それぞれの意味を理解し、どちらの行事も大切に受け継いでいくことが、何よりも素晴らしい供養となるのではないでしょうか。
Q4.浄土真宗では、お盆やお彼岸の考え方が違うのですか?
A.はい、浄土真宗では、お盆やお彼岸の捉え方が他の宗派と少し異なります。
浄土真宗の教えでは、亡くなった方はすぐに阿弥陀如来のお力によってお浄土に往生し、仏様になると考えます。そのため、ご先祖様の霊がこの世に「帰ってくる」という考え方はいたしません。
ですから、お盆やお彼岸は、亡き人を偲ぶことをご縁として、私たち自身が阿弥陀如来の教えに改めて耳を傾ける「仏法聴聞(ぶっぽうちょうもん)」の機会と捉えます。お浄土である「彼岸」に思いを馳せ、仏様の教えに感謝する大切な期間なのです。
Q5.遠方にお墓があり、お参りに行けない場合はどうすればいいですか?
A.直接お墓に行けなくても、心を込めて仏壇に手を合わせたり、故人を思い出しながらお花やお供えをすることで、十分な供養になります。最近では、遠方のご先祖様のお墓を代わりに清掃・お参りしてくれる「墓参り代行サービス」などもあります。
Q6.忙しくて仏壇やお墓の掃除ができません。最低限やるべきことはありますか?
A.時間がない中でも、仏壇の前で静かに手を合わせたり、お線香をあげたりするだけでも立派な供養になります。仏壇の掃除も、埃を払い、新しいお花やお供え物を用意するだけでも心を込めた行動になります。大切なのは、気持ちを向けることです。
Q7.お供え物は何を選べば良いですか? 迷ったときの定番は?
A.季節の果物や故人の好物が定番です。迷った場合は「日持ちのするお菓子」「個包装のもの」「砂糖の控えめな和菓子」などが喜ばれます。表書きは「御供」「御仏前」が基本で、のし紙の種類や包装にも気を配ると丁寧です。
證大寺のお盆とお彼岸について

證大寺でのご相談風景
お盆やお彼岸を大切にしたいと思っても、いざ準備を進めようとすると、ご家庭の事情や地域の慣習の違いなどから、迷われたり、不安に思われたりすることもあるかもしれません。
「うちは浄土真宗だけれど、お盆の迎え方はどうすればいいのだろう」
「初めての新盆で、何から手をつければよいか分からない」
「お墓が遠方にあって、なかなかお参りに行けない」
私たち證大寺(しょうだいじ)は、そうした皆様一人ひとりの心に寄り添い、ご供養に関するさまざまなご相談をお受けしております。
これまで受け継がれてきた大切な伝統を尊重しながらも、現代の暮らしやご家族の形に合わせた、心安らぐご供養のあり方を一緒に考えさせていただきます。
浄土真宗 證大寺のお盆
「浄土真宗では人は亡くなると極楽浄土に行くという教えです。」と住職はいいます。「とはいえお盆の行事は、宗派を超えて地域色が濃いという特徴があります。たとえば青森のねぶたや沖縄のエイサーなども、お盆に先祖を供養することから始まっているようです。浄土真宗は、これらを否定するわけではありません。地域の風習を尊重しながらも、お盆は『仏様に感謝する日』と捉えています。」また住職は「浄土真宗のお盆について聞きたいことがあれば、お気軽にお尋ねください」とのこと。證大寺では浄土真宗での通夜や葬儀、法要などが行えるほか、仏教講座なども開催しています。お盆にかぎらず相談があれば、話を聞いてみるとよいでしょう。
證大寺の彼岸会法要

證大寺運営の「船橋昭和浄苑」では夜のお参りも行っております
彼岸会(ひがんえ)とは、春分・秋分を中心としたお彼岸の一週間に営まれる仏教行事です。先祖供養にとどまらず、仏さまの教えを聴き、自分自身の生き方を見つめ直す大切な機会とされています。法要では読経の後に法話があり、仏教の教えを日常生活にどう生かすかを考えるきっかけとなります。證大寺では埼玉県と千葉県で「森林公園昭和浄苑」「船橋昭和浄苑」という2つの霊園を直接運営しています。2つの昭和浄苑にも立派な本堂があり、こちらでも彼岸会法要を開催。お墓参りに来て彼岸会に参加する方がたくさんおられます。
また、「船橋昭和浄苑」では夜のお参りも行っております。日中はご都合が悪くお参りに行けない方でも、夜間にご参拝いただけます。参道はランタンで優しく灯されておりますので、夜間でも安心してお参りすることができます。
<このようなご相談をお受けしております>
◯お盆やお彼岸の詳しい過ごし方、法要について
◯永代供養や納骨、お墓について
◯お墓の承継者がいない、墓じまいを考えている
◯ご葬儀や年忌法要について
◯その他、仏事に関するあらゆるお悩み
證大寺は浄土真宗のお寺ではございますが、宗旨・宗派を問わず、どなた様からのご相談も広くお受けしております。
どうぞ一人で抱え込まず、まずはお気軽に心の内をお聞かせください。皆様が心穏やかに、大切な方をご供養する時間をお過ごしになれますよう、お手伝いさせていただきます。
ご相談やご見学をご希望の方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
證大寺について:https://shoudaiji.or.jp/
證大寺へのお問合せ:https://shoudaiji.or.jp/contact/
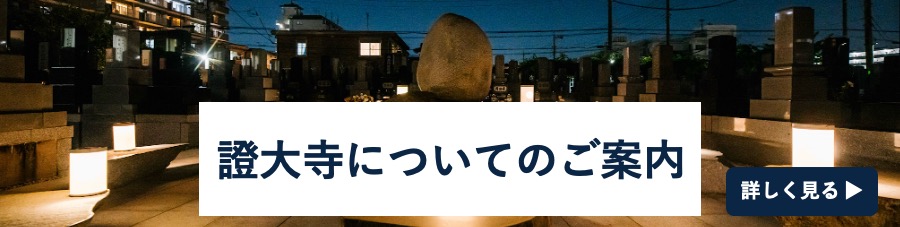
まとめ:違いを理解し、ご先祖様を敬う心を大切に
ここまで、お盆とお彼岸について、その意味や由来、過ごし方の違いなどを詳しく見てまいりました。
最後に、二つの行事の主な違いを振り返ってみましょう。
| お盆 | お彼岸 | |
| 目的 | ご先祖様を自宅にお迎えし、おもてなし(供養)をする | ご先祖様のいる彼岸に思いを馳せ、私たちが会いに行く |
| 時期 | 夏の年1回 (7月または8月) | 春と秋の年2回 (春分・秋分の日を中心とした7日間) |
| 由来 | インドの仏教説話「盂蘭盆会」 | 日本古来の自然信仰と仏教思想の融合 |
| 特徴的なこと | 盆棚や精霊馬、迎え火など、お迎えの準備 | お墓参りを中心に、六波羅蜜という仏道修行を実践する |
このように整理すると、お盆とお彼岸は全く異なる背景を持つ行事であることが、改めてお分かりいただけたかと存じます。
しかし、その形や風習は違っていても、私たちの根底に流れる想いは、きっと同じなのではないでしょうか。
今は亡き大切な方を静かに想い、命を繋いでくださったご先祖様への感謝の気持ちを捧げる。その温かい心こそが、時代を超えて受け継がれてきた、日本の美しい文化なのだと感じます。
この記事が、皆様にとって次のお盆、そしてお彼岸を、より心豊かに過ごすための一助となれば幸いです。
忙しい日々の中で、ふと立ち止まり、遠い昔に思いを馳せる。そんな穏やかな時間が、私たちの毎日をやさしく照らしてくれるかもしれません。