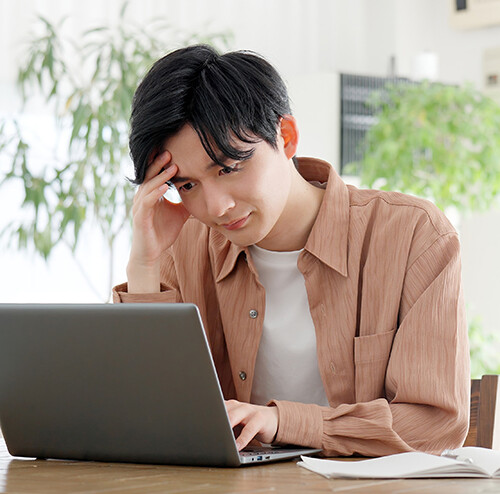永代使用料とは?相場・管理費や永代供養料との違いを解説

永代使用料とは、お墓の土地を永代に使う権利を得るための費用です。本記事では全国相場や地域別の違い、年間管理料・永代供養料との違い、費用を抑えるポイントまでわかりやすく解説します。
目次
●永代使用料とは?お墓の土地を「永代に使う権利」の費用
●永代使用料の相場と価格が決まる要因
●永代使用料・年間管理料・永代供養料の違いを一覧でわかりやすく解説
●永代使用料に関するQ&A【よくある疑問を解決】
●永代使用料を賢く抑える3つのポイント
●證大寺の多彩な永代供養
●まとめ:永代使用料を正しく理解し、納得のいくお墓選びを
永代使用料とは?お墓の土地を「永代に使う権利」の費用

お墓について考えはじめると、「永代使用料(えいたいしようりょう)」という言葉を初めて目にされる方も多いかもしれません。大切な方を偲ぶ場所を選ぶ上で、とても重要な費用となりますが、一体どのようなものなのでしょうか。
永代使用料とは、お墓を建てるための土地(墓所区画)を、永代にわたって使用する権利を得るために支払う費用のことです。この費用を寺院や霊園にお納めすることで、「永代使用承諾書」といった証書が発行され、その場所にお墓を建て、故人をご供養していくことが認められます。いわば、その場所をお墓として永代にわたりお守りしていくための、最初の大切な費用といえるかもしれません。
土地の「所有権」とは違う!永代使用料は墓地を売ったり貸したりできない
ここで少し注意しておきたいのが、永代使用料を支払うことで得られるのは、あくまでその土地を「お墓として使用する権利」であるという点です。
例えば、私たちが家を建てるために土地を購入する場合、その土地の「所有権」を得ることになります。所有権があれば、その土地を売ったり、誰かに貸したりすることも可能です。
しかし、お墓の土地の場合は少し考え方が異なります。得られるのは使用権ですので、不動産のように第三者の方へ売却したり、お墓以外の目的で利用したりすることはできないとされています。もし将来、お墓を維持することが難しくなった場合には、墓石を撤去して更地にし、その使用権を寺院や霊園にお返しするのが一般的です。これは、墓地全体がご先祖様を敬い、静かに故人を偲ぶための神聖な場所であり続けるために、大切な決まりごととされています。
永代使用料の成り立ちと檀家制度の関係
では、なぜこのような「永代使用料」という仕組みがあるのでしょうか。
その起源は、江戸時代に行われた寺請制度(てらうけせいど)や、それによって確立された檀家制度(だんかせいど)にまでさかのぼるといわれています。
檀家制度とは、特定の寺院に所属し、お葬式やご法事など、ご先祖様の供養一切をそのお寺にお任せするという仕組みです。人々がお寺を経済的に支え、その代わりにお寺は檀家の方々のお墓を守り、永代にわたって供養を続けていく。この相互の信頼関係の中で、お墓の場所を確保し、維持していくための費用として永代使用料の考え方が生まれたとされています。
時代は変わり、今では檀家にならなくても利用できる民営霊園なども増えましたが、その根底にある「大切な方を偲ぶ場所を、永代にわたって清らかに維持・管理していく」という心は変わりません。永代使用料は、そのための大切な費用なのです。
永代使用料の相場と価格が決まる要因

永代使用料がどのようなものか少しずつ見えてくると、次に気になるのは、やはり具体的な費用についてではないでしょうか。大切な方を偲ぶ場所を選ぶ上で、費用の目安を知っておくことは、心の準備にもつながります。
ここでは、永代使用料の全国的な費用相場と、その価格がどのような理由で決まってくるのかを、一つひとつ丁寧に見ていきたいと思います。費用はあくまで一つの目安ですが、どうぞご参考にしてみてください。
【全国・地域別】永代使用料の平均相場一覧
全国的な永代使用料の平均相場は、60万円~80万円ほどといわれています。しかしこれはあくまで平均であり、地域によって大きな差が見られるのが実情です。都市部の土地の価格が高いように、永代使用料も都心に近いほど高くなり、郊外や地方へ行くほど落ち着く傾向にあります。
例えば、関東圏内では、東京都心部が最も高くなる傾向にあり、神奈川県、千葉県、埼玉県と、都心からの距離に応じて費用も変わってくることが多いといわれています。東京都内(例:江戸川区周辺)と、埼玉県東松山市や千葉県船橋市周辺では、前提となる永代使用料が異なるかもしれません。お墓を建てる地域の相場をあらかじめ調べておくと安心です。
永代使用料が変動する4つの要因
地域による違いのほかに、永代使用料の価格はいくつかの要因によって変わります。主なものとして、以下の4つのポイントが挙げられます。
1.立地条件
駅から近い、バス停が目の前にあるなど、交通の便が良くお参りしやすい場所は、やはり人気が高く、永代使用料も高くなる傾向にあるようです。ご家族やご親戚がお参りに来られる際のことも考えながら、検討したいポイントです。
2.区画の広さ
当然のことながら、お墓を建てる区画の面積が広くなれば、その分、永代使用料も高くなるのが一般的です。どのくらいの広さが必要か、どのようなお墓を建てたいかによって、選ぶ区画も変わってきます。
3.霊園の種類
お墓を建てる場所には、都道府県や市町村が運営する「公営霊園」、宗教法人や公益法人が運営する「民営霊園」、そしてお寺の境内にある「寺院墓地」があります。一般的に、公営霊園は費用が比較的抑えられていることが多いですが、申し込みに居住地などの条件があったり、募集が抽選になったりする場合もあります。
4.施設の設備
参道がきれいに整備されている、駐車場が広い、休憩所や法要施設が充実しているといった霊園は、それだけ管理が行き届いており、利便性も高いといえます。こうした施設の維持管理も永代使用料に含まれるため、設備が充実しているほど価格も高くなることがあります。
永代使用料・年間管理料・永代供養料の違いを一覧でわかりやすく解説

永代使用料について見てきましたが、お墓の費用には、ほかにも似たような名前のものがあり、少し戸惑われるかもしれません。特に「年間管理料」と「永代供養料」は、永代使用料としばしば混同されやすい費用といわれています。
しかし、この3つはそれぞれ全く異なる意味合いを持っています。まずは下の表で、それぞれの役割の違いを比べてみましょう。一つひとつの言葉の意味をゆっくりと紐解いていくことで、お墓にかかる費用全体の姿が、よりはっきりと見えてくるかもしれません。
| 費用項目 | 目的・内容 | 支払いのタイミング | 費用の目安(相場) |
|---|---|---|---|
| 永代使用料 | お墓を建てる土地(区画)を永代にわたって使用する権利を得るための費用。 | 契約時に一度だけ | 約20万円~200万円 |
| 年間管理料 | 霊園の共有スペース(参道、水道施設、緑地など)を維持・管理するための費用。 | 毎年(年に一度など) | 公営:数千円~ 民営:約5千円~2万円 |
| 永代供養料 | お墓の承継者がいない等の場合に、寺院や霊園に永代の管理と供養を任せるための費用。 | 契約時に一度だけ | 約10万円~150万円 |
上の表の通り、この3つの費用は、目的も支払う時期も大きく異なります。
永代使用料が、いわば「場所を確保するための初期費用」であるのに対し、年間管理料は、その場所を皆で気持ちよく使い続けるための「維持費」のようなもの、と考えると分かりやすいかもしれません。霊園の美しい景観や、清潔な施設が保たれているのは、この管理料によって支えられているのです。
そして永代供養料は、また少し意味合いが異なります。これは、将来お墓を継ぐ方がいらっしゃらないなど、お墓の管理や供養に関する不安に応えるための費用といえるでしょう。この費用をお納めすることで、ご自身に代わって寺院や霊園が永代にわたり故人のご供養を続けてくださいます。
それぞれの費用の意味を正しく理解しておくことは、ご自身とご家族にとって、心から安心できる場所を見つけるための大切な一歩となります。
一般的なお墓と違う「永代供養墓」について、より詳しくお知りになりたい方は、こちらの記事もご覧ください。
>永代供養墓とは?お墓の種類・費用相場など基本からわかりやすく解説!
永代使用料に関するQ&A【よくある疑問を解決】

お墓の費用について理解が深まってくると、今度はより具体的な事柄について、さまざまな疑問が浮かんでくるかもしれません。それは、ご自身やご家族にとって大切な場所を、真剣に考えていらっしゃるからこそだと思います。
ここでは、永代使用料に関してよく寄せられるご質問をいくつか取り上げ、一つひとつお答えしていきます。心の中の気がかりが、少しでも軽くなる一助となれば幸いです。
Q.一度払えば終わり?追加費用はかからない?
永代使用料は、前の章で触れたように、基本的にお墓を契約する際に一度だけお納めする費用です。そのため、毎年支払う必要はございません。
ただし、お墓を維持していくためには、多くの場合「年間管理料」が別途必要となります。これは、参道や水道設備、緑地といった霊園全体の共有スペースを、きれいで穏やかな状態に保つために使われる費用です。
したがいまして、「一度支払えば全く追加費用がかからない」というわけではなく、永代使用料とは別に、年間管理料を毎年お支払いしていくことになるのが一般的です。
Q.継承者がいない場合はどうなるの?
お墓は、親から子へ、子から孫へと代々受け継がれていくことを前提として考えられてきました。お墓を継ぐ方(承継者)が、年間管理料の支払いやお墓の掃除などを行い、ご先祖様のご供養を続けていく、という形です。
もし、お墓を継ぐ方がいらっしゃらなくなると、年間管理料の支払いが滞ってしまうことがあります。そのような状態が続きますと、定められた手続きと期間を経て、お墓を使用する権利が失われ、最終的にはお墓が整理(無縁仏として合祀)されてしまう可能性もございます。
こうした将来への不安から、近年では承継者を必要としない「永代供養」という形を選ばれる方も増えています。
Q.墓じまいをしたら永代使用料は返還される?
さまざまなご事情から、すでにあるお墓を片付けて、更地にして使用権を霊園にお返しすることを「墓じまい」といいます。
この墓じまいをされた際に、「最初に支払った永代使用料は戻ってくるのでしょうか?」というご質問をいただくことがあります。結論から申しますと、一度お納めした永代使用料は、原則として返還されないのが一般的です。
永代使用料は、土地の購入代金や保証金とは異なり、あくまで「永代にわたってお墓としてその場所を使用する権利」に対して支払われた費用です。そのため、契約の際に取り交わした規約にも、返還されない旨が記されていることがほとんどかと思われます。
Q.支払い方法やマナーは?
永代使用料の支払い方法は、霊園や寺院によって異なりますが、多くは契約時に現金で支払うか、指定された口座へ一括で振り込む形がとられています。霊園によっては分割払いに応じてくださる場合もあるようですので、契約前によく確認されるとよいでしょう。
もし、寺院などに直接お持ちになる場合には、特別な決まりはありませんが、白い無地の封筒にお金を入れるのが丁寧な方法とされています。表書きには「永代使用料」と書き、その下に契約者のお名前をフルネームで記します。お金をお渡しすることに変わりはありませんが、ご先祖様を敬う心や、これからお世話になる寺院への感謝の気持ちを形に表す、という視点も大切かもしれません。
永代使用料を賢く抑える3つのポイント

故人を偲ぶ気持ちに、費用の大小は関係ありません。とはいえ、ご自身のこれからの暮らしや、ご家族のことを考えたとき、少しでも負担を抑えたいと考えるのは、ごく自然なことだと思います。永代使用料は、いくつかの点を少し違った視点から見てみることで、費用を抑えることができるといわれています。ここでは、そのための3つのポイントを、心静かに見ていきましょう。
①公営霊園や郊外を検討する
一つ目は、お墓を建てる「場所」について考えてみることです。
前の章で、永代使用料は地域によって大きく異なるとお伝えしました。都道府県や市町村が運営する公営霊園は、民営の霊園に比べて永代使用料が比較的安価なことが多いようです。ただし、例えば東京都江戸川区が運営する霊園であれば区民であることなど、申し込みに条件が設けられていたり、希望者が多く抽選になったりする場合もあります。
また、都心から少し離れた郊外の霊園に目を向けてみるのも、一つの方法です。少し足を延ばすことで、より静かで自然豊かな環境にありながら、費用を抑えた場所が見つかるかもしれません。
②小さめの区画を選ぶ
二つ目は、お墓を建てる「広さ」を見直してみることです。
永代使用料は、区画の面積に比例して高くなるのが一般的です。近年では、お墓のあり方も多様化しており、代々受け継ぐ大きなお墓ではなく、ご夫婦だけ、あるいはご自身だけが入るような、こぢんまりとしたお墓を選ばれる方も増えています。
何よりも大切なのは、広さや大きさではなく、故人を静かに偲び、心が安らぐ場所であるかどうかです。ご自身やご家族にとって、本当に心地よいと感じられる広さを考えてみるのもよいでしょう。
③一般墓以外の選択肢も検討する
三つ目は、お墓の「形」そのものについて、視野を広げてみることです。
今日では、墓石を建てる伝統的なお墓(一般墓)だけでなく、さまざまな供養の形が生まれています。例えば、墓石の代わりに樹木を墓標とする「樹木葬」や、屋内の施設にご遺骨を安置する「納骨堂」といった選択肢です。これらの新しい形のお墓は、一般墓ほど広い土地を必要としないため、永代使用料を大きく抑えることができます。また、お墓の管理をご自身で行う必要がない「永代供養」が付いていることが多く、将来の承継者に不安がある方にも、安心な選択肢として広がっています。
證大寺の多彩な永代供養墓

證大寺(森林公園昭和浄苑)の永代供養墓
ここまで、永代使用料や、お墓にまつわる様々な選択肢についてお話ししてきました。多くの情報を前に、ご自身の、そしてご家族にとって、どのような形が一番良いのだろうかと、静かに思いを巡らせていらっしゃるかもしれません。
「費用や承継者のことで、子どもたちに負担はかけたくない」「自分らしい、穏やかな眠りの場所を見つけたい」。そうした現代の切実な想いに寄り添い、具体的な形として応えるのが、私たち證大寺がご提案する永代供養です。
これまでの記事で触れてきた、お墓に関する不安を解消するための選択肢が、ここにはあります。
永代供養墓は管理料不要で安心
例えば、證大寺の永代供養墓は、一度ご契約いただければ、この記事で解説した「年間管理料」は一切かかりません。最初に費用をお納めいただくだけで、その後のご負担なく、證大寺が永代にわたって故人様のご供養を続けてまいります。また、お墓を継ぐ方がいらっしゃらない場合でも、何一つ心配はいりません。ご縁をいただいたすべての方を、お寺が責任をもってお見守りします。
證大寺がご提案する多彩な供養のかたち
美しい花と緑に囲まれて自然に還る「樹木葬」。天候を気にせず、いつでも静かにお参りできる屋内型の「納骨堂」。そして、ご夫婦で、またご家族で入れる様々なタイプのお墓をご用意し、お一人おひとりの心に寄り添ったご供養の形をお選びいただけます。
お墓選びは、ご自身の人生を見つめ、大切な方への想いを確かめる、かけがえのない時間です。もし、具体的なことでお悩みでしたら、どうぞお気軽に證大寺へご相談ください。専門のスタッフが、あなたの心に静かに耳を傾け、最も安らげる選択を見つけるお手伝いをいたします。
まずは一度、現地の空気を感じに、見学に訪れてみてはいかがでしょうか。
證大寺(江戸川区):https://edogawa2.eitaikuyou.life/
森林公園 昭和浄苑(埼玉県東松山市):https://higashimatsuyama2.eitaikuyou.life/
船橋 昭和浄苑(千葉県船橋市):https://funabashi2.eitaikuyou.life/
まとめ:永代使用料を正しく理解し、納得のいくお墓選びを
この記事では、「永代使用料」という言葉を入り口に、お墓にまつわる様々な費用とその意味について、一つひとつ触れてまいりました。
はじめは少し複雑に感じられたかもしれませんが、永代使用料、年間管理料、そして永代供養料という、それぞれの費用の役割を理解することで、ご自身がどのような供養の形を望んでいらっしゃるのか、その輪郭がよりはっきりと見えてきたのではないでしょうか。
費用や制度を正しく知ることは、未来への不安を和らげ、心から納得できる選択をするための、大切な道のりの一つです。何よりも重要なのは、故人を偲ぶ気持ちが安らぐ場所であり、ご自身やご家族が穏やかな心でお参りできることでございます。
人生の中で、時に立ち止まり、大切なことに思いを巡らせる時間があります。この記事が、あなたの心の内に灯る、小さな明かりとなれば幸いです。