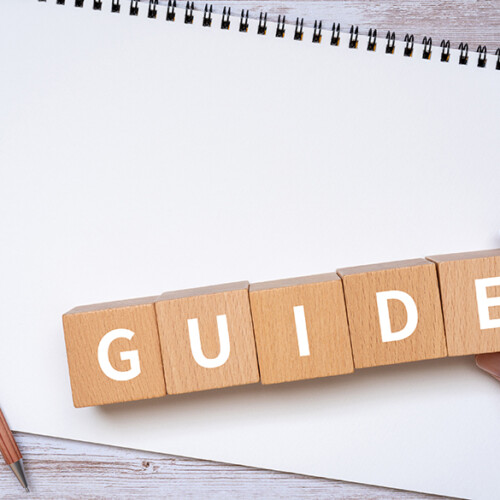墓じまいの手続きは何をすればいい?具体的な手順から費用まで分かりやすく解説!

お墓の継承を選ばない、郷里から離れて暮らすことでお墓を管理できないなどの理由から、墓地の改葬(墓じまい)は増加傾向にあります。
多くの場合、墓じまいは郷里のお寺(菩提寺など)からになりますが、勝手に墓じまいを進めるとトラブルに発展する場合があります。そこで「先々のことも考えて、自分たちの代で墓じまいをしたい」という方に向けて、失敗しないためのポイントなどを提示します。
目次
●墓じまいとは
●墓じまいの流れ|9つの手順とやること
●墓じまいの手続きに必要な書類
●墓じまいにかかる費用の目安
●墓じまいの際に押さえておくべき2つの注意点
●證大寺|墓じまいによる改葬受入が可能
●まとめ
墓じまいとは

墓じまいは、これまでのお墓を撤去・処分するだけではありません。遺骨を取り出して改葬し、「別の形で供養する」ことも墓じまいの中に含まれています。供養する場所を新しく整え、後継者がなくても永代供養などでずっと供養が続けられます。お墓を無縁仏にしないためにも大切なものです。
墓じまいのメリット
墓じまいすることにより、維持や管理の負担がなくなり、住んでいる近くに改葬すればお墓参りの負担も軽減できます。永代供養すればお墓の継承に関する心配もなくなります。
墓じまいのデメリット
お墓の撤去には費用がかかり、新たな改葬先を見つける手間や費用も必要です。また家族や親族に了承をとらないで強行すると、トラブルになる可能性もあります。
墓じまいをしないとどうなる?
墓じまいをしないまま放置すると、そのお墓は草木が生い茂って荒れ果て、周囲のお墓にも迷惑をかけることに。連絡がつかないと判断されたお墓は、最終的には行政や管理者によって撤去されてしまいます。
墓じまいの流れ|9つの手順とやること

墓じまいは、お墓を撤去・処分するだけでは足りません。手続きなどやるべきことが多く、事前準備が必要です。まずは墓じまいから改葬までの流れについて、順を追って説明します。
1.現在のお墓の状況を把握する
まずはお墓の中に納められた遺骨が誰のものか確認し、遺骨の数や骨壺の大きさ、埋葬してからの年数など、現在のお墓の状況を把握しましょう。移転して改葬する際には、遺骨の数だけ改葬許可証が必要になります。
2.家族・親族に了承を得る
墓じまいをしたいと思っていても、家族や親族の中には「今まで通りにしてほしい」と考える方もいるでしょう。親族や家族の反対を押し切って墓じまいを進めると、後にトラブルになったり関係が悪化するおそれがあります。
墓じまいを進めるにあたっては、「なぜ墓じまいをしたいのか」「その後はどうするのか」をよく説明して家族や親族の了承を得るようにしましょう。また決定した内容を、後々トラブルを回避するために覚書を作ったというお話しもあります。
3.墓地の管理者・お寺に相談する
家族や親族の了承が得られたら、お墓のある墓地の管理者や寺院に意思を伝えます。
公営・民営霊園の場合は、管理事務所に墓じまいをしたい旨を伝えます。
お寺にお墓がある場合は、いきなり伝えるのではなく「お寺に相談する」という形をとることをおすすめします。お寺にとっては「墓じまいをする=檀家をやめる」ことになり、お寺側が態度を硬化させてしまうことも。なぜ墓じまいを考えるに至ったかを伝えながら相談し、お墓の維持が難しいことなどを丁寧に説明して理解を得ましょう。
4.改葬先を決める
次に、墓じまいをした後の遺骨をどこに改葬するかを検討しましょう。
墓じまいの理由が「お墓が遠い」ということであれば、近くで新たにお墓を購入してもよいでしょう。後継者がいないなら、寺院や霊園が後々まで供養してくれる永代供養墓を探します。また費用を抑えたいなら、合祀墓という選択もあります。そのほか樹木葬や納骨堂など改葬先はいろいろな種類があるので、比較しながら検討していきましょう。
5.墓石の解体工事を行う石材店を決める

お墓を更地に戻す解体工事は、石材店に依頼します。
寺院や民営の霊園では石材店が決まっている場合があります。指定された石材店があるのに別の業者に依頼すると、敷地に入れてもらえないなどのトラブルが起こることも。また公営の霊園では指定石材店はなく、どこにでも依頼できます。しかし、遠方の業者に依頼すると交通費や墓石の運搬費が上乗せされることもあります。見積もりを取って、納得できる価格かどうか確認しましょう。
6.役所で墓じまいの行政手続きを行う
墓じまい・改葬には、法律で定められた手続きを取る必要があります。墓じまいするお墓がある自治体が窓口となるので、まず「改葬許可証」を交付してもらい、「改葬許可申請書」や必要書類を提出するなどの行政手続きを行います。
詳しい内容は、以下の項目をご覧ください。
7.改葬法要を行う
改葬法要とは、墓じまいをするにあたっての儀式です。宗派や地域によっては「閉眼法要」や「魂抜き」などと呼ばれることもある儀式で、故人の魂が宿るお墓から魂を抜くと考えられ、この儀式を行うことでお墓はただのモノに戻るとされています(宗派によって異なります)。
■改葬法要の流れ
家族・親族やお寺と相談して改葬法要の日時を決め、当日は墓じまいするお墓に集まります。僧侶の読経の後、お墓から遺骨を取り出し、場所を移して参列者で会食を行います。
8.墓石を解体し、墓地を撤去する
石材店に墓石の解体工事を依頼し、更地にした後、墓所に返還します。
墓石の解体は改葬法要の1週間後くらいに済ませる場合が多いです。また遺骨の取り出しは石材店に依頼することが多いので、改葬法要ではなく解体工事の際に取り出してもらう場合もあります。
9.次の改葬先に遺骨を納骨する
遺骨を新しい改葬先に納骨します。これで墓じまいと改葬が終了となります。このときに改葬先の管理者に「改葬許可証」を提出します。
墓じまいの手続きに必要な書類

墓じまい・改葬する場合には、法律で定められた手続きを踏む必要があります。墓じまいから改葬までの行政手続きや必要な書類について説明します。
改葬許可申請書を入手する
墓じまいする現在のお墓がある自治体から改葬許可申請書を入手します。
改葬許可申請書は、改葬許可証の交付を申請するための書類です。現地の役所の窓口のほか、自治体のホームページからも入手できます。書式は自治体によって異なり、1つの遺骨につき申請書が1枚必要な場合と、複数の遺骨を1枚でまとめて申請できる場合があります。
埋葬証明書を現在の墓地の管理者に発行してもらう
埋葬証明書は、現在の墓地に誰が埋葬されているのかを証明する書類です。現在の墓地が民営霊園や公営墓地なら管理事務所、寺院ならお寺が発行してくれます。
自治体によっては、改葬許可申請書と埋葬許可証が兼用になっている場合もあり、その場合は改葬許可申請書に署名捺印してもらうことになります。該当する自治体のホームページで確認しましょう。
新しい改葬先から受け入れ証明書をもらう
受入証明書は、遺骨を受け入れることを証明する書類です。改葬先が決まったら、契約時に新しいお墓の管理者から発行されます。
必要な書類を役所に提出する
改葬許可申請書、埋葬証明書、受入証明書がそろったら、身分証明書のコピーをつけて役所に提出します。また遠方の場合は郵送での受付も行われています。
改葬許可証が発行される
書類が受理されると、自治体から改葬許可証が発行されます。これが発行されてはじめて、お墓から遺骨を移動させることができるようになります。書類を提出してから発行まで時間がかかることもあるので、余裕をもって提出しましょう。
また改葬許可証は、改葬先で納骨する際にも必要となります。
墓じまいにかかる費用の目安

墓じまいにかかる費用の相場は30万円〜300万円程度と大きく振り幅があります。お墓の大きさや遺骨がどれだけ入っているか、改葬先をどうするかによって異なってくるためです。
お墓の撤去に関する費用
お墓の撤去で必要な費用は、墓石の解体・撤去料はもちろんのこと、ほかにも費用が発生します。改葬(魂抜き法要とも)の費用、遺骨を取り出す出骨作業料のほか、離檀料がかかる場合もあります。
■墓石の撤去料/出骨作業料
撤去費用はお墓の大きさや墓石の量、重機が使えるか否か、作業人数・日数などによって変わりますが、平均的には1㎡あたり10万円〜15万円程度といわれています。
また遺骨の取り出しを石材店に依頼した作業料は、遺骨1つにつき1~5万円程度が相場となります。
■閉眼法要の費用
改葬法要のお布施は2~5万円程度が相場で、お寺から墓地まで離れている場合はお車代として5,000~1万円程度を別途お包みします。
また法要後に会食の席を設ける場合は、1人3,000~5,000円程度の食事代が一般的です。
このほかお墓にお供えするお花、果物、菓子といったお供物をご用意します。
■離檀料
墓じまいで檀家を離れる際、離檀料を支払います。離檀料には法的な根拠はなくあくまで慣習で、寺院によっては「離檀料をいただかない」こともあれば、高額な離檀料を請求されトラブルに発展するケースもあります。
トラブルを避けるためについては、下記をご参照ください。
行政手続きでかかる費用
埋葬証明書や改葬許可申請・許可証の発行など、行政手続きでの費用は自治体によって異なります。しかし無料~1,000円超程度と少額な場合がほとんどです。
改葬先でかかる費用
墓じまいの後の改葬先でかかる費用は、改葬先の種類によって異なります。
永代供養墓で合祀する場合は5~30万円、樹木葬だと20~80万円、納骨堂は40~100万円程度が相場とされています。新しくお墓を建てる場合は、墓地の永代使用料と墓石価格で全国平均が200万円超となっています。
このほかに改葬先で、開眼法要の費用などが加わる場合があります。
費用が心配な場合は
墓じまいは、高額な費用が発生することもあります。費用が心配なら、次のような対応策を考えてみてはいかがでしょう。
■家族や親族に協力してもらう
費用はお墓の承継者が負担することが多いものの、決まりごとではありません。実際、兄弟など家族・親族が費用を出し合って負担する場合も多くあります。
■自治体の補助を利用する
一部の自治体ではあるものの、墓じまいの補助金制度を設けているところがあります。適用条件等もありますので、まずは自治体に確認してみましょう。
■メモリアルローンを利用する
メモリアルローンとは、お墓や葬儀に関する費用のローンで、銀行などで用意されています。審査に通ればお墓じまいでもローンが適用されます。
墓じまいの際に押さえておくべき2つの注意点

墓じまいでは、寺院とトラブルになるケースがあります。また家族・親族間でのトラブルも起こりがちです。それらを避けるためにできる方法をご紹介します。
離檀料を今までの墓地にお支払いする
前述した通り、離檀料の支払は慣習で法的な根拠はありません。
しかし実際に墓じまいをしてお墓の中の遺骨を移すには、改葬許可申請書への署名や押印、埋蔵証明書の発行など、お寺に協力してもらう手続きがいろいろあります。たとえ今はご縁が薄くても、先祖代々お世話になったお寺です。墓じまいについて丁寧に説明しながら相談し、感謝の気持ちやお礼の言葉をしっかりと伝えましょう。法外な離檀料の請求は論外ですが、スムーズに墓じまいを進めるには、相場の上限近く(20~30万円程度)の離檀料を支払うのもひとつの方法でしょう。
證大寺|墓じまいによる改葬受入が可能

歴史豊かな證大寺の入り口
證大寺は江戸川区にあるお寺で、地下鉄やバスなどアクセスしやすい場所にあります。境内には一般墓所のほか、合祀の永代供養墓、個別で入れる永代供養墓、樹木葬などがあり、改葬を受け入れています。東京近郊で改葬先をお探しの場合は、候補の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。
異なる宗派からの改葬受入が可能
證大寺は浄土真宗・大谷派のお寺ですが、異なる宗派からの改葬を受け入れています。宗派だけでなく宗教や国籍、多様な性別を受け入れています。故人を死者ではなく人々を導く仏さまとして、大切に供養しています。
霊園拠点:江戸川区、船橋、森林公園、東銀座(分骨・ラウンジ)

明るいラウンジ
江戸川区にある本坊以外にも、千葉県船橋市と埼玉県東松山市に霊園があります。寺院が運営する霊園として僧侶が常勤、全職員で毎朝の勤行をつとめているほか、お彼岸やお盆には1時間おきに勤行と法話があり、お参りに来られた方との縁を大切にしています。
また東銀座の拠点では「仏教人生大学」を開催、仏教講座や教養講座を催して交流を深める場を提供しています。
江戸川区 證大寺
船橋 昭和浄苑
森林公園 昭和浄苑
仏教人生大学
墓じまいのご相談1000件の実績|無料相談会を実施
墓じまいを考えたとき、やらねばならないことが多く、悩んでしまうこともあるでしょう。そんな時はひとりで抱え込まず、相談してみてください。インターネットを検索すると「墓じまい」の手順や墓じまい支援の業者が多く出てきます。しかし多くの場合は、墓じまいをするお墓のあるお寺の気持ちを理解しないまま、形式上のアドバイスをしているようです。書類提出など形式上は正しくても、お寺側からは一方的すぎるとトラブルになることも多いようです。多くのお寺では「離檀料」を求めているのではなく、親先祖を大事にしてもらいたいと思っている場合がほとんどです。そこを踏まえて、お墓の継承が厳しい事情や、離れて暮らしていてお墓参りに来ることが困難であることを説明すれば、ほとんどのお寺は理解を示しトラブルに発展いたしません。
證大寺では、墓じまいの無料相談会を実施。お寺だからこそ、墓じまいをされる側の気持ちも理解できます。これまで1000件を超える墓じまい実績がありますが、トラブルに発展したケースは皆無です。知識も経験も豊富ですので、皆さまの悩みに寄り添いながら、最適な答えを一緒に考えます。
詳しくは edogawa_hp@sinran.com までメールでお問合せください。
※お使いのブラウザーによってはメールソフトが起動しない場合がございます。その際は、お手数ですがメールソフトを起動し、上記のアドレスを宛先に入力(コピー&ペースト)してお問い合わせください。
まとめ

墓じまいでは、少なからず問題が起こる可能性があり、起きてしまうと費用が余計にかかったり、最悪の場合は墓じまいできないこともあります。
トラブルを未然に防ぐには、知識や経験を持つ方に相談するのが一番です。身近に「墓じまいをした」という方がいないなら、無料の相談会を上手に使って適切な助言を受けるようにしましょう。