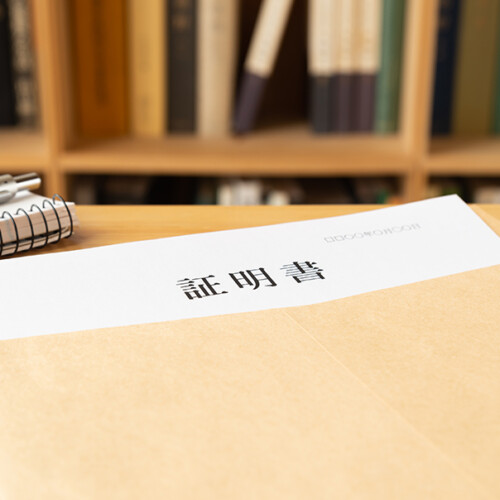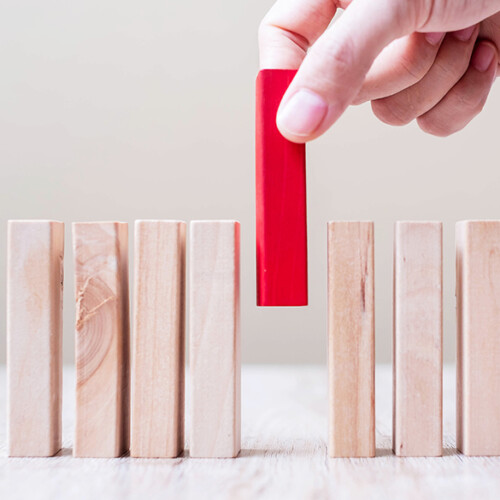墓じまいとは?意味・流れ・費用・供養方法まで総解説

墓じまいとは、お墓を撤去し遺骨を別の場所に移すこと。本記事ではその意味や理由、手続きの流れ、費用、供養方法、注意点までを解説する初めての方でも安心して読める完全ガイドです。
目次
●墓じまいとは?まずは意味と基本を正しく理解しよう
●なぜ今、墓じまいが選ばれているのか?よくある5つの理由
●こんな場合は墓じまいを検討してみよう|状況別の判断ポイント
●墓じまいを決断する前に知っておきたい注意点
●墓じまいをするならいつがベスト?判断のタイミングと進め方
●墓じまいの相談は證大寺に
●まとめ
墓じまいとは?まずは意味と基本を正しく理解しよう

墓じまいとはどういうこと?わかりやすく解説
墓じまいとは、これまでのお墓を閉じ、墓石を撤去して更地に戻し、遺骨を別の納骨先へ移す一連の手続きを指します。
一般に「墓じまいとは」お墓をなくすことだけを意味するのではなく、遺骨の行き先をきちんと整えるまでを含むとされています。改葬(かいそう)とは、遺骨を別の墓地や納骨堂へ移すことの名称です。
手続きの中心は、役所で行う改葬許可の申請です。必要書類としては、改葬許可申請書、現在の埋葬を証明する書類(埋蔵・収蔵証明書)、新しい受け入れ先からの受入証明書などが一般的です。書式や呼称は自治体により異なります。
東京都江戸川区:「墓地改葬許可申請書 兼 許可証」を使用
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e031/kuseijoho/denshi/download/kurashi/d_torokushomei/bochi_kaisou.html
千葉県船橋市:改葬許可申請書のほか、埋蔵(収蔵)証明書や受入証明書も必要
https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/koseki/004/p085300.html
埼玉県東松山市:申請書・記入例をPDFやExcelで公開
https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/28/2116.html
各地域や自治体の案内に従い、事前に新しい納骨先を決め、菩提寺や親族とよく相談して進めることが大切です。
墓じまいを検討する人が増えている理由とは?
近年、改葬(墓じまい)を選ぶ人は増えているといわれています。
背景には、少子化や未婚化の進行による「お墓を継ぐ人がいない」不安、遠方化によるお参りの負担、墓地管理費や維持費の経済的な負担が挙げられます。
また、供養観の多様化も見逃せません。従来の「先祖代々のお墓」を守る形だけでなく、永代供養墓や納骨堂、樹木葬や合同墓など、家族の事情に合った選択肢が広がっています。
客観的なデータでは、厚生労働省の「衛生行政報告例」による全国の改葬件数が参考になります。直近の公的統計によれば、2023年度(令和5年度)の改葬件数は166,886件※1と過去最多を記録し、増加傾向が続いています。
なお、2024年度および2025年度の確定値はまだ公表されていません。数字だけで判断せず、家族の生活や将来像を丁寧に見つめ、必要に応じて寺院や専門家に相談して進めることが安心につながります。
※1出典:厚生労働省令和5年度衛生行政報告例
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&query=%E6%94%B9%E8%91%AC&layout=dataset&toukei=00450027&tstat=000001031469&stat_infid=000040217221&metadata=1&data=1
なぜ今、墓じまいが選ばれているのか?よくある5つの理由

1.お墓を継ぐ人がいない
少子化や未婚化、単身世帯の増加により、将来お墓を守る人がいなくなるケースが増えています。
単身世帯は全世帯の38.1%を占めています※2。さらに、この割合は2050年には44.3%に達するとされており※3、こうした社会構造の変化が、「無縁墓」になる不安を高め、墓じまいを検討する動機につながっています。
※2出典:総務省「令和2年国勢調査」https://www.stat.go.jp/data/index.html
※3出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(2024年推計)」
https://www.ipss.go.jp/pp-ajsetai/j/HPRJ2024/hprj2024_PR.pdf
2.遠方にあるお墓が負担に
お墓が実家や地方にあり、現住所から遠く離れている場合、移動や宿泊の負担が大きくなります。
全国的なお墓参りの平均所要時間はおよそ31分※4という調査もありますが、地方から都市へ移り住んだ世代では、数時間かかる場合も少なくありません。交通費や宿泊費が積み重なり、年を重ねるごとに訪問が難しくなることも理由のひとつです。
※4出典:株式会社鎌倉新書【第15回】お墓の消費者全国実態調査(2024年)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000064.000009951.html
3.お墓の管理が大変になった
高齢化が進み、墓石掃除や草取りなどの管理作業が体力的に負担になる方が増えています。
真夏の草刈りや墓石の洗浄などは、健康面のリスクも伴います。遠方に住む子ども世代にお墓の管理を任せることも難しく、やがて放置状態になる前に墓じまいを選ぶケースが増えています。
4.経済的負担を軽くしたい
お墓には、年間管理費・修繕費・法事などの費用が継続的にかかります。
墓じまいを行う場合の費用相場は全国で30万円〜300万円程度とされます。さらに、改葬に伴う新しい納骨先の購入や永代供養料などを含めると、100万円〜250万円程度になることもあります。
これらの費用を長期的に見たとき、早めに墓じまいを行うほうが総負担を減らせると判断する方も多くいます。
墓じまいの費用について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
>墓じまいのお布施、相場やマナーを徹底解説!後悔しないための完全ガイド
5.従来の「家単位のお墓」に関する価値観の変化・自由な供養を望む
供養の形は時代とともに多様化しています。
従来の「家単位のお墓」から、自然に還る樹木葬、海や山に散骨する方法、複数の遺骨をまとめて供養する合同墓など、選択肢は広がりました。
樹木葬の費用相場は、合葬型で5〜20万円、集合型で20〜60万円、個別型で50〜150万円程度が目安とされます。
こうした多様な選択肢が、家族や本人の価値観に合った供養方法を選びやすくし、墓じまいを後押ししています。
このように、墓じまいが選ばれる背景には、社会構造の変化、生活スタイルの多様化、経済的・身体的負担の軽減といった複数の要因が絡み合っています。それぞれの理由に共感する点があれば、早めに家族で話し合い、将来に備えることが大切です。
こんな場合は墓じまいを検討してみよう|状況別の判断ポイント

跡継ぎがいない or 親族が反対している場合
跡継ぎがいない場合、将来お墓が無縁化する可能性があります。例えば、長男が独身で、次男は遠方に住んでいる家庭では、数十年後にお墓を維持する人がいなくなることがあります。
また、親族が反対する中で墓じまいを進めると、「遺骨を誰が管理するか」「どの供養方法を選ぶか」などで深刻な対立になることがあります。特に兄弟姉妹間や親族間で事前の意思確認がないまま進めると、後からやり直しがきかず関係が悪化する恐れもあります。早めに全員で意見を共有し、合意形成を図ることが大切です。
お墓の場所が遠く、将来的に通えなくなる不安がある
都市部に移住した子ども世代が、地方にある実家のお墓を守るケースは少なくありません。片道2〜3時間以上かかる場合、交通費は年間で数万円単位になり、体力的な負担も大きくなります。
また、仕事の転勤や高齢期の引っ越しなどで、さらに遠方になる可能性もあります。数十年先を見据えると、「今は行けても将来は難しい」という状況になりやすく、その前に墓じまいを選ぶ方も増えています。
お墓の管理費が重く感じてきたとき
お墓を維持するためには、管理費だけでなく、交通費やメンテナンス費、法要費などさまざまな出費があります。これらを長期的に見ると、30年間で数十万円から数百万円になることもあります。
特に遠方にあるお墓の場合は、管理費以外の費用が大きな負担になりやすく、早めに墓じまいを検討する方も増えています。
■お墓に関する30年間で想定される主な費用内訳(目安)
年間管理費(30年間総額):15万円〜60万円前後
なぜかかる?→墓地の清掃・維持・水道代などに充てられる。立地や運営形態で金額差あり。
お墓参り・交通・宿泊費:6万円〜300万円
なぜかかる?→遠方の場合は交通費や宿泊費がかかる。帰省や法事の時期は料金が高くなることも。
メンテナンス費用:無料〜60万円+修繕費
なぜかかる?→墓石の清掃や草刈りを業者に依頼する場合や、地震・劣化で修繕が必要な場合。
これらの金額を墓じまいでかかる費用(30万円〜300万円)と比較すると、将来の総負担が見えてきます。
また、管理費の滞納が続くと使用権を失うケースもあり、維持が難しいと感じた時点で方向性を決めることが、家族の負担軽減につながります。
親族間で墓じまいの話し合いの場を持てていないときの注意点
親族間で墓じまいについて話し合えていない場合は、意思疎通不足が後のトラブルにつながることがあります。特に、誰が申請者になるか、遺骨をどこに移すか、費用負担をどう分担するかは事前に明確にしておく必要があります。
対応策としては、家族全員が集まれる日を設けて話し合い、議事録を残すこと。意見が分かれた場合は、菩提寺や行政書士、石材店など第三者の専門家に同席してもらい、条件や費用を整理しながら進める方法も有効です。こうした事前準備が、感情的な対立や誤解を防ぎ、スムーズな合意形成につながります。
このように、「自分の家の場合はどうか」を具体的に想像しながら判断できるようにすることで、墓じまいの必要性やタイミングがより明確になります。
詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
>墓じまいで起こるトラブルとは?事例と対策、未然に問題を防ぐ方法
墓じまいを決断する前に知っておきたい注意点

注意すべきトラブル事例
墓じまいは家族や親族にとって大きな決断です。そのため、十分な話し合いをしないまま進めると、思わぬトラブルにつながることがあります。
典型的なのが親族間トラブルです。遺骨の分配方法や供養方法を巡って意見が割れ、感情的な対立に発展するケースがあります。また、「菩提寺から離檀料を請求されたが、事前に説明がなかった」という声も少なくありません。離檀料については、法的な支払い義務はありませんが、これまでの感謝を示すお布施として3万円〜20万円程度をご用意するのが一般的とされております。
さらに、遺骨の行き先も注意が必要です。改葬先を決めずに墓じまいを進めた結果、遺骨の行き先が決まらず、保管場所に困る事態になることがあります。書類の不備や申請順序の誤りによって、予定通り改葬できないケースもあるため、事前準備は慎重に行いましょう。
地域別事例:江戸川区・船橋市・東松山市の手続きの違いと特徴
墓じまいの手続きや必要書類は、全国でほぼ共通していますが、自治体によって窓口や書式、郵送対応の有無などが異なります。ここでは、いくつかの地域の事例をご紹介します。
■東京都江戸川区
東京都江戸川区では、改葬許可申請書等の書類を区役所で提出し許可証を交付してもらう流れですが、自治体によって対応にかかる日数等は異なります。一般的には申請から交付まで数日から1〜2週間程度で済む場合が多いとされていますが、年末年始や年度替わりの繁忙期にはさらに時間がかかることがあります。(墓じまい全体の期間については後述の「墓じまいの流れをステップで理解する」をご覧ください)
江戸川区の改葬許可申請書の入手先・詳細
■千葉県船橋市
船橋市では、まず環境保全課で「埋蔵(収蔵)証明書」、次いで戸籍住民課で「改葬許可証」を取得する必要があります。書類提出は基本的に窓口のみで、郵送対応はされていない点に注意が必要です。詳しくは船橋市公式サイトをご覧ください。
船橋市の改葬手続き詳細
■埼玉県東松山市
東松山市では、改葬許可申請書や記入例をPDF・Excel形式で公式サイトからダウンロード可能です。郵送申請にも対応しており、返信用封筒と切手を同封すれば遠方からでも手続きができます。特に遠隔地在住・高齢者にとって利便性が高い自治体です。
東松山市の改葬手続き・ダウンロードページ
墓じまいの流れをステップで理解する
墓じまいは、一度決めたら後戻りが難しい大きな手続きです。あらかじめ全体の流れを知っておくことで、必要な準備やスケジュール感がつかみやすくなります。上述の通り、申請から交付まで数日から1〜2週間程度で済む場合が多いとされていますが、関係者との話し合いから、すべての手続きと工事が完了するまでには、一般的に3ヶ月〜半年、場合によっては1年以上かかることもあります。
以下は一般的な進め方の一例です。
STEP1:家族・親族との「墓じまい」の相談
最初の段階で、家族や親族と十分に話し合い、理解と同意を得ることが重要です。特に親族間で意見の食い違いがある場合、後のトラブル防止になります。
STEP2:菩提寺への相談
寺院にお墓がある場合、住職に墓じまいの意向を伝えます。離檀料の有無や閉眼供養の日程についても確認します。
STEP3:改葬先の決定・受入証明書の取得
新しい納骨先(永代供養墓、納骨堂、他の霊園など)を決め、管理者から受入証明書を発行してもらいます。
STEP4:改葬許可申請書の入手・提出
現在のお墓がある自治体から改葬許可申請書を入手し、必要書類とともに提出します。許可証の交付までに数日〜数週間かかる場合があります。
STEP5:閉眼供養(魂抜き)
お墓の魂を抜く儀式です。僧侶を招き、読経のもとで行われます。
STEP6:墓石撤去・遺骨の移転
石材店に依頼して墓石を撤去し、遺骨を新しい納骨先へ移します。移転時には改葬許可証が必要です。
STEP7:新しい納骨先での納骨・開眼供養
納骨を行い、必要に応じて開眼供養(魂入れ)を行います。
この流れを把握しておくことで、書類の準備や工事日程の調整をスムーズに進められ、全体の期間短縮や費用節約につながります。
墓じまい後の供養方法をどうするか?選択肢を比較
墓じまい後の遺骨は、あらかじめ新しい納骨先や供養方法を決めておく必要があります。主な選択肢と特徴は次の通りです。
永代供養墓:5万円〜30万円が目安。寺院や霊園が永続的に供養してくれます。管理不要で、跡継ぎがいない場合に向いています。
納骨堂:10万円〜100万円程度。屋内型が多く、立地や施設のグレードによって価格が変わります。別途年間管理費が必要な場合があります。
散骨:海や山などに粉骨した遺骨をまく方法。代行散骨は5万円〜10万円、合同散骨は10万円〜30万円、チャーター船による散骨は20万円〜50万円が目安です。
都市部では納骨堂や合同墓が人気で、地方では永代供養墓を選ぶ傾向が多いとされています。
| 供養方法 | 費用目安 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 永代供養墓 | 5万〜30万円 | 寺院や霊園が永代に渡って供養 | 維持費をかけたくない |
| 納骨堂 | 10万〜100万円+管理費 | 屋内型、アクセス良好 | 都市部在住、雨天でも気兼ねなく通いたい |
| 樹木葬 | 20万〜70万円 | 自然と一体化した埋葬 | 自然志向、跡継ぎがいない |
| 散骨 | 5〜20万円 | 海や山へ散骨、儀式多様 | 宗教色薄く自由に供養したい |
墓じまいをするならいつがベスト?判断のタイミングと進め方

法事・命日・お彼岸など節目の時期がベター
墓じまいは、親族が集まりやすく、説明や合意形成がしやすい時期を選ぶのが理想です。特に法事や命日、お彼岸などは自然に集まるきっかけになり、閉眼供養や改葬の説明を行う場として適しています。
実際の進め方としては、命日に合わせて閉眼供養を行い、その後に墓石撤去工事を実施する流れが一般的です。この方法なら、儀式と工事を切り分けて進められるため、精神的な負担も軽減できます。
引っ越しや移住が決まったとき
転勤や移住が決まっている場合は、新生活が始まる前に墓じまいを行うのが理想です。引っ越し後に手続きを進めると、遠方から何度も現地へ足を運ぶ必要があり、交通費・日程調整の負担が大きくなります。節目の時期や余裕のある時期に合わせて進めることで、スムーズかつ経済的に対応できます。
早めの準備が安心につながる理由
墓じまいには、改葬許可申請や受入証明書などの書類準備が必要です。自治体によっては申請から許可までに数週間かかることもあります。さらに、墓石撤去工事は繁忙期(春秋彼岸・お盆前)に依頼が集中し、希望日に施工できない場合があります。
また、費用面でも早めの準備は有利です。1〜2年かけて計画すれば、閉眼供養や改葬工事の費用を分散でき、一度に大きな負担をかけずに済みます。計画的に進めることで、手続きや日程、費用の面でゆとりを持つことができます。
ちなみに、墓じまい業者の繁忙期(お盆・お彼岸前)は料金が高騰することもあります。逆に1〜2月や梅雨明け後などは比較的予約が取りやすく、数万円安くなる場合もあります。
墓じまいの相談は證大寺に

墓じまいは、家族の歩みやこれからの暮らしを見つめ直す大切な節目です。證大寺では、まずご事情を丁寧にうかがい、手続きの流れや費用の見通しを一緒に整理いたします。改葬先の選び方や、菩提寺・親族への伝え方も、無理のない進め方をご提案します。新しいお墓や永代供養のこと、法要の段取りまで含めてご相談いただけます。迷いがあるときこそ、静かに心を整える時間を持ちましょう。
理由を整理して、後悔しない墓じまいを目指す
気がかりを言葉にするところから始めます。事情・希望・予算を整理し、必要な手順を可視化。判断の拠り所が見えてくるよう伴走します。
新しいお墓も、永代供養墓も
屋外の新墓、屋内施設、合同墓や永代供養墓など、複数の選択肢をご案内します。生前の思い出や家族構成に合わせて、無理のない形を一緒に考えます。
費用は抑えて、供養は手厚く
費用の内訳と時期を分けて検討し、負担を軽くする進め方をご提案します。閉眼供養や改葬後の法要も、落ち着いてお勤めできるよう支えます。
證大寺では、墓じまいの無料相談会を実施しています。これまで1000件を超える墓じまい実績があります。しかもトラブルに発展したケースは皆無で、親身に寄り添いながら相談にのってくれます。
墓じまいについて考えている方は、證大寺に相談してみてはいかがだろう。
證大寺:https://shoudaiji.or.jp/
證大寺 江戸川:https://edogawa2.eitaikuyou.life/
森林公園 昭和浄苑:https://higashimatsuyama2.eitaikuyou.life/
船橋 昭和浄苑:https://funabashi2.eitaikuyou.life/
●墓じまいのご相談について詳しくは、下記までメールでお問合せください。
edogawa_hp@sinran.com
まとめ
墓じまいは、人生と家族の歩みに関わる大きな選択です。焦らず、墓じまいする意味や手続きの流れを落ち着いて確かめましょう。気持ちと状況を整え、親族と対話を重ねることが、後悔の少ない判断につながるといわれています。必要に応じて第三者の助言も取り入れ、選択肢を見比べてください。今日の小さな一歩が、静かな安心へと結びつきますように。