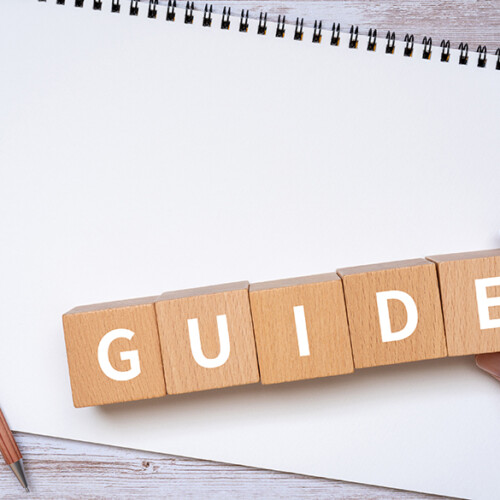お墓はいつまでに建てるべき?最適な時期と注意点を徹底解説!

お墓は故人が安らかに眠る場所であると同時に、遺族にとっては心の拠り所ともなる場所といえます。しかし先祖代々のお墓がない場合などでは、いつまでにお墓を用意すればいいか悩むことも多いでしょう。そこでお墓をたてる最適なタイミングや注意点などについて解説します。
目次
●お墓を建てる時期に決まりはない
●一般的にお墓を建てるのに適した時期
●お墓を建てるまでに必要な準備と流れ
●選べる供養方法|永代供養墓の種類
●お墓を建てる際に注意すべきこと
●お墓でお悩みなら|證大寺
●まとめ
お墓を建てる時期に決まりはない

お墓を建てるタイミングには、特に時期の決まりはありません。いつまでにお墓に納骨すべきなど、法律で決められる期限などもありません。しかし一般的な目安というものは存在します。
お墓は一般的には、四十九日法要や百箇日法要までに用意するとよいといわれています。とはいえ新しくお墓を建立するとなると、それでは間に合わないことも多いでしょう。そのため新盆やお彼岸の時期に合わせてお墓を建てる場合や、一周忌などの法要に合わせて建立することが多いようです。
一般的にお墓を建てるのに適した時期

このようにお墓を建てるのに適したタイミングはいくつかあるとされていますが、それにはどのような理由があるのでしょうか。
四十九日や百箇日までにお墓を建てるケース
一般的に納骨は、四十九日法要とあわせて行われることが多いです。それまでにお墓を建てることができれば、故人の供養として最も適しているといえるでしょう。また遺族にとってもお墓を早めに用意することができれば、気持ちの整理がつけやすいといえます。とはいえお墓を新しく建てるとなると、完成まで2~3ヵ月かかることがほとんどなので、四十九日法要に間に合わないことが多いでしょう。百箇日法要ならそれよりも期間があるので、百箇日法要を目処にするケースもあります。
新盆やお彼岸の時期までにお墓を建てるケース
新盆やお彼岸などの法要にあわせて、お墓を建てるのもよく見られるケースです。新盆やお彼岸は親族が集まる機会となり、法要と一緒に納骨式を行うことができるからです。しかしお盆の時期は暑いから、秋のお彼岸は台風がくるかもしれないからなど、気候を理由として避ける場合もあります。
一周忌・三回忌に合わせてお墓を建てるケース

一周忌や三回忌などの法要に合わせて、お墓を建てるというケースも多く見られます。年忌法要は親族が集まる機会となり、1~2年と時間的な余裕があるので準備や計画しやすいというメリットがあります。ただし三回忌に間に合わないと次の法要は七回忌で、4年も空くことになってしまいます。心の整理がつかずなかなか納骨に踏み切れない場合でも、できれば三回忌までにお墓を用意して納骨するようにしたいものです。
生前にお墓を建てる「寿陵(じゅりょう)」という選択肢もある
亡くなる前にお墓を建てておくというのも、選択肢のひとつです。生前にお墓を建てることを「寿陵(じゅりょう)」と呼び、昔から縁起がよいとされています。生前なら希望にあわせたお墓を建てることができ、事前に用意することで遺族の負担も軽減できるというメリットもあり、最近は生前に用意する人も珍しくありません。またお墓には相続税がかからないので、節税対策にもなります。ただしお墓を建てた時点から管理料が発生することがほとんどなので、その点については注意が必要です。
お墓を建てるまでに必要な準備と流れ

ではお墓を建てるための準備とはどのようなことをしなければならないのでしょうか。お墓を建てるまでに必要な準備の詳細を、建立までの流れとともに紹介します。
墓地・霊園を選ぶ(公営・民営・寺院墓地の違い)
まずはどこにお墓を建てる場所を決めるために、墓地や霊園を探すことになります。墓地や霊園は大別して公営霊園、民間霊園、寺院墓地の3種類があります。3種類のどれを選ぶかに加えて、立地条件や予算なども考慮して決めるようにしましょう。
■公営霊園
公営霊園は、市町村などの自治体が運営しているものです。比較的割安なことが多いものの、購入に条件が付けられていることもあります。また人気の公営霊園は抽選制になっているケースが多く、抽選に外れると購入できません。さらに抽選の時期が決まっていて、買いたい時に買えないということもありがちです。
■民間霊園
民間霊園は、宗教法人や公益法人などが運営管理しているというものです。設備が充実しているものが多いですが、公営に比べ割高な傾向にあるといえます。また指定石材店制というルールを設けている民間霊園も多くあります。墓石の製造や工事は指定石材店に依頼するというルールで、それ以外の石材店には依頼できないというものです。
■寺院墓地
寺院墓地はお寺が運営・管理しているものです。お寺によって異なりますが、檀家にならないと利用できなかったり、宗旨宗派が異なると断られたりすることもあります。その一方で、供養はそのお寺の宗旨宗派で行うものの、生前の宗旨宗派を問わずに入れるというところも多くあります。
お墓の種類やデザインを決める(和型、洋型など)

墓地が決まったら。どのようなお墓にしたいかを考えるようにしましょう。墓石には、主に「和型」とよばれる縦長タイプのほか、「洋型」と呼ばれる横長タイプがあります。このほか最近では個性的なデザインの墓石にする方もいます。墓石の石材もさまざまな種類があって、好みなどで選ぶことができるのが一般的です。ただしデザインや石材などによって費用は異なるので、石材店と相談しながら予算を考慮して決めるようにしましょう。
石材店との契約(費用や工期の確認)
お墓のデザインや墓石の石材などが決まったら、石材店から見積書をもらうようにしましょう。費用を確認して納得できれば契約となります。また法要に間に合わせたいなどの希望があれば、しっかり伝えて工期を確認してから契約するようにしましょう。
お墓の建立・開眼供養を行う(僧侶の手配、法要の準備)
お墓が建立できたら、開眼供養を行うことになります。開眼供養とは、お墓を「物」から「供養の対象」に変えるための儀式のことで、「魂入れ」「お性根入れ(おしょうねいれ)」などとも呼ばれます。菩提寺と相談して開眼供養の日時を決め、墓前まで僧侶に来て貰えるように手配します。また開眼供養は、納骨式と同じタイミングで行われることも多いので、納骨する場合は納骨式の準備もあわせて行うようにしましょう。
選べる供養方法|永代供養墓の種類

最近は埋葬や供養の方法も多様化しています。新しくお墓を建てる以外にも、納骨堂や樹木葬などのお墓を購入するという選択肢もあります。以下で紹介する方法なら、新しくお墓を建てるよりも短期間で契約できるため、四十九日法要に間に合う可能性もあります。また費用もお墓を建てるよりも抑えられる傾向にあり、後の承継問題が起こらないというメリットもあります。
永代供養墓
永代供養墓とは、お寺や霊園が管理も供養も行ってくれるお墓のことです。一般的に永代供養墓と呼ばれるものは、個別墓タイプと合祀タイプに大別できます。
個別墓タイプは墓石があってその下に遺骨を納骨するというスタイルのものが多く、1人だけが入るものもありますが、夫婦一代限り、または子供と二世代のお墓として利用する方が多いです。従来のお墓と異なるのは、安置できる期間が決まっている点です。33回忌や50回忌など一定期間を過ぎると、供養塔や合祀墓に合祀されることが多いです。
一方、合祀タイプは血縁関係のない他の人の遺骨と一緒に埋葬する方法で、骨壺から遺骨を取り出して埋葬されます。
永代供養付きの樹木葬
樹木葬とは、墓石ではなく樹木をシンボルとしたお墓で、永代供養付きのものがほとんどです。樹木葬は主に、里山型と庭園型の2種類があります。
里山型の樹木葬は山の中など自然が豊かな場所にあり、自然回帰を願う方に人気があります。
庭園型は墓地や霊園の一角に区画が設置されていることが多く、お墓の整備や管理も里山型よりも充実している傾向にあります。また1人、夫婦などペアで、家族で入れるタイプなどもあります。
樹木葬は一定の安置期間を過ぎると合祀されるものと、合祀されないものがあります。また最初から合祀するタイプのものもあります。
永代供養付きの納骨堂
納骨堂もお墓として利用できる屋内施設で、ほとんどのものが永代供養付きになっています。ロッカー型や墓石型などさまざまなタイプがあり、こちらも1人だけでなく夫婦や家族で入れるものなどがあります。ただし多くの納骨堂では、一定の安置期間が過ぎると他の方と一緒に合祀されることになります。
お墓を建てる際に注意すべきこと

お墓を建てるという経験は、人生に何度もあるものではないでしょう。お墓の建立を検討する前に、以下のポイントについても注意しておくようにしましょう。
お墓の工事時期を考慮する
春や秋は気候が安定し、一般的にはお墓の工事には適した時期だとされています。反対に夏や冬は暑さや寒さが厳しく天候の影響を受けやすく、工事が遅れる可能性があって不向きといわれています。お墓を建てるにはさまざまな準備や工程があり、数ヶ月かかることも珍しくありません。早めの準備をして計画を立て、石材店と相談して工期を決めるようにしましょう。
お墓を建ててはいけない年とは?避けるべき時期
昔からの言い伝えで「うるう年にお墓を建てるな」というものがあります。これは江戸時代の武士が年俸制だったことの名残です。太陰暦のうるう年は1年が13ヵ月あり、12ヵ月と同じ年棒額で13ヵ月を賄わなければならないことから、大きな買い物は避けるべきという意味です。現代とは事情が異なるので、特に気にしなくてもよいでしょう。
このほか厄年も避けるべきという説もありますが、特に根拠はありません。また日にちでいえば大安や仏滅などの六曜を気にする方もいますが、これも仏教的には意味がないとされています。ただし地域によっては昔ながらの習慣として守られている場合もあるので、気になる場合は周囲に確認するようにしましょう。
お墓でお悩みなら|證大寺

写真:證大寺「船橋昭和浄苑」でお墓を建立する様子
證大寺は江戸川区にある浄土真宗大谷派のお寺です。新宿都営線の一之江駅より徒歩10分の場所にあり、すぐ側にバス停もあってアクセスしやすい環境にあります。お寺に隣接した墓地は都心にありながら緑が豊か。また證大寺は埼玉の「森林公園昭和浄苑」、千葉の「船橋昭和浄苑」という2つの霊園を直接運営していて、車で行きやすく、最寄り駅からバスも出ていてアクセスに便利です。
さらに證大寺や昭和浄苑では「お寺タクシー」というサービスがあります。これは自宅からお墓まで月に1度無料で送迎してくれるというものです。また「お寺巡回バス」も運行を開始しました。これはお寺が定めたバス停をまわっていくものです。生活導線上にある病院やスーパーなどもバス停にありますのでお参りの後に寄ることも出来て便利なサービスです。
一般墓はもちろん、樹木葬や納骨堂も
證大寺や昭和浄苑でも、新しくお墓を建立することができます。また納骨堂や樹木葬などもあり、多彩な中からお墓を選ぶことができます。供養は浄土真宗大谷派の教えに基づいて行われますが、生前の宗旨宗派不問で入ることができ、檀家になる必要もありません。またいずれのお墓も生前に予約の希望にも応じてもらえます。お墓のことで悩んでいるなら、證大寺に相談してみてはいかがでしょうか。
證大寺:https://shoudaiji.or.jp/
證大寺 江戸川:https://edogawa2.eitaikuyou.life/
森林公園 昭和浄苑:https://higashimatsuyama2.eitaikuyou.life/
船橋 昭和浄苑:https://funabashi2.eitaikuyou.life/
まとめ

先祖代々のお墓がない、あっても遠くて新しくお墓を建てたいなどの理由で、新しくお墓を建てたいと考える方もいるでしょう。そうなるとなにかと準備も必要です。ベストなタイミングでお墓を建てられるように、しっかり計画しながら進めるようにしましょう。また早くお墓に納骨したい場合や、代々の継承が困難な場合は、永代供養付きのお墓を検討するのもいいのではないでしょうか。