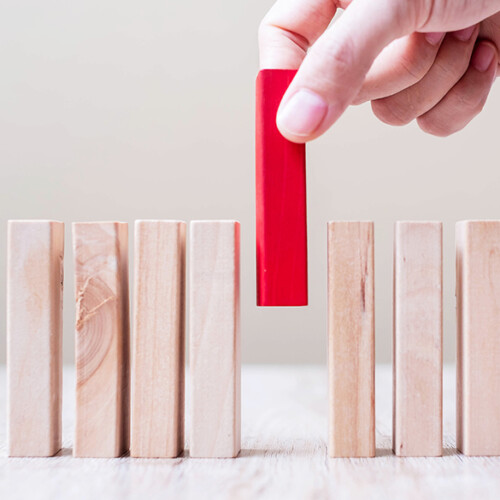お骨(おこつ)とは|お骨は自宅に置いておいてもいいの?お骨の3つの供養方法

人が亡くなって葬送する場合、日本では火葬が主流で99%以上が火葬されています。そのため故人は火葬後の「お骨」という形で、最後に残ることになります。この記事ではお骨についての知識のほか、お骨の納骨方法などについても解説します。
目次
●お骨(おこつ)とは故人の骨
●収骨とはお骨を骨壺に収めること
●分骨とはお骨を分けて供養すること
●お骨の3つの供養方法
●お骨の供養に関するよくある質問
●お骨の納骨先でお悩みなら|證大寺
●まとめ
お骨(おこつ)とは故人の骨

お骨(おこつ)とは故人の骨のことで、遺骨とも呼ばれます。火葬されて骨になり、骨壺に収められたものをさすのが一般的です。故人の存在を感じられるため、供養の対象にされています。
意外と知らない?お骨の数え方
お骨の数え方はさまざまあり、「体(たい)」、「片(へん)」、「本(ほん)」、「柱(はしら)」などと数えられますが、これらには違いがあります。全身の骨の場合は一体、二体と数えるのに対し、砕けた状態の骨は一片または一本と数えることが多いです。また骨壺に入った状態のお骨は一柱、二柱と数えることがあります。柱とは神道での神様の数え方で、死者を神格化する風習から「柱」という数え方が生まれたといわれています。
収骨とはお骨を骨壺に収めること

収骨とは、故人が火葬された後にお骨を骨壺に収めることをいいます。収骨と似た言葉として「お骨上げ」があります。仏式の場合、2人1組になって遺骨を骨壺に収めるという習慣がありますが、お骨上げはお骨を拾い上げる行為自体をさします。お骨上げは、拾骨(しゅうこつ)、お骨拾い(おこつひろい)などとも呼ばれます。また収骨の際になぜ2人1組で箸を使って拾うのかというと、「無事に三途の川を渡れるように、橋渡しをして手助けする」という意味があるとされています。しかし浄土真宗の場合は、三途の川を渡るという考え方や、2人で1組になってお骨上げするというような作法は定められていないため、1人ずつ収骨します。
分骨とはお骨を分けて供養すること

分骨とは、故人のお骨をいくつかに分けて供養することです。火葬の際に分骨することが決まっている場合は、火葬場に分骨証明書を発行してもらいます。分骨証明書とはお骨が誰のものであるかを証明するための書類です。分骨後にお墓へ納骨する際や、海や山へ散骨する場合などにも証明書が必要になります。
また俗説として分骨は良くないといわれることもありますが、分骨は法律上も宗教上も問題ありません。分骨の正しい知識など詳細については、下記のリンク先記事を参照してください。
https://shoudaiji.or.jp/baton/post249/
お骨の3つの供養方法

お骨となった故人は丁寧に供養したいものですが、供養にはいくつかの方法があります。ちなみに分骨した場合も、供養場所や供養方法が異なったとしても供養自体は行うのが一般的です。
(1)墓地や霊園に納骨する
もっともオーソドックスなのが、墓地や霊園に納骨して供養するという方法でしょう。とはいえ最近ではお墓への価値観が多様になったこともあり、墓地や霊園に納骨する場合でもさまざまな納骨先があります。どのような納骨先があるのかを以下で説明します。
またお墓の種類については、下記のリンク先記事でも紹介しています。
https://shoudaiji.or.jp/baton/post644/
■一般墓
一般墓とは、墓石があるお墓のことで、代々継承されるのが前提となっているお墓をさします。先祖代々のお墓はもちろん、新しく建立した場合も含まれます。お骨は墓石の下にあるカロートに納骨されます。
■納骨堂や樹木葬
新しいお墓の形として注目されているのが、納骨堂や樹木葬です。どちらも継承を前提としない永代供養付きのものが多いため、お墓の承継者がいない場合でも安心などといった理由で人気を集めています。納骨堂では屋内施設の決められたスペースにお骨を納めることになります。また樹木葬は木や草花を墓標とするもので、区画の決められたスペースにお骨を納めます。
■永代供養墓
永代供養墓とは、お寺や霊園が家族や子孫に代わって管理・供養してくれるお墓のことです。供養塔や合祀墓などと呼ばれることもあります。血縁に関係なく、他人の遺骨と一緒に埋葬されて供養され、骨壺からお骨をだして埋葬するというものが多いです。
ただし永代供養付きの納骨堂や樹木葬も広い意味での永代供養墓に含まれるほか、個別の永代供養墓というものもあります。これらの場合はお骨を骨壺に収めたまま納骨されることが多いようです。
(2)散骨する

お骨を撒く散骨も、現代では供養方法の一つとされています。散骨はお骨をパウダー状に粉砕して海や山などに撒くことから、自然に還る自然葬であると考えられています。お墓の購入も管理も不要なこともあり、散骨を選ぶ方が徐々に増えてきています。ただし散骨は法律に違反する行為ではないものの、粉砕したお骨の大きさや散骨場所についてなど、さまざまな制限があります。このため実績のある専門業者に依頼して行うのが一般的です。散骨について詳しくは下記のリンク先記事を参考にしてください。
https://shoudaiji.or.jp/baton/post688/#sankotsuchuiten34
(3)手元供養する
手元供養とは、お骨を自宅等に置いて供養するという方法です。お墓の費用や管理の必要がないだけでなく、自宅だと毎日お参りして供養でき、故人を身近に感じることができます。
お骨の供養に関するよくある質問

お骨の供養に関するよくある質問を以下にまとめましたので、参考にしてください。
Q.お骨は自宅に置いておいてもいいの?
お骨を自宅において保管するのは、法律上問題はありません。手元供養という形でお骨を自宅において供養する方も多いです。また故人と離れがたい、身近に感じていたいからなどの理由で、お骨の大半をお墓等に納骨し、一部を分骨して手元供養する人も多くいます。
Q.お骨を捨てるのは法律違反?
お骨をゴミとして廃棄したり公共の場に放置したりした場合は、「遺骨遺棄罪」となり法律違反になります。手元供養していた人が亡くなった場合なども、遺棄してはいけません。どこかに納骨するか散骨するなど法律に則って対処するようにしましょう。
Q.お骨の供養にかかる費用は?
お骨の供養はどのような方法で行うかによって費用は異なります。お墓を新たに建てる場合は150万以上、手元供養は0円~可能とされていて、費用の幅は大きいといえるでしょう。供養方法の違いによる相場については、下記のリンク先記事に詳細がありますので参考にしてください。
https://shoudaiji.or.jp/baton/post773/#ohakanedan-hiyoubosekinashi
お骨の納骨先でお悩みなら|證大寺

写真:相談の様子(江戸川区にある證大寺)
江戸川区にある證大寺には一般墓の墓地のほか、納骨堂や樹木葬、永代供養墓などがあります。お墓の種類が豊富なほか、浄土真宗大谷派のお寺であるものの生前の宗旨・宗派不問で檀家にならずお墓に入ることができ、人気を集めています。また散骨も信頼できる会社に紹介をしてくれるなど、納骨に関して親身に相談にのってくれます。納骨先で悩んでいたら、證大寺に相談してみてはいかがでしょうか。
證大寺 江戸川:https://edogawa2.eitaikuyou.life/
森林公園 昭和浄苑:https://higashimatsuyama2.eitaikuyou.life/
船橋 昭和浄苑:https://funabashi2.eitaikuyou.life/
まとめ

人が亡くなって、最後に残る姿がお骨です。お骨の納骨先や供養方法は、価値観の多様化を受けてこれまでのお墓への納骨だけでなく、納骨堂や樹木葬、散骨、手元供養などさまざまな形で行われるようになっています。どの形をとるにせよ、故人の意に沿い遺族も納得できる供養となるようにしたいものです。