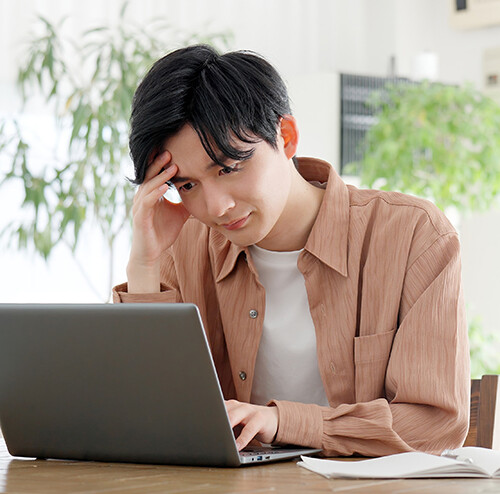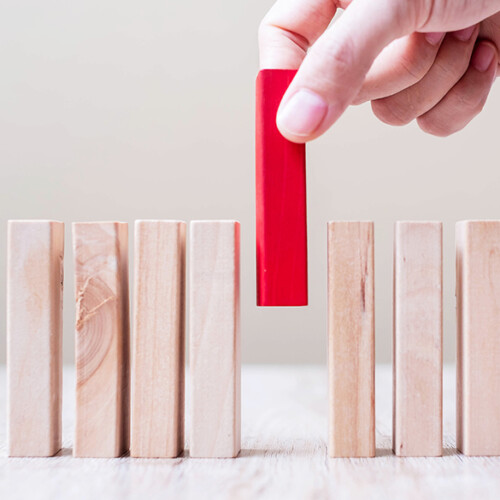埋葬許可証とは?取得する方法と発行手順、注意点を解説

お墓などに遺骨を納骨する際には、「埋葬許可証」が必要です。また埋葬許可証と混同されがちなものとして「火葬許可証」というものもあります。そこでこの記事では、埋葬許可とはどんなものであるか、また火葬許可証との違いについてなどを説明します。さらに埋葬許可証の発行の手順や、失くした場合の再発行の方法などもお伝えします。
目次
●埋葬許可証とは
●埋葬許可証を取得する方法と発行手順
●埋葬許可証を紛失した時の再発行手続き
●埋葬許可証に関する注意点
●納骨先でお悩みなら|證大寺
●まとめ
埋葬許可証とは

埋葬許可証とは、火葬した故人の遺骨をお墓などに納骨する際に必要となる書類です。この書類がなければ、納骨することはできません。公的な書類であるものの、埋葬許可証の表記は自治体によって異なっています。
納骨の際に墓地や霊園に提出
埋葬許可証とは本来は、土葬で埋葬することを前提として発行されたものです。「埋葬」という名称が付いているのも、日本ではかつては土葬が主流だった名残といえるでしょう。火葬が主流になった現在でも、火葬した遺骨をお墓などに納骨する際には必要となり、墓地や霊園の管理者に埋葬許可証を提出することになっています。
埋葬許可証と火葬許可証との違い
では埋葬許可証と混同しやすい「火葬許可証」との違いはどんなものでしょうか。埋葬許可証はお墓などに納骨するための書類であるのに対し、火葬許可証は故人の遺体の火葬を許可する書類となり、この書類がないと火葬できません。火葬許可証は死亡届提出時などに役所で発行してもらい、火葬場に提出することになっています。
埋葬許可証を取得する方法と発行手順

現代の日本では99.9%が火葬となっています。そのため火葬許可書を取得した後に、埋葬許可証を取得するのが手順となります。以下で一連の手続きについて述べますが、一般的には故人の家族等が手続きを行うことが多いですが、最近では葬儀社のスタッフに代行してもらうことも増えています。
【手順1】死亡届を提出する
埋葬許可証を取得するには、まず市区町村役場で死亡届を提出する必要があります。提出する役所は、故人の本籍地もしくは死亡地、または届出人の居住地の市区町村役場となります。死亡届の用紙には「死亡診断書」も付いているので、臨終に立ち会った医師や遺体を検案した医師に記入してもらい、死亡届に必要事項を記入したうえで提出します。
【手順2】火葬許可証を申請する

死亡届を提出する役所の窓口には「火葬許可証申請書」も置かれています。火葬許可証申請書に必要事項を記入して、死亡届と一緒に提出して申請します。書類に不備がない限りその場で受理され、火葬許可証を発行してもらえます。
【手順3】火葬場に火葬許可証を提出する
火葬許可証を受け取った後は、火葬までの間しっかり管理・保管しておきましょう。火葬当日に火葬場へ持って行き、管理者に提出するようにします。
【手順4】火葬許可証は押印されると埋葬許可証になる
火葬場に提出した火葬許可書は、火葬後に火葬した日時を記入して証印が押された状態で返却されます。押印されて返却された火葬許可証は、「埋葬許可証」として使用することができます。埋葬許可証は地域などによって「火葬埋葬許可証」や「死亡届・火葬許可証」などと記載されている場合もあります。名称が違っても火葬が実施されたことを認める押印があれば、埋葬許可証としての効力を持つことになります。
埋葬許可証を紛失した時の再発行手続き
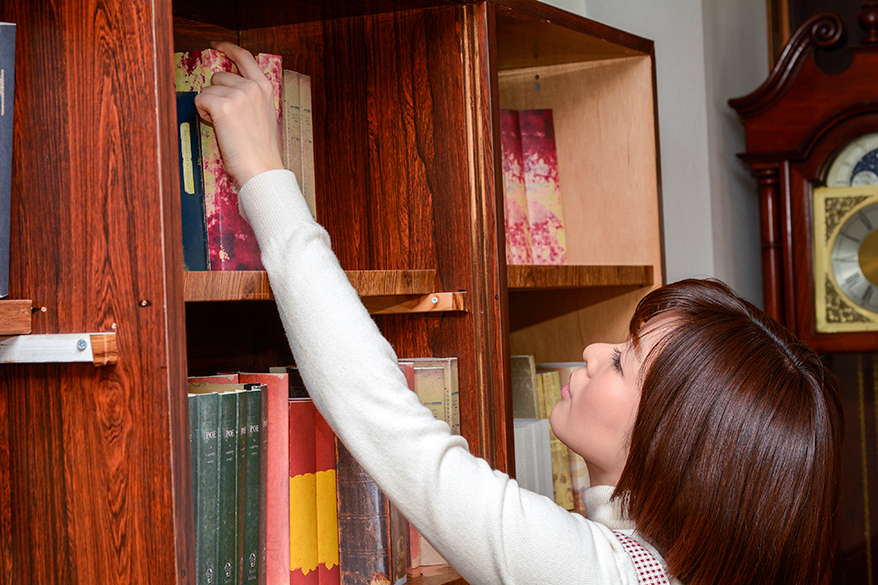
火葬後、納骨まで時間があるなどの事情で、埋葬許可証を紛失してしまった場合は役所で手続きをとれば再発行してもらえます。費用は数百円程度と負担にならない金額です。ただし再発行を申請できるのは、死亡届の届出人や故人の直系親族、祭祀継承者に限られています。また最初に発行された時から「5年未満」なのか「5年以上」経っているかによっても手続きは少し変わってきます。
発行後5年未満の場合
埋葬許可証発行後5年未満の場合は、死亡届を提出した役所で再発行を申請するようにしましょう。5年未満なら役所に火葬許可証を申請したという記録が残っているので、すぐに再発行してもらえます。死亡届を提出した人が手続きする場合は、本人確認書類や印鑑なども用意して持参します。それ以外の場合は戸籍や住民票など故人との関係が証明できる書類も必要となることもあるので、まずは役所の窓口で確認するようにしましょう。
発行後5年以上の場合
埋葬許可証発行から5年以上経っている場合は、役所によっては火葬許可申請書が保管されていない場合があります。その場合は埋葬許可書の再発行に火葬証明書が必要となります。まず火葬場で火葬証明書を再発行してもらってから、役所に申請して手続きをすることになります。手続きに必要な書類等は概ね5年未満と同じですが、役所によって異なる場合があるので確認するようにしましょう。
埋葬許可証に関する注意点

埋葬許可証の取得はそれほど難しい手続きではありません。とはいえ急な訃報で動転していたり、煩雑だと感じた場合は、葬儀社などに代行を頼んでもよいでしょう。ただし取得時や取得後には注意しておきたいポイントもあります。
合祀墓や樹木葬などでも必要
埋葬許可証が必要となるのは、先祖代々などの一般墓だけではありません。合祀墓や樹木葬、納骨堂などに納骨する場合でも、埋葬許可証が必要となります。お墓の種類を問わずに必要なものであると心得ておきましょう。
納骨の際に使えるのは「埋葬許可証の原本」だけ
埋葬許可証は納骨の際に霊園や墓地の管理者に提出しますが、その際使えるのは「原本」だけです。念のためにとっておいたコピーはあるものの、原本が紛失してしまったなどという場合は、再発行してもらわないと納骨を受け付けてもらえません。また分骨して複数のお墓に納骨する場合も、コピーで代用することはできません。
分骨する場合は場所ごとに埋葬許可証が必要
分骨する場合は、納骨する場所ごとに埋葬許可証が必要となります。埋葬許可証は提出後に返却されないので、1通を使い回すことはできません。あらかじめ分骨が決まっている場合は、火葬の際に火葬場に伝えておきます。そうすれば火葬場で分骨する数の埋葬許可証を発行してもらえます。その場合「火葬証明書(分骨用)」と記載された書類となり、埋葬許可証として使用することができます。
散骨や手元供養する場合も取得しておく

故人の希望などで散骨する場合も、埋葬許可証を取得しておいた方が無難です。散骨の場合は公的には散骨業者へ埋葬許可証を提出する義務はないものの、業者によっては身元確認のために埋葬許可証の提示を求められることがあるからです。
手元供養する場合は提出先がないので、不要と思う方もいるかもしれません。しかし手元供養を行っていた人が亡くなったり、事情で手元供養を続けられなくなった場合は、どこかに納骨することになることが多いです。その際に埋葬許可証が必要となるので、あらかじめ取得して保管しておくようにしましょう。
埋葬許可証は大切に保管する
埋葬許可証は納骨の際に必要となるので、それまでは大切に保管しましょう。火葬と納骨の時期がずれる場合は、紛失しないように特に注意しましょう。また埋葬許可証は、お墓の購入時などでも確認として提示を求められることがあります。再発行ができるとはいえ手間となってしまうので、家族と保管場所についての情報を共有しておくようにすると安心です。
ちなみに手続きを葬儀社に依頼した場合は、骨壺の袋の中や桐箱の中に納められていることが多いので、見当たらない場合は、まずはそこを確認してみるようにしましょう。
納骨先でお悩みなら|證大寺

写真:證大寺で相談を受けている様子
證大寺は江戸川区にある浄土真宗大谷派のお寺です。本坊の墓地のほか、埼玉県の森林公園と千葉県の船橋に「昭和浄苑」という霊園を直接運営しています。いずれも一般墓はもちろん、合祀墓や樹木葬など、さまざまな種類のお墓があります。納骨先が決まっておらず悩んでいるなら、證大寺に相談してみてはいかがでしょうか。
詳しくは下記のリンク先をご参照ください。
https://higashimatsuyama2.eitaikuyou.life/
https://edogawa2.eitaikuyou.life/
https://funabashi2.eitaikuyou.life/
まとめ

埋葬許可証とは、お墓に納骨する際に必要となる書類です。火葬場に提出した「火葬許可証」に、火葬済の押印がされたものが埋葬許可証となって使用することができます。万一失ってしまっても再発行できますが、大切な物なので紛失しないよう、納骨まで大切に保管しましょう。