墓じまいで後悔しないために|失敗事例と対策・費用相場・改葬手順をやさしく解説

「墓じまい」を考え始めたとき、多くの人が不安を感じます。後悔しないために知っておきたい5つの事例と、具体的な対策、正しい手順を解説します。ご家族との大切な対話の一助となれば幸いです。
目次
●墓じまいとは?後悔を避けるための必須知識
●墓じまいで後悔する5つの事例
●墓じまいの後悔を回避する5つの対策
●墓じまいにおけるメリットとデメリット
●墓じまい完了までの7つのステップ
●墓じまい後の供養の選択肢
●墓じまいに関するよくある質問(Q&A)
●證大寺のご案内
●まとめ:後悔しない墓じまいは「準備」と「対話」で決まる
墓じまいとは?後悔を避けるための必須知識

ご先祖様から受け継いできたお墓を、どう守っていくか。これは、現代を生きる私たちにとって、とても大きな問いかけとなっています。
「墓じまい」という言葉を聞く機会が増え、関心を持つ方がいる一方で、「後悔しないだろうか」と、心に迷いを抱える方も少なくありません。
墓じまいは、一度行うと元に戻すことが難しい、大切な決断です。
だからこそ、まずはその意味や背景を正しく知ることが、後悔を避けるための第一歩となります。
ここでは、墓じまいの基本的な知識と、もし現状のままにした場合のリスクについて、静かに確認していきましょう。
墓じまいの意味と「改葬」
「墓じまい」とは、現在使用しているお墓の墓石を撤去・解体し、その土地を更地(さらち)にして、墓地の管理者様へお返しすることを指します。
ただ、お墓を単に「やめる」ことだけを指すのではありません。
多くの場合、墓じまいには「改葬(かいそう)」という手続きが伴います。
改葬とは、お墓から取り出したご遺骨を、別の場所へ移して新しく納骨し、供養を続けることです。
移転先としては、納骨堂や樹木葬、あるいは他の方々と一緒に供養される合祀墓(ごうしぼ)など、さまざまな形が選ばれるようになりました。
つまり墓じまいは、お墓の「お引っ越し」や「整理」を含めた、一連の流れ全体を指す言葉として使われています。
墓じまいが選ばれる社会的背景
近年、墓じまいを検討される方が増えている背景には、私たちの暮らしや社会の大きな変化があります。
最も多い理由としては、「お墓の跡継ぎ(承継者)がいない」というお悩みです。
また、少子化や核家族化が進み、子どもがいても「将来の負担をかけたくない」と考える親御さんも増えています。
生まれ育った故郷を離れて都会で暮らす方が増えたことで、「お墓が遠方にあり、なかなかお参りや管理ができない」という現実的な問題もあります。
これらは、誰か一人の責任ではなく、ライフスタイルが多様化した現代社会特有の、やむを得ない事情といえるでしょう。
墓じまいをせずに放置すると、無縁仏や費用負担のリスクが残る
では、もしお墓の管理が難しいまま、墓じまいもせずに放置してしまったら、どうなるのでしょうか。
まず考えられるのは、お墓の荒廃です。
お掃除やお参りをする方がいなくなれば、お墓は次第に雑草に覆われ、荒れていってしまいます。
そして、お墓の管理費の支払いが滞り、長期間連絡もつかない状態が続くと、最終的には「無縁仏(むえんぼとけ)」として扱われてしまう可能性があります。
無縁仏とは、供養する身寄りのない仏様のことを指しますが、墓地管理の観点からは、管理者がお墓を強制的に撤去できると法律や条例で定められている場合があります。
撤去された墓石は処分され、ご遺骨は他の方々のご遺骨と一緒に合祀されることになります。
また、ご親族のどなたかが承継者である限りは、お墓が遠方にあっても、管理費や維持費の経済的な負担は永続的に続いていくことになります。
こうした現状維持のリスクを知ることも、ご自身やご家族にとって最善の道は何かを考える上で、大切なことだといえます。
墓じまいで後悔する5つの事例

墓じまいは、一度実行すると、元の状態に戻すことはできません。だからこそ、慎重な準備が何よりも大切になります。
お墓を大切に思う気持ちから決断したにもかかわらず、後になって「こうすれば良かった」と心残りを感じる方もいらっしゃいます。
実際に多くの方がどのような点で後悔をされたのか、その典型的な事例と理由を5つの視点から静かに見つめてみましょう。ご自身の状況と照らし合わせることで、大切な気づきがあるかもしれません。
事例1:【親族トラブル】相談なしで進め、関係が悪化した
「自分がお墓を守ってきたのだから」と良かれと思って一人で話を進めたところ、ご親戚から「なぜ一言も相談してくれなかったのか」と猛反対を受けてしまった。
あるいは、墓じまいの費用負担の割合についてご兄弟と意見が合わず、関係が気まずくなってしまった。
こうした、ご親族との間のトラブルは、最も多く聞かれる後悔の一つです。
法律上は、お墓の管理や供養を引き継ぐ「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」、いわゆる「墓主(はかぬし)」に決定権があるとされています。
しかし、お墓は法的な側面だけでなく、「ご先祖様から続く、家みんなのもの」という感情的な側面を強く持っています。
そのお墓に思い入れのあるご親族のお気持ちを軽視してしまうと、取り返しのつかない溝が生まれてしまうことがあるのです。
事例2:【費用トラブル】想定外の出費で予算オーバー
墓じまいの費用として、墓石の撤去費用だけを考えていたら、想定外の出費が重なってしまった、というケースです。
例えば、お寺の檀家(だんか)をやめる際に、これまでのお礼として「離檀料(りだんりょう)」をお包みすることがあります。この金額が予想より高額であったり、墓石を撤去する前に行う「閉眼供養(へいがんくよう)」などのお布施、細かな手続き費用などが積み重なったりすることがあります。
後悔の理由は、墓じまいに必要な「総額」の見積もりが十分でなかった点にあります。
墓石の撤去費用だけでなく、法要に関する費用、離檀のお礼、そして新しい納骨先の費用まで、全体を把握しておくことが大切です。
事例3:【納骨先選び】安易に決め、供養の形に不満が残った
ご遺骨の新しい行き先となる納骨先選びも、後悔の分かれ道となりやすいポイントです。
「費用をできるだけ抑えたい」と考え、他の方々のご遺骨と一緒に埋葬される「合祀墓(ごうしぼ)」を選んだ。しかし、いざ納骨の際に、ご先祖様のご遺骨が他の方と混ざり合うのを見て、何とも言えない寂しさを感じてしまった。
また、自然に還したいと「散骨(さんこつ)」を選んだものの、その後、手を合わせる具体的な対象がないことに、心の喪失感を覚えてしまった。
こうした思いは、「ご遺骨を個別に残したいか」「お参りする場所は必要か」といった、ご自身やご家族が大切にする供養の価値観を、事前に深く整理しなかったために生じることがあります。
事例4:【寺院トラブル】配慮のない伝え方で、お世話になった寺院と関係がこじれた
菩提寺(ぼだいじ)、つまりご先祖代々お世話になっている寺院との関係が悪化してしまうケースもあります。
これまでのお付き合いがあるにもかかわらず、ご住職に対して、いきなり「お墓をしまいますので、手続きをお願いします」と一方的に伝えてしまった。その結果、ご住職の心証を損ねてしまい、その後の話し合いが難航してしまった。
お寺にとって、檀家の方が墓じまいをされることは、ご縁が切れる寂しさだけでなく、お寺の運営にも関わるデリケートな問題です。
これまでご先祖様を供養してくださったことへの感謝や敬意を欠いたコミュニケーションをとってしまうと、円満に進むはずの話もこじれてしまうことがあります。
事例5:【タイミング】墓じまいを先延ばしにし、心身ともに疲弊
「いつかやらなければ」と思いながらも、なかなか決断できずに先延ばしにしていた。
そして、70代後半や80代になり、いよいよ重い腰を上げたものの、ご親族との調整、役所での煩雑な手続き、お寺様との交渉などで、心身ともに疲弊してしまった。
「もっと元気なうちに、早く進めておけば良かった」という後悔です。
墓じまいは、想像以上に多くの手順と時間を要するものです。
大切なことを決める判断力や、あちこちへ足を運ぶ体力は、ご年齢とともにどうしても難しくなっていく現実があります。
「まだ大丈夫」と思っているうちに時が過ぎ、気力も体力も必要な決断が、大きな負担になってしまうのです。
墓じまいの後悔を回避する5つの対策

先ほどご紹介した5つの後悔の事例。
それらを避けるために、墓じまいを実行する前に必ず確認しておきたい対策を、具体的に解説いたします。
一つひとつ、ご自身の心に問いかけながら読み進めてみてください。
対策1:親族に対して「報告」ではなく「相談」を行うこと
墓じまいをなぜ検討しているのか、その理由を丁寧に伝えることが大切です。
例えば、お墓の管理が体力的に難しくなってきた負担や、将来の承継者への不安など、具体的な事情をお話しし、理解を求める姿勢を見せましょう。
これは、決定事項を伝える「報告」ではなく、皆の意見を聞く「相談」という形をとることが重要です。
墓じまいにかかる費用負担についても、この段階で事前に話し合っておくことが望まれます。
もし反対の意見が出た場合に備えて、代替案を考えておくことも大切です。例えば、ご親族で費用や管理の負担を分担してお墓を維持する方法や、ご遺骨の一部だけを別の場所に移す「分骨(ぶんこつ)」といった選択肢もございます。
対策2:費用は「総額」で見積もりを取り、比較検討すること
墓じまいには、下記のような費用がかかります。
1.墓石の撤去費用
2.閉眼供養などのお布施
3.離檀料としてのお包み
4.新しい納骨先の費用
5.行政手続きの費用
費用が必要となる項目をあらかじめリストアップしてみましょう。
これらの「総額」を把握することが重要です。
特に墓石の撤去については、お寺様から石材店が指定されている場合を除き、複数の石材店から見積もり(相見積もり)を取り、内容や費用を比較検討することをおすすめします。
墓じまいの費用やお布施について、さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
>墓じまいにかかる費用を徹底解説!平均費用や内訳、費用を抑えるポイントまで解説
対策3:納骨先はご家族で「何を重視するか」を話し合うこと
新しいご遺骨の行き先となる納骨先選びは、ご家族の供養のあり方そのものに関わります。
安易に費用だけで決めてしまうと、後悔につながるかもしれません。
以下の3つの点について、ご家族で優先順位を整理しておくことが、後悔しない納骨先選びにつながります。
1.ご遺骨の扱い:「個別」で安置されることを望むか、あるいは他の方々と一緒になる「合祀(ごうし)」でよいか。
2.お参りの対象:お墓やシンボルツリーなど、具体的に「手を合わせる場所」が必要かどうか。
3.費用:最初にかかる初期費用と、その後に続く年間管理費はいくらかかるのか。
対策4:寺院に対して「感謝」と「丁寧な経緯」を伝えること
寺院にご相談に伺う際は、まず「これまでご先祖様を長きにわたり供養していただいたことへの感謝」の気持ちを、誠心誠意お伝えすることが最も大切です。
その上で、「跡継ぎがいない」「お墓が遠方で管理が難しい」など、墓じまいを決断するに至った、やむを得ない事情を丁寧にご説明し、ご理解(ご承諾)を得るよう努めます。
「離檀料」については、法的な支払い義務があるものではありません。しかし、これまでの感謝の気持ちを示すものとして「お布施」や「御礼」としてお包みするのが、日本において長らく続いている慣例とされています。
対策5:墓じまいは心身ともに元気なうちに計画を行うこと
墓じまいは、ご親族との話し合いから行政手続き、新しい納骨先の手配まで、すべてが完了するまでに半年から1年ほどかかることも珍しくありません。
体力と気力、そして冷静な判断力が必要な、長期のプロジェクトです。
「いつかやろう」と先延ばしにせず、心身ともに元気なうちに、早めに計画をスタートすることが望まれます。
また、お寺様のご繁忙期であるお盆やお彼岸、年末年始の時期は避けて、ご相談に伺うと、お互いに落ち着いてお話ができるでしょう。
墓じまいにおけるメリットとデメリット
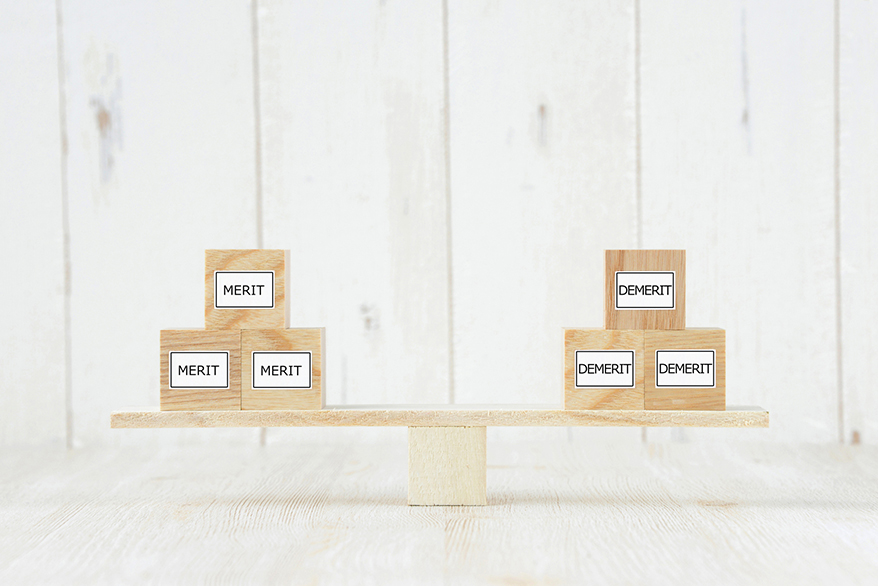
墓じまいには、もちろん良い側面と、注意すべき側面があります。
決断を下す前に、ここで改めて、メリットとデメリットを心の中で静かに整理し、ご自身とご家族の決断の材料といたしましょう。
墓じまいの主なメリット
墓じまいをすることで得られる、最も大きなメリットは「負担の軽減」です。
まず、管理の負担からの解放です。
遠方のお墓への移動や、夏の暑い時期の草むしり、お墓掃除といった肉体的・時間的負担が軽減されます。
次に、経済的な負担の軽減です。
将来にわたって支払い続ける必要があった、お墓の年間管理費や維持費が不要となります。
そして何より、精神的な負担からの解放です。
「お墓を将来どうしよう」という漠然とした不安や、「子どもたちに負い目を残してしまうのではないか」という心の重荷から解放されることは、大きなメリットといえるでしょう。
墓じまいの主なデメリット
デメリットとしては、まず墓じまいを実行する際に、まとまった初期費用がかかることが挙げられます。
墓石の撤去費用、離檀のお布施、そして新しい納骨先の費用などです。
また、先ほどの対策の章でも触れましたが、進め方次第では、大切なご親族や寺院との関係が悪化してしまうリスクもあります。
そして、ご先祖様から続いてきた「お墓」という形がなくなることで、供養の形が変わることに、心情的な寂しさや喪失感を覚える可能性も、デメリットとして考えておく必要があります。
墓じまい完了までの7つのステップ

墓じまいを決意された後、実際にどのような手順で物事を進めていけばよいのでしょうか。
ご親族との話し合いから、行政での手続き、そして新しい納骨先へのご供養まで、やるべきことは多岐にわたります。
不安を感じられるかもしれませんが、一つひとつのステップを順に確認していくことで、全体の流れが見えてまいります。
ここでは、一般的な墓じまいの流れを、7つのステップに分けてご説明します。
ステップ1:親族・家族間の合意形成
まず最初に行うべき、最も大切なステップです。
なぜ墓じまいが必要なのか、その理由(管理の負担や将来への不安など)をご家族やご親族に丁寧に説明し、皆様の理解と合意を得ます。
ここでの十分な対話が、後のトラブルを避ける鍵となります。
ステップ2:墓地管理者(寺院など)への相談・承諾
次に、現在お墓がある墓地の管理者様(寺院や霊園の管理事務所など)へ、墓じまいの意向を伝えます。
これまでお世話になった感謝の気持ちを込めてご相談し、承諾を得ます。この時、離檀料(りだんりょう)の有無や、墓石撤去の指定業者、必要な手続きについても確認しておくとよいでしょう。
ステップ3:新しい納骨先(改葬先)の決定・契約
ご遺骨を新しくお納めする場所(改葬先)を決めます。
納骨堂や樹木葬、永代供養墓など、様々な選択肢がありますので、後悔のないよう、できれば現地へ見学に足を運び、ご自身の目で確かめてから契約します。
契約後、その納骨先から「受入証明書(永代使用許可証など)」を発行してもらいます。これは次のステップで必要になります。
ステップ4:行政手続き(改葬許可申請)
墓じまい(改葬)を行うには、法的な許可が必要です。
現在のお墓がある市区町村の役所(東京都江戸川区や埼玉県東松山市、千葉県船橋市など、多くは戸籍担当課や環境衛生課が窓口です)で「改葬許可申請書」を入手します。
この申請書に必要事項を記入し、「現在の墓地管理者様の署名・捺印」と、ステップ3で取得した「新しい納骨先の受入証明書」を添えて提出します。
書類に不備がなければ、「改葬許可証」が発行されます。
ステップ5:閉眼供養(魂抜き)と遺骨の取り出し
「改葬許可証」を現在の墓地管理者様へ提示し、お墓からご遺骨を取り出す日を調整します。
ご遺骨を取り出す前には、僧侶にお越しいただき、墓石に宿るとされる故人様の魂を抜くための法要、いわゆる「閉眼供養」(「魂抜き」や「お性根抜き」とも呼ばれます)を執り行います。
ステップ6:墓石の解体・撤去工事
閉眼供養が済み、ご遺骨を取り出した後、石材店に墓石の解体・撤去工事を依頼します。
お墓があった場所を更地の状態に戻し、きれいにして墓地の管理者様へ返還します。これで、元の墓地での手続きは完了となります。
ステップ7:新しい納骨先への納骨・法要
取り出したご遺骨を、ステップ3で契約した新しい納骨先へ持参します。
その際、ステップ4で取得した「改葬許可証」を必ず提出してください。
そして、新しい場所で「納骨法要」(新しくお墓を建てた場合は「開眼供養」など)を執り行い、ご遺骨をお納めします。
これで、墓じまいの一連の流れがすべて完了となります。
墓じまい後の供養の選択肢

墓じまいをした後のご遺骨を、どのようにご供養していくか。
かつてはお墓を新しく建て直す「改葬」が主でしたが、現代ではご家族のあり方やお気持ちに寄り添う、多様な選択肢が生まれています。
どれが優れているということではなく、ご自身やご家族が「この形なら心安らかに手を合わせられる」と感じられることが大切です。
ここでは、代表的な6つの供養の形をご紹介します。
1.永代供養墓(合祀墓・集合墓)
お寺様や霊園が、ご家族に代わって永続的にご遺骨の管理・供養を行ってくれるお墓のことです。
特徴としては、費用を比較的抑えられる点や、将来の管理の心配がない点が挙げられます。
ただし、多くの場合、一定期間が過ぎると、他の方々のご遺骨と一緒に埋葬される「合祀(ごうし)」となる点には、事前の理解が必要です。
2.納骨堂
主に建物の中にある、ご遺骨を納めるための施設です。
ロッカー式や仏壇式、自動搬送式など、様々なタイプがあります。
メリットとしては、天候に関わらずお参りがしやすいこと、駅の近くなど利便性の高い場所にあることが多い点です。
注意点として、永代供養墓と同様に、個別で安置される期間が決まっている場合もあります。
3.樹木葬
墓石の代わりに、樹木や草花をシンボル(墓標)としてご遺骨を埋葬する形です。
「自然に還りたい」というお考えの方に選ばれることが増えています。
緑豊かな環境で眠れることがメリットですが、一度埋葬するとご遺骨の返還が難しいタイプや、次第に自然の土に還っていく形のものもあります。
4.散骨(自然葬)
ご遺骨を細かく粉末状(粉骨)にして、海や山、空などに撒く供養の方法です。
故人様が愛した自然に還ることができる、という点が特徴です。費用も抑えられる傾向にあります。
ただし、ご遺骨は手元に一切残らず、お墓のような「手を合わせる具体的な場所」がなくなるため、後にお参りの対象がなくて寂しさを感じる方もいらっしゃいます。
5.手元供養
ご遺骨のすべて、または一部を、ご自宅などで保管して供養する形です。
小さな骨壺や、ペンダントなどのアクセサリーにご遺骨を納める方法があります。
故人様をいつも身近に感じていられることが最大のメリットです。
一方で、将来的にそのご遺骨をどなたが引き継ぐのか、最終的にどうするのかを、あらかじめ考えておく必要があります。
6.新しいお墓(改葬)
これは、従来からある「お墓のお引っ越し」です。
遠方にあったお墓を墓じまいし、ご自宅の近くなど、お参りしやすい利便性の良い場所に新しくお墓を建てます。
ご先祖様からのお墓参りの形をそのまま継続できることがメリットです。
ただし、他の選択肢と比べて、新しい墓石の建立費用などがかかるため、費用は最も高額になる傾向があります。
墓じまいに関するよくある質問(Q&A)

墓じまいを具体的に考え始めると、細かな疑問や現実的な不安が心に浮かんでくるものです。
特に費用や手続きに関しては、多くの方が「これで後悔しないだろうか」とお悩みになります。
ここでは、よく寄せられるご質問にお答えします。心のつかえを解きほぐす一助となれば幸いです。
Q.墓じまいをすると「永代使用料」は返ってきますか?
A.結論から申し上げますと、一度納めた「永代使用料(えいたいしようりょう)」は、返金されないのが一般的です。
永代使用料とは、その区画の土地の所有権を購入した代金ではなく、お墓の土地を永代にわたって「使用する権利」を得るための費用とされています。
そのため、墓じまいをしてその権利を手放す(墓地を返還する)場合でも、契約上、返金は行われないことがほとんどです。
Q.「離檀料」は必ず支払うものですか?高額請求が不安です。
A.「離檀料(りだんりょう)」について、法的な支払い義務があるわけではありません。
しかし、これはご先祖様が長きにわたりお世話になった寺院(菩提寺)とのご縁を円満に終えるための、日本に根付いた慣例ともいえます。
これまでご先祖様の供養を担ってくださったことへの「感謝の気持ち」として、「お布施」や「御礼」という形でお渡しするのが一般的です。
金額についてはお寺様との関係性にもよりますが、高額な請求をされて後悔するのではないか、というご不安もあるかと存じます。
大切なのは、やはり事前の丁寧なコミュニケーションです。「後悔を回避する5つの鉄則」でも触れましたが、一方的な通告ではなく、感謝とやむを得ない事情を誠心誠意お伝えすることが、トラブルを避ける何よりの鍵となります。
Q.手続きにかかる期間はどれくらいですか?
A.すべての手続きが完了するまでの期間は、一般的に半年から1年程度かかると考えておくとよいでしょう。
ご親族皆様の合意を得るまでに時間がかかることもありますし、寺院とのご相談や、行政での「改葬許可証」の取得、石材店の手配なども必要です。
特に、寺院が忙しい時期(お盆やお彼岸など)は、話し合いや法要の日程調整が難しい場合もあります。
「いつかやろう」と思っていると、想像以上に時間がかかってしまうため、早めに準備を始めることが大切です。
Q.指定石材店が異常に高額な場合はどうすべきですか?
A.墓地によっては、墓石の撤去工事を行う石材店が指定されている場合があります。
その費用が、ご自身で探した他の石材店の見積もりと比べて、あまりにも高額で納得が難しい、というお悩みも耳にします。
まずは、なぜその金額になるのか、内訳をよく確認し、墓地の管理者様(お寺様や霊園事務所)に率直にご相談ください。
それでも正当な理由なく、話し合いに応じてもらえないような場合は、お住まいの自治体の消費生活センターや、国民生活センター、あるいは弁護士などの専門家にご相談する、という選択肢もあります。
證大寺のご案内

墓じまいの費用や、ご家族・ご親族との話し合いの進め方について、ここまでご紹介してまいりました。しかし、実際にご自身の状況に当てはめてみると、どのように進めたらよいか、どなたに相談すべきか、迷われることも多いかと存じます。
墓じまい相談の実績と専門知識
私たち證大寺(しょうだいじ)は、これまで1,000件を超える墓じまいや改葬(お引越し)に関するご相談をお受けしてまいりました。
人生の大きな節目である墓じまいを、皆様が安心して進められますよう、経験豊富なスタッフが皆様のお気持ちに静かに寄り添い、お手伝いをさせていただきます。費用のお悩みから、お手続きの具体的な流れ、ご親族へのご説明の仕方まで、どのようなことでもお気軽にお尋ねください。
改葬先の選択肢としての霊園拠点
證大寺では、墓じまい後の新しいご供養の場所として、様々な選択肢をご用意しております。
・證大寺 江戸川本坊(東京都江戸川区)
・森林公園 昭和浄苑(埼玉県東松山市)
・船橋 昭和浄苑(千葉県船橋市)
いずれも、お墓参りのしやすい環境を大切にした霊園です。永代供養墓や樹木葬など、現代の多様なニーズにお応えできるご供養の形をご提案しております。
安心のサポート体制(無料相談会・宗派不問)
皆様のお悩みに、より丁寧にお応えするため、證大寺では「無料相談会」を随時開催しております。まずは皆様のお話をじっくりとお伺いすることから始めさせていただきますので、どうぞお気軽にご参加ください。
また、證大寺の永代供養墓は、宗旨・宗派を問わず、どなたでもお受け入れしております。これまでのお寺様が異なる宗派であった場合でも、何ら心配はいりません。ご先祖様を大切に想うお気持ちを、そのままお持ちいただければと思います。
墓じまいは、皆様のご事情や想いによって、その形もさまざまです。證大寺は、皆様が納得のいく新たな一歩を踏み出すための、信頼できるパートナーでありたいと願っております。
ご相談について詳しくは、下記までメールでお問合せください。
edogawa_hp@sinran.com
まとめ:後悔しない墓じまいは「準備」と「対話」で決まる
墓じまいという大切な決断において、多くの方が感じる「後悔」の根本的な原因は、突き詰めると「準備不足」と「コミュニケーション不足」にあるといえるでしょう。
後悔しない墓じまいのために最も大切なこと。
それは、ご自身の思いだけでなく、ご先祖様のお墓に心を寄せるご親族との「十分な対話」を重ねること。
そして、費用や利便性だけにとらわれず、ご自身とご家族がこの先も心安らかに手を合わせられる「供養の形(納骨先)」を、慎重に選ぶことです。
墓じまいは、法的な手続きや、お寺様とのデリケートな交渉も伴います。
「どう進めたらよいか分からない」「これで本当に後悔しないだろうか」と、不安な点をどうかお一人で抱え込まないでください。
皆様の心が少しでも軽くなり、ご先祖様への感謝の気持ちを大切にしながら次の一歩を踏み出せるよう、静かに寄り添わせていただきます。










