遺骨はどうすればいい?気をつけたい法律と主な供養方法

墓じまいなどを契機に、遺骨をどうするべきかと悩む方が増えています。また墓じまい以外でも、遺骨の取り扱いに直面することもありえます。この記事では、遺骨の取り扱いや永代供養の選択肢、法律やマナーの注意点を解説。墓じまいや改葬の流れも紹介し、後悔しない判断のヒントをお伝えします。
目次
●遺骨をどうすればいいか、悩む人が増えている理由
●遺骨を処分する際に気をつけたい法律とマナー
●遺骨の主な供養方法
●「永代供養墓」は管理不要で現代的な選択肢
●墓じまい後の改葬・処分の流れ
●お骨の納骨先でお悩みなら|證大寺
●まとめ
遺骨をどうすればいいか、悩む人が増えている理由

遺骨について悩む人が増えているのは、墓じまいと関連することが多いようです。また墓じまい以外でも遺骨の問題に直面することがあります。まずは、それらの背景を見ていきましょう。
お墓を持たない・継がないという選択が一般的に
遺骨を納めるお墓がないという理由で、遺骨をどう供養するかで悩む場合があります。最近では、故人や遺族の意思でお墓を持たない選択をする方も増えています。また先祖代々のお墓があっても、お墓を継がない、いまあるお墓には入らないという方もいます。そのような場合、遺族は遺骨をどうするかで悩むことになります。
墓じまいをきっかけに「遺骨の行き先」に悩む人が増加
このほか最近増えている墓じまいの過程で、遺骨の行き先に悩む方も多くなっています。墓じまいとは、お墓を解体して更地にして霊園等に返却するというものです。その際、もともとのお墓にあった遺骨は改葬することになります。しかし先祖代々のお墓の場合は、誰のものかよくわからない古い遺骨が納められていることもあります。近い親族の遺骨は改葬するにしても、そのような古い遺骨はどうすればいいのか。また遺骨の数が多くて、改葬先に入りきらないこともあります。このような場合、墓じまいをきっかけに遺骨をどうするか悩むことになってしまいます。
■親族や兄弟と意見が分かれるケースも

墓じまいで、もともとのお墓にあった遺骨をどうするかについては、親族や兄弟で意見が分かれるケースも多くあるようです。遠方にある先祖代々墓を維持管理することができない、法要の取り仕切りも難しいからと、墓じまいを訴えても「墓じまいとはなにごとか」という価値観の親族がいる場合もあります。また墓じまいは認めても、改葬先の場所や費用などで親族間に意見の相違があり、場合によってはトラブルに発展するケースも珍しくありません。
その他の理由で悩むケースも
お墓があっても墓じまいをしなくても、遺骨の行き先に悩まされることもあります。たとえば遠縁の親族が亡くなり、遺骨の引き取りを要請されることがあります。会ったこともない親戚の遺骨の引き取り手になった、会ったことはあるものの自分たちのお墓に入れて供養するには抵抗があるといった場合は、遺骨をどうするかで悩むことになります。このほか、手元供養をしていた遺骨があり、供養する人が亡くなった場合なども、遺骨の行き先に悩むことになります。
それ以外にも、お墓はあるもののカロートがいっぱいになってしまい、骨壺が物理的に入らなくなって遺骨の処分に悩むケースもあります。ただしこの場合は、古い遺骨を取り出して粉骨し、カロートの下の土に埋めるか、いくつかの粉骨した遺骨をまとめて1つの骨壺に納めるのが一般的です。
遺骨の取り扱いで気をつけたい法律とマナー
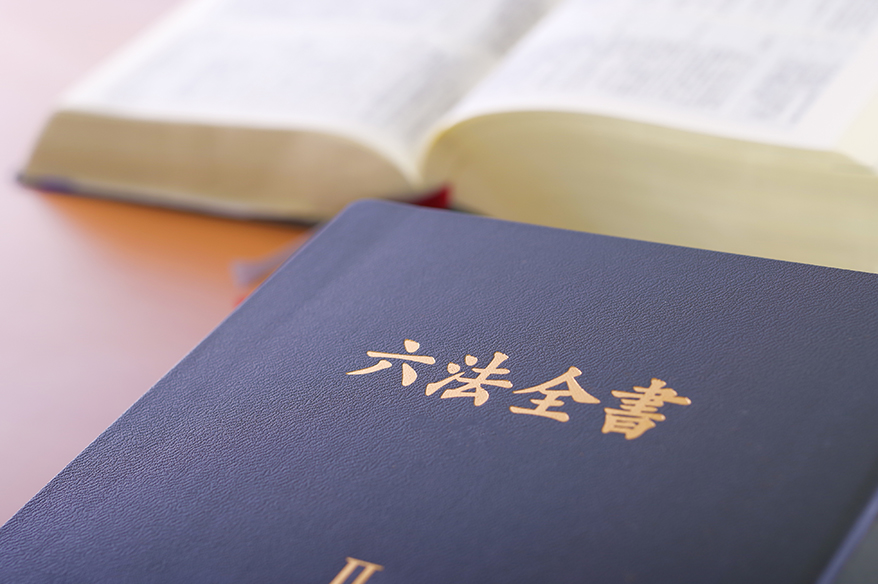
遺骨の取り扱い方については、実は法律で定められています。対処方法を誤ると、処罰される可能性があります。遺骨に関する法律のほか、起こりやすいトラブルや注意ポイントなどを紹介します。
「勝手に捨てる」は違法?遺骨の法的位置づけ
遺骨について法律では、「刑法第190条」で「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する」と定められています。遺骨をゴミに出したり遺棄したりすると、罰せられることになります。また「墓地、埋葬に関する法律第4条」では「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」とあり、墓地以外の場所に埋葬することも処罰の対象となります。身内の遺骨でも自分の私有地であっても、勝手に埋葬すると罰せられます。
親族間トラブルを避けるための話し合いのポイント
遺骨に関するトラブルで起こりやすいのは、やはり墓じまいに関連する場合でしょう。現代ではお墓に対する価値観が人によって大きく違います。墓じまいしたくても、親族に違う価値観の人が居ると反対されることもあります。また墓じまい自体には納得してもらえても、改葬先について苦言がでるケースも。トラブルを避けるためには、親族とじっくり話し合うことが大切です。話し合いのポイントとしては、墓じまいの必要性を伝えるのはもちろんのこと、墓じまいするほかに良い考えがあるかどうか、相手の意見を聞いて徐々に折り合いを付けていくようにしましょう。また改葬先についても、お墓が遠くなるなどの理由で反対されたら、元のお墓がある墓地の合祀墓を提案するなどして、納得してもらえるように相談を重ねるようにしましょう。
供養意識・将来の管理負担で考える
遺骨をどうするのかは、供養の意識を持ちながらも、将来の管理負担で考えることが重要です。墓じまいをしないと、将来にわたって管理負担が続くことになります。年間管理費も支払えなくなって無縁仏化すると、お墓が強制撤去されることになり、思うような供養ができなくなる可能性もあります。墓じまいを考える場合はもちろん、親族との話し合いの過程でも、遺骨の供養や管理負担についても勘案することが大切だといえるでしょう。
また墓じまいをした場合、永代供養にすることが多いですが、永代供養は供養を放棄するということではありません。永代供養はお寺や霊園に託すことで、精神的・肉体的・経済的な負担を軽減しながら、しっかり供養できる方法だといえます。
遺骨の主な供養方法

お墓がない場合の遺骨の供養や、墓じまいの改葬先としては、以下のような方法があります。
散骨|自然に還すという新しい供養のかたち
散骨とは、遺骨を粉状に細かく砕き、山や海などに撒いて自然に還すという新しい形の供養方法です。お骨が残らず、お墓を用意する必要もありません。海に撒く海洋散骨は、特に注目を集めている供養方法です。業者に委託散骨する形なら、比較的安価な費用で行えるというメリットもあります。
合祀墓|費用を抑えた永代供養の選択肢
合祀墓とは、大きなお墓の下に複数の遺骨を埋葬するスペースがあり、たくさんの遺骨を一緒に供養するというものです。合祀すると他の遺骨と混ざるため、一度埋葬すると遺骨を取り戻すことはできません。その代わり埋葬費用を抑えることができ、個別の管理費も必要ないことが多いです。また合祀墓のほとんどは、永代供養という形でお寺や霊園が末永く供養してくれます。
樹木葬|自然の中で眠る新しいスタイル

樹木葬は、木や草花を墓標とする新しいスタイルのお墓で、自然の中で眠れると最近人気を集めています。通常のお墓との違いは、継承を前提とせず、一代限りとすることがほとんどだという点です。そのため多くの樹木葬では永代供養がついていて、霊園やお寺が末永く供養を続けてくれます。また年間管理費等もがかからない場合が多いのも特長です。
樹木葬は大別すると、山中などにある「里山型」と、霊園の一角などにある「庭園型」の2タイプに分けられます。タイプによって特色やメリットも違うので、樹木葬について詳しく知りたい方は、リンク先の記事を参考にしてみてください。樹木葬について詳しく知りたい方は、樹木葬の費用や種類を解説した記事をご覧ください。
樹木葬の費用はどれくらい?埋葬方法ごとの費用相場と安く抑えるためのポイントを解説
納骨堂|都市部で増えているコンパクトな供養施設
遺骨を納骨堂に安置するという方法もあります。納骨堂は都市部に多い屋内型の施設で、遺骨を骨壷に入れたまま室内で安置するというものです。かつては遺骨の仮置き場所として始まりましたが、現代では新しいスタイルのお墓として利用されることがほとんどです。交通の便が良い場所にあることが多いため、お墓参りしやすいというメリットがあります。納骨堂も樹木葬同様で、継承を前提としないタイプがほとんどで、永代供養が付いているものが主流です。ただし一定の期間が過ぎると合祀されるというものが多く、合祀前までは年間管理費がかかるのが一般的です。
納骨堂について詳しくはリンク先の記事を参考にしてください。
納骨堂とは?お墓との違いやメリット、デメリットを解説
「永代供養墓」は管理不要で現代的な選択肢

上記で遺骨のさまざまな供養方法について説明しましたが、選択肢として現実的なのは永代供養墓といえるかもしれません。遺骨の供養やお墓の管理をする必要がなく、年間管理費も不要なことが多いためです。
永代供養とは?管理者による供養が続くシステム
そもそも永代供養とは、供養方法のひとつです。通常のお墓は遺族が管理して継承し、供養も同様に遺族が続けていくことになります。一方、永代供養は、遺族の代わりにお寺や霊園などの墓地管理者が遺骨の供養・管理を永代に渡り行うというものです。このため継承者を必要とせず、お墓を管理する負担が軽減でき、無縁仏になる心配もありません。
合祀型・個別型・樹木葬や納骨堂などタイプの違い
永代供養墓にはさまざまな種類があります。前述した合祀墓もそのひとつで、費用が比較的抑えられ、合祀墓によっては1体3万円〜5万円で納骨できる場合もあります。
埋葬方法が合祀ではなく、遺骨ごとに骨壺に収める集合型や個別型といった永代供養墓もありますが、費用は合祀墓に比べると高い傾向となっています。このほか永代供養付きの樹木葬や納骨堂もなども、永代供養墓のひとつと捉えられることができます。
生前申込や墓じまい後の移行も可能
永代供養墓の中でも、樹木葬や納骨堂などは生前予約を行っている場合が多くあります。生前予約ですれば、自分が納得いく場所に埋葬してもらえるというメリットがあります。
また墓じまいの改葬先として、樹木葬や納骨堂、合祀墓などに遺骨が移行されることもよく見られます。ただし樹木葬や納骨堂は、埋葬できる人数が決まっていることが一般的です。そのため代々の墓の遺骨を、すべて移すことが困難な場合もあります。しかし墓じまいの改葬先は、すべて同じ場所に改葬するという決まりはありません。そのため、両親など近い親族は樹木葬や納骨堂に改葬し、遠い親族は合祀墓に改葬するなどの例も見受けられます。
墓じまい後の改葬・供養の流れ

墓じまいで遺骨を取り出す場合。その後の改葬の流れについての概略や注意点などを紹介します。
墓じまい全体の詳しい手順等については、リンク先の記事を参考にしてください。
https://shoudaiji.or.jp/baton/post14/#hakajimainonagare
墓じまいから改葬までの主な手順
墓じまいは、墓地を更地に戻して霊園やお寺に返却するというものです。その際に、墓石などを撤去する解体工事を行います。またお墓に納めてあった遺骨は、取り出して改葬することになります。これら一連のプロセスを行うには、霊園やお寺の許可をとるだけでなく、行政手続きも必要となります。手続きを踏まず許可なく改葬すると、罰金や拘留の可能性もあります。
改葬許可証が必要になる場面とは
お墓にあった遺骨を取り出す際には、「改葬許可証」が必要となります。また改葬先へ遺骨を移す際にも改葬許可証は必要です。
改葬許可証は、墓じまいするお墓を管轄する自治体に申請書を提出して発行されるもので、遺骨1つにつき1通を申請します。この申請書を提出する際には、埋蔵証明書が必要です。埋蔵証明書はお墓の遺骨が誰のものであるかを証明するというもので、お寺や霊園などのお墓の管理者に発行してもらいます。
改葬許可証の申請時には、埋蔵証明書のほかに改葬先の受入証明書も必要です。遺骨を改葬せず散骨する場合、改葬許可証は法的には必須ではありません。ただし多くの散骨業者では、改葬許可証の提出を求めることが一般的となっています。
お寺や霊園のルール確認が重要
取り出した遺骨を永代供養墓に改葬することになったら、改葬先を選ぶ段階でお寺や霊園のルールを確認しておくことをおすすめします。永代供養墓の場合、お参りなどについてお寺や霊園ごとに独自の規則がある場合がほとんどです。たとえば里山型の樹木葬などでは、山火事を防ぐためにろうそくや線香などの火気を禁止しているところがあります。また納骨堂は開館時間が決まっていて、いつでもお参りできるわけではありません。納骨堂によっては参拝室でしかお参りできないタイプのものもあります。合祀墓ではお供え物を置くスペースがないというものもあります。通常のお墓と同様のお参りができないこともあるので、ルールを確認して納得できる場所を選ぶようにしましょう。
お骨の納骨先でお悩みなら|證大寺

写真:證大寺 船橋昭和浄苑の浄苑墓
墓じまいなどでの遺骨の供養方法について見てきました。さまざまな方法があるとわかったものの、具体的にどうすればいいかとお悩みなら、證大寺に相談してみてはいかがでしょうか。
證大寺は東京都江戸川区にある浄土真宗大谷派のお寺です。證大寺の特長は、生前の宗旨宗派不問で納骨できるという点です。またお墓の種類も豊富で、一般墓のほか樹木葬や納骨堂、合祀墓などがあります。本坊の墓地のほか、埼玉県の森林公園と千葉県の船橋で、昭和浄苑という霊園を直接運営しています。2つの昭和浄苑でも樹木葬や合祀墓があって、生前の宗旨宗派不問で納骨できます。
自分と家族に合った供養を選べる
證大寺は墓じまいの改葬先として実績があり、親身に相談にのってもらえると好評を得ています。たとえばある方は、先祖代々のお墓の墓じまいで遺骨の数が多く費用で悩んでいました。遺骨が多いと費用が嵩みがちですが、證大寺の合祀墓なら「5体まで」「10体まで」といった費用設定があります。證大寺から費用を軽減できる提案をしてもらえ、予算内で改葬することができました。このほか同じく墓じまいで、両親の遺骨は昭和浄苑の樹木葬に、遠い祖先は樹木葬の合葬区画で自然に還るという選択をした例もあります。
證大寺では、樹木葬や納骨堂などの生前予約も受け付けており、自身の納骨先について悩んでいる方の相談にものってくれます。納骨先で悩んでいるなら、自分や家族にあった供養が選べる證大寺に相談してみてはいかがでしょうか。
證大寺:https://shoudaiji.or.jp/
證大寺 江戸川:https://edogawa2.eitaikuyou.life/
森林公園 昭和浄苑:https://higashimatsuyama2.eitaikuyou.life/
船橋 昭和浄苑:https://funabashi2.eitaikuyou.life/
★證大寺では、墓じまいに関する無料相談会も実施しています。
無料相談会については以下からお問合せください。
お問い合わせはこちら
まとめ

遺骨は故人とのつながりを感じる大切な存在です。墓じまいやお墓を持たない選択をした場合でも、その想いを託せる供養の方法を選ぶことが重要です。散骨や樹木葬、永代供養墓など、遺骨の処分方法にはさまざまな選択肢がありますが、どの方法も「故人を敬い、心を込めて見送る」ことが本質です。将来の管理や費用の負担を考慮しつつ、家族や親しい人と話し合い、納得できるかたちで供養を行うことが、故人への最大の敬意となります。










