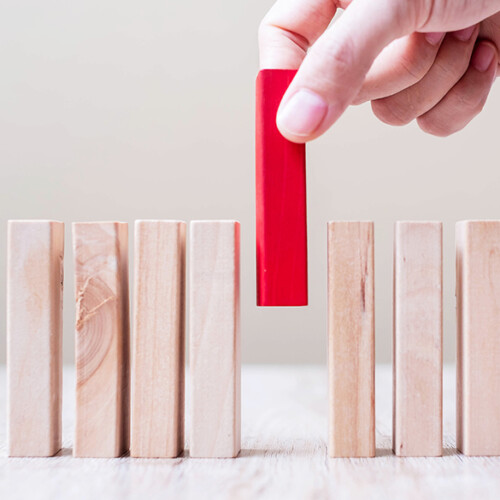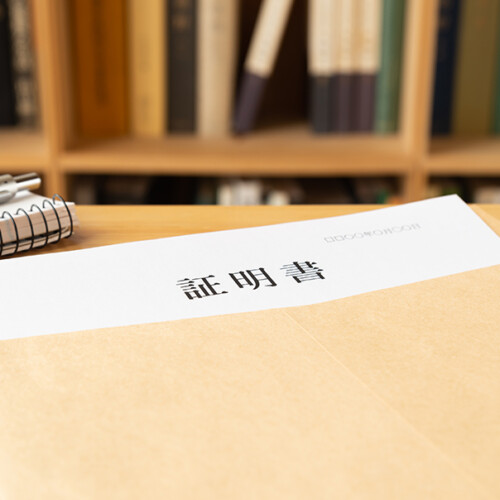納骨のやり方完全ガイド|流れ・費用・注意点をわかりやすく解説
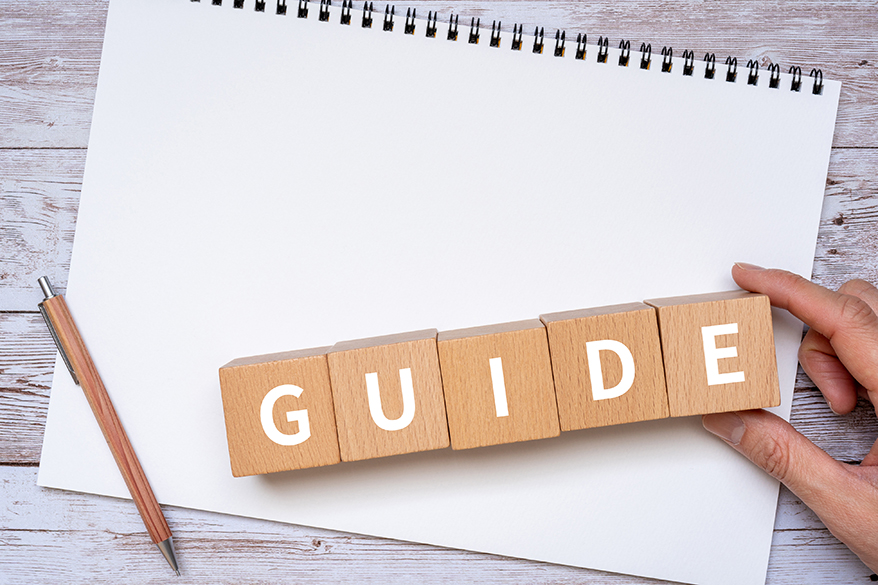
納骨とは、火葬して骨壺に収められた遺骨をお墓等に納めることです。葬儀や納骨式に参列したことはあっても、納骨を執り行ったことがないと細かい点までわからないことも多いでしょう。そこで納骨のやり方について、手順や流れ、費用や注意点まで網羅して完全ガイドします。
目次
●納骨のやり方|一般的な流れと手順
●納骨式の流れ
●お墓の種類別(納骨先別)納骨の方法
●納骨の費用目安
●納骨を安く抑える方法
●納骨の際の注意点とマナー
●よくある質問|納骨の疑問を解決!
●多彩な納骨先が選べる「證大寺」の納骨
●まとめ
納骨のやり方|一般的な流れと手順

納骨は、単に故人の遺骨をお墓に納めるというものではありません。納骨には手続きや儀式があり、遺族にとっては故人への想いを再確認したり心の整理をしたりする機会となります。まずは納骨を行う際の一般的な流れと手順を紹介します。
納骨の手順(1)納骨を行う場所の選択|お墓・納骨堂・永代供養墓など
納骨する場合、まずは納骨先を決める必要があります。先祖代々のお墓がある場合は、そこに入ることになるでしょう。しかし入るお墓がないというケースもあります。また先祖代々のお墓があっても、遠方のため別のお墓に納骨したいということもあるでしょう。そういった場合は、納骨先を探すことになります。新たなお墓を建てるというケースもありますが、現代では納骨堂や樹木葬、永代供養墓などを選択する方も増えています。どのような納骨先を選ぶかによって、費用相場は異なります。また納骨方法もお墓の種類によって変わってきます(詳細は後述参照)。新たな納骨先を探す場合は、希望や予算にあわせて選択するようにしましょう。
納骨の手順(2)使用許可証と埋葬許可証
納骨先が決まったら、納骨先から使用許可証を発行してもらいます。使用許可証とはお墓を所有していることを示す書類で、遺骨を埋葬してもよいという許可を証明するものです。先祖代々のお墓や親族でお墓を共有している場合は、そのお墓の管理者が持っているので、管理者から使用許可証を借りておくようにします。
使用許可証のほか、納骨には埋葬許可証も必要となります。埋葬許可証は火葬後に火葬場から発行されるものです。骨壺を納める白木の箱に一緒に入れられていることが多いので、納骨前に確認しましょう。
使用許可証と埋葬許可証がないと、納骨できなくなるので忘れないよう準備しておきましょう。
納骨の手順(3)日程調整と手配|事前準備から納骨式当日までにやること
納骨を行う際は、納骨式と呼ばれる儀式を行うことが一般的です。納骨式では僧侶に墓前に来て読経して貰うことになるので、菩提寺と相談して日にちを決めるなどの手配を行いましょう。納骨式に親族などの参列者を呼ぶ場合は、招待状を送付するようにします。また納骨式当日は納骨式が始まる前に管理事務所に出向き、使用許可証と埋葬証明書を提出して手続きを行います。
納骨式の流れ

納骨式ではどのようなことが行われるのでしょうか。納骨先となるお墓の種類や、宗旨・宗派によって多少異なる部分もありますが、一般墓を例として当日の流れを紹介します。
納骨式の流れ(1)焼香台・お供え・供花の準備
納骨式当日は、墓前に焼香台やお供え、供花などを置いて準備をします。お供えは季節の果物や賞味期限の長いお菓子などを選ぶのが一般的ですが、地域や宗派によっては決まりがある場合も。事前にお寺に相談して揃えておくようにしましょう。供花の花の種類は特に決まりがないものの、トゲのあるバラなどは避け、仏花として相応しいものを用意しましょう。そのほか線香やロウソク、遺影なども持参するようにします。
納骨式の流れ(2)遺族の挨拶
準備が整って僧侶が到着したら、まずは施主が挨拶をします。参列者や僧侶に感謝の気持ちを述べるようにしましょう。また挨拶とともに故人が生前受けた厚誼のお礼や、遺族の心情なども述べられるのが一般的です。納骨式後に会食を行う場合は、その案内もするようにしましょう。挨拶が終了したら、僧侶に読経をしてもらいます。
納骨式の流れ(3)納骨
僧侶の読経が終わったら、いよいよ納骨となります。納骨の一連の作業は、石材店などの業者に依頼して作業してもらうことがほとんどです。墓石の下にあるカロートと呼ばれる納骨室を開けて、骨壷を納めてもらいます。納骨後、墓石は元に戻されます。
納骨式の流れ(4)供養と焼香
遺骨がお墓に納められたら、僧侶が2度目の読経をして供養を行います。読経の途中で、僧侶の合図により参列者の焼香が始まります。焼香の順番はまず施主、続いて家族、親族と故人と縁の深い順番に行うのが一般的です。読経や焼香が終わったら納骨式は終了となります。会食を行う場合は会場に移動します。
お墓の種類別(納骨先別)納骨の方法

納骨の方法は、納骨先となるお墓の種類によって変わってきます。それぞれの納骨方法をお墓の種類別に紹介します。
一般募での納骨方法
一般墓とは墓石がある墓で、代々継承することが前提とされているものです。一般墓に納骨する際は、お墓の下にあるカロートに遺骨を納めることになります。
カロートの構造にはいくつかの種類があり、納骨棚が設けられている場合は、壺ごと棚に納められます。その際、入り口側に新しい遺骨がくるように置くのが一般的です。このほか土中に遺骨を還せる仕組みのカロートもあり、その場合は骨壷から遺骨を出して納めることになります。
納骨堂での納骨方法
納骨堂は屋内型の納骨施設です。納骨堂にはいくつかのタイプがありますが、その多くは個別の扉のついた納骨壇というスペースに骨壺ごと遺骨を納める形になっています。
永代供養墓での納骨方法
永代供養墓の納骨方法は、タイプによって異なります。永代供養墓には遺骨を収蔵できる安置棚が設けられ、遺骨を骨壺のまま一定期間安置できるものがあります。このほか最初から合祀し、骨壺から遺骨を取り出して納めるというタイプもあります。
樹木葬での納骨方法
樹木葬の場合も、タイプによって納骨方法は異なります。樹木葬は大別すると、里山型と庭園型があります。里山型は自然回帰を謳っているものが多いため、遺骨は骨壺から取り出して直接土中に納めるか、自然に還る素材の袋に入れて納骨されるのが一般的です。
一方、庭園型の場合は墓標となる樹木の近くに納骨スペースがあり、そこに納骨することになります。骨壺に入れたまま遺骨を納める、もしくは粉骨して専用の容器に移して納骨する形が主流となっています。
納骨の費用目安

納骨の費用は、どこに納骨するのか、納骨式を行うか否かによって変わってきます。納骨式にかかる費用と、それ以外の費用について説明します。
納骨式の費用
納骨式を行う場合は、僧侶へのお布施、お供え物などの費用が必要となります。また納骨式後には会食を催すことが多く、会食の費用や引出物の費用も生じます。僧侶へのお布施は3〜5万円が相場とされています。それ以外にお寺からお墓まで足を運んでもらう場合は、御車料を包みます。また僧侶が会食に参加しないのであれば御膳料を包みます。御車料と御膳料はそれぞれ5,000〜1万円程度包むのが一般的とされています。
会食を催す際の費用は、参列者1人あたり3,000〜1万円程度が目安となります。また引出物は1家族に1つ渡すのが通例で、1家族あたり3~5,000円が目安です。このほかお供え物の費用も必要で、5,000〜1万円程度が相場となっています。
納骨式以外の費用
納骨式以外の費用は、お墓がない場合にどこに納骨するかで大きく異なってきます。新たにお墓を建てる場合は150万円程度、納骨堂だと60万円程度、樹木葬だと50万円程度が平均とされています。
先祖代々などのお墓がある場合でも、墓石に名前を刻む彫刻料などが必要です。彫刻料の費用相場は3~5万円で、このほか納骨作業の料金は5,000~1万円程度が目安となっています。
納骨を安く抑える方法

納骨の費用を安く抑えるには、大きくわけて2つの方法があります。1つは納骨式を簡略化して費用を抑える方法で、もう1つは費用を抑えられる納骨先を選ぶという方法です。
納骨式を簡略化する
納骨式の費用を抑えたいなら、身内だけで納骨式を行うなど参列者を絞りましょう。最近では家族だけで行い、会食や引出物を省略して簡略化するケースも増えています。これだけでも費用は大幅に軽減できるでしょう。また稀に納骨式をしないというケースもあります。しかし納骨式は仏事であり、大切な儀式です。納骨式をせずに納骨だけするというのは、あまりおすすめできません。
費用が抑えられる納骨先を選ぶ
お墓がなくて納骨先を選ぶ際、費用を大きく抑えたいなら、合祀型の永代供養墓を選択するという方法があります。霊園や墓地によって異なるものの、5万円程度~で納骨できるところもあります。
このほかにお墓自体を持たずに供養する方法もあります。たとえば海や山に遺骨を撒く散骨では、業者に全て委託した場合は5万円程度、船をチャーターして家族で散骨した場合は20~30万円程度が相場とされています。また遺骨を自宅などで保管する手元供養という方法もあり、特別に費用をかけずに行うことができます。ただし手元供養は、なんらかの事情で供養が続けられなくなったら、いずれはどこかに納骨することになります。
納骨の際の注意点とマナー

納骨は、どのようなタイミングで行うのがよいかなど注意しておきたいことがあります。また納骨式に参列する場合にも、服装や持ち物などにマナーがあります。
納骨の時期
納骨の時期には特に決まりはありません。一般的には四十九日法要にあわせて行われることが多いですが、地域によっては火葬後にそのまま納骨式を行うこともあります。お墓を新たに建立するなど新たに納骨先を探す場合は、完成後や購入後に納骨することになります。そんな場合は、百箇日法要や新盆、一周忌や三回忌など、法要で親族が集まる機会に合わせて行われることが多いです。
このほか気持ちの整理がつかないなどといった理由で、すぐに納骨を行わないケースもあります。とはいえあまり長い間納骨をしないと周囲に心配をかけてしまうこともあるので、家族でよく話し合って納骨時期を決めるようにしましょう。
納骨式の服装・持ち物
納骨式を四十九日よりも前に行う場合は、喪服で参列するのがマナーです。四十九日以降に行う場合は平服で参列するのが一般的です。ただし平服といってもカジュアルではなく、ダークスーツや地味なワンピースなどを選ぶようにします。華美な服装を避けるだけでなく、宝飾品は結婚指輪など必要最低限にとどめ、メイクや髪型も派手にならないように注意しましょう。ただし身内だけで納骨式を行う場合や、真夏や真冬など天候の状況によってドレスコードが変わる場合があります。その場合でも参列者で統一することがマナーとなっているので、事前に確認するようにしましょう。
納骨式の持ち物として、施主はお供え物や数珠を持参します。また参列者は数珠のほかに香典を持って行くのが通例となっています。ただし香典は、身内だけで納骨式を行う場合は省略することもあるので、施主に確認するようにしましょう。
よくある質問|納骨の疑問を解決!

納骨についてのよくある質問をまとめました。疑問のある方はぜひ参考にしてください。
Q.納骨は必ずしなければいけないの?
遺骨を納骨せずに自宅等で保管することは、法律上も特に問題はありません。ただし遺骨を遺棄してしまうと法律違反となります。また私有地であっても遺骨を墓地以外の場所に埋めることはできません。「墓地、埋葬等に関する法律」により、「埋葬または焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に行なってはならない」と定められているため、遺棄したり墓地以外に埋めたりした場合は罰せられることになります。
Q.納骨できない場合はどうすればいい?
さまざまな事情で納骨できない場合は、手元供養するのがおすすめです。手元供養とは、自宅に祭壇を作るなどして骨壺を置き、供養することをいいます。ただし手元供養は、供養していた人が亡くなるなどの理由で、継承できなくなる恐れがあります。遺骨は遺棄することはできないので、将来のことも考えて納骨の準備をすすめるようにしたいものです。
Q.お墓がない場合の納骨先の選び方は?
現代では納骨先が多様化していて、一般墓のほかに樹木葬や納骨堂など新しい形のお墓も増えています。選択肢が豊富になった分、どこを選べばよいのか迷うことも多いでしょう。納骨先を選ぶ際には、まず継承できるお墓がいいのか、永代供養してもらえるものがいいのかなど希望を明確にします。さらにどれくらいの予算を欠けられるかも考えて、候補を絞っていくようにしましょう。
多彩な納骨先が選べる「證大寺」の納骨

東京都江戸川区にある證大寺にはお寺に墓地があるほか、千葉と埼玉で2つの昭和浄苑という霊園を直接運営しています。證大寺や昭和浄苑は、納骨先となるお墓の種類が多彩で、一般墓のほか樹木葬、納骨堂、永代供養墓などがあります。また「ペットと一緒に入れるお墓」という特徴もあり、ペットを家族同様に考える方からも人気があります。
證大寺は浄土真宗大谷派のお寺なので、供養は宗派の教えに基づいて行われますが、生前の宗旨宗派不問で入ることができます。多彩な選択肢の中から希望や事情に合わせて選ぶことができるので、納骨先に悩んでいたら證大寺に相談してみてはいかがでしょうか。
證大寺:https://shoudaiji.or.jp/
證大寺 江戸川:https://edogawa2.eitaikuyou.life/
森林公園 昭和浄苑:https://higashimatsuyama2.eitaikuyou.life/
船橋 昭和浄苑:https://funabashi2.eitaikuyou.life/
まとめ

納骨は一般的には納骨式という仏事も伴うものです。納骨についての知識を深めておけば、実際に行うことになった時も慌てないですむでしょう。お墓がないなどで新たに納骨先を探す場合は、予算はもちろん清掃など定期的な管理ができるのか、継承者がいるのかなどの点を加味して選択し、故人が安らかに眠れて遺族も安心してお参りできる場所を見つけるようにしましょう。